家族の日
- カテゴリ:家庭
- 2025/11/16 16:54:45
ニコットおみくじ(2025-11-16の運勢)

こんにちは!高気圧に覆われ、九州から東北まで広く晴れる。
北海道は午後から雨が降る所も。
沖縄は曇り。
最高気温は平年より高い所が多い。
【家族の日】 かぞくのひ Family Day
☆家族の日は毎年11月の第3日曜日で、
社会全体で子育てを支えることを目的とした記念日です。
<概要>
〇家族の日
@家族の日・家族の週間
★家族の日
内閣府が2007年(平成19年)に制定した特別な日です。
少子化が進む日本において、家族の重要性を再認識して、
地域社会が子育てを支える役割について考える良い機会となっています。
□日本の少子化
日本の少子化が本格的に始まったのは1970年代後半からで、
1990年代以降は政府も「少子化問題)として認識しました。
原因は、経済的な事や社会的要因が絡み合っています。
◆少子化の始まり
△1957年
合計特殊出生率(TFR)が、
人口置換水準(約2、1%)を始めて下回ります。
▲1974年以降
出生率低下が顕著(けんちょ)になりまして、
厚生省の「人口白書」で出生抑制政策が掲げられます。
△1970年後半
少子化のフェーズに入りまして、出生数が減少し続けます。
▲1992年
「少子化」という言葉が国民生活白書で公式に使用されまして、
社会問題として認識されます。
◇主な原因
▲晩婚化・未婚化
▽平均初婚年齢
・1980年:夫は27、8歳で、妻は25、2歳です。
・2023年:夫は31、1歳で、妻は29、7歳です。
▼50歳時点の未婚率
男性:28、25%、女性:17、81%です。
◆女性の社会進出とライフスタイルの進化
キャリア形式や教育期間の長期化によりまして、
結婚や出産が後回しになります。
△女性のキャリア形式と教育期間の長期化
▼女性のキャリア形式
・広義のキャリア
「キャリア」は単に職業経験だけではなく、
家庭生活や市民活動、ボランティア、
趣味等を含めた、人生全体の役割遂行を指します。
・女性特有の課題
・出産や子育て、介護といった生活面の影響を受けやすい
・社会に根強い男女の固定的役割分担意識により、
職業選択の幅が挟まりやすい
・非正規雇用の割合が高く、
キャリア形成に不利な立場に置かれやすい
・多様な役割の両立
女性は就労だけではなく、家庭や地域活動等、
多様な役割を果たしてきましたが、
経済的価値に直結しない活動は「見えない価値」とされまして、
評価されにくい傾向があります。
▼教育期間の長期化
・大学進学率の上昇
戦後から現代にかけて、女性の高等教育進学率は大幅に上昇し、
大学や大学院に進む女性が増えています。
これによって社会に出るまでの教育期間が長期化しています。
・キャリア形成への影響
・高学歴化により、専門職や正規雇用を志向する女性が増加
・就労開始年齢が遅れる為、
結婚や出産とのライフイベントとの調整が課題となっている
・教育期間の長期化は「キャリア意識の成熟」を促す一方で、
ライフコース設計に複雑さを加えている
◇経済的不安定さ
・若い世代の所得停滞
・非正規雇用の増加
・住宅費の高さ
これら等が結婚や出産を制約しています。
◆子育てコストの高さ
教育費や保健環境の不足が「子供を持ちにくい」状況を作っています。
日本では子育てコストが非常に高く、
教育費の負担や保険、子育て環境の不足が、
少子化の大きな要因となっています。
教育費や私立校や塾通いで膨らみまして、
保健環境は待機児童や制度利用の難しさが課題です。
さらに、医療や地域支援の不足も家庭の負担を増しています。
△子育てコストの現状
▼総額負担
第一子を0歳から高校3年生まで育てる費用は、
約2170万円(預貯金・保険を含まない場合)です。
含む場合は、約2570万円に達します。
▽生活費の比率
衣類や食費、生活用品等の生活費が、
常に年間費用の半分程度を占めまして、
年齢が上がるにつれて増加しています。
▼教育費の増大
都市部では私立学校や塾通いが一般的で、
教育費が家計を圧迫しています。
△教育環境の不足
▼公的支出の低さ
日本の教育期間への公的支出割合はOECD最低基準でありまして、
家庭の自己負担が大きいです。
●教育のOECD「教育政策委員会(Education Policy Committee)
・Education at a Glance(図表でみる教育)
・毎年公表される国際教育統計で、教育への投資や学習成果、
教員の労働環境等を数値で比較出来ます。
・例えば日本では、
高等教育への家計負担がOECD平均より大きいことが、
指摘されています。
・PISA(生徒の学習到達度調査)
・15歳を対象に、読解力や数学的リテラシー、
科学的リテラシーを3年ごとに調査しています。
・各国の教育の「質」を測る代表的な国際調査で、
日本も参加しています。
・TALIS(国際教員指導環境調査)
・教員の勤務時間や職務満足度、
ICT活用状況等を調査しています。
・日本の教員は、
世界最長の勤務時間を持つことが明らかになっています。
▽格差拡大
高所得層は私的教育投資を行う一方、
低所得層は公立教育に依存しまして、教育格差が広がっています。
▼学級運営の困難
小学校低学年で集中力不足や授業成立の難しさが指摘されまして、
教育環境の質にも課題があります。
問題 日本の少子化問題についてですが、社会的要因もあります。
その社会的要因について、
次の文章の???に入る言葉を教えてください。
〇社会的要因
???や育児と仕事の両立の難しさや、
出産や育児に対する社会的支援の不足です。
1、不法労働
2、長時間労働
3、非正規雇用
ヒント・・・〇???対策
・労働時間の適正管理
・業務効率化
・企業文化の改革
これら3つの法令遵守と同時に、
従業員の健康と生産性を守る為の多面的な取り組みが必要です。
時間外労働は原則は月45時間、年360時間で、
健康管理上は月80時間超が過労死ラインで医師面談が義務化です。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。





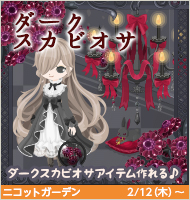

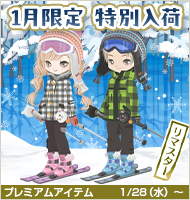





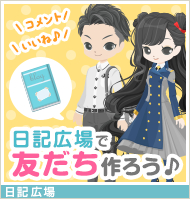












こんばんは!度々のコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
はい、おみくじですが「大大吉」です。
どうもありがとうございます。
そうですね、子育ての負担は圧倒的に女性に負担が多いですね。
ああ~、今後も女性の負担は減ることは少ないとの読みですか。
そうですね、支援金の方で増やしていただくことが出来たらですね。
問題の答えですが、2番の長時間労働が正解になります。
どうもおめでとうございました(祝)
長時間労働は性別に関わらず減らしていかないといけませんね。
家族の日
子育ての負担は確率的に圧倒的に女性に負担がありますよね。
男性は残業が当然という社会で、
減ることは今後もないと思っています。
高市政権になったので、支援金が増えればと希望を持っています。
答え 2