なんか現実を解って無くてマスコミの
- カテゴリ:日記
- 2025/10/30 20:52:20
なんか現実を解って無くてマスコミの自称専門家とやらが頓珍漢な事を言っていて居る様な事をどうして言うのか解らない。
彼らは何をマスコミを使ってしたいのか良く解らない。
まずねぇ、常識として理解して欲しいのがハンター不足だからと言って其れじゃお金に少し余裕があるから時間も少し余裕があるからハンターになってあげようと言う人が色々な試験や手続きをやってハーフライフルも取得して「ハンター」になりました。
で、其の「ハンター」が直ぐに鹿を撃てるかと言うと殆どが出来ません。
先ず山に入っても最悪は間違って人を撃って人を殺してしまう可能性もあるのです。
先ず先輩のベテランと言われる「鹿撃ちハンター」の人にくっついて「経験値」を上げます。
つまりHPを上げるのです。
最初はくっついて行って山を歩いて鹿の見つけ方を学びます。
次に先輩が実際に鹿を撃つ場面を体験します。
何度か一緒に連れて行って貰って次に鹿をみつけると実際に撃つ事をします。
殆どの人が鹿に逃げられます。
ハーフライフルの射程距離まで鹿に近づく事が難しく更に動いている鹿を撃つ事は難しいのです。
何度かベテランの人と行動して自分でも鹿を仕留める事が何度か出来る様になって「鹿撃ちハンター」になれるのです。
だからベテランハンターとの一緒に経験を積み重ねると言う事が凄く大事な過程なのです。
更に其の「要するにハーフライフルを持ってハンターの資格はあります」と言う人達に熊を撃てと言われても無理なのです。
「鹿撃ちハンター」の人達にまずベテランの熊を撃つ「狩猟ハンター」の人が熊を撃つ現場に連れて行って熊を撃つための色々な経験から来たり自分が更に過去にベテランハンターに教えて貰った事を伝授しながらどこを狙うのかとかを教えながら実際に熊を撃って見せます。
するとどの程度でどこを撃たないとそう簡単に熊は死なない事等を実際に目の前で実感します。
其れにはまず檻に入っていて殺す許可を得た熊を実際に撃って見せる事が「狩猟ハンター」を育てる1丁目1番地と言うか最初の経験値を上げるステップです。
警察も小銃で実際に実験をして「警察の小銃では熊は殺せない」と言う事が解ったと思います。
ハーフライフルでさえ1発では大人のヒグマは殺せませんよ。
基本的に熊をヒグマを殺す時は「狩猟ハンター」は複数人で行動するのが原則です。
ヒグマも狩猟ハンターもマジに命の駆け引きをお互いに意識して対自します。
明らかにヒグマはライオンやトラよりも強いかもしれないレベルです。
そして地の利も解って居ます。耳も良ければ嗅覚も圧倒的にヒグマの方が上なのです。
もっと解りやすく例えて見ましょう。
医学生が医師免許を取って外科医になりました。
いきなり脳外科手術をしろと言われても出来ますか?
先ず研修期間がありますね。次に実際の脳外の手術を何度も見学します。
次に助手として割と簡単な所を手伝わせて貰います。
次第に少しずつ難しい所をやらせてもらいます。
そして一人で責任のある手術を任せられますがベテランの脳外の先生が付き添います。
其れからやっと本格的な脳外の医者になりますね。
ハンターの場合も最初は大勢のハンターを取得してハーフライフルを持った人がベテランハンターと一緒に山に入って見学します。
次にベテランハンターが安全を確かめて割と仕留めやすい鹿へ実際に複数人で撃ってみます。
で何とか誰か弾が当たって怪我を負わせる事が出来てベテランハンターが逃げる前に止めを刺すか動きが鈍かったら再度ハンターたちに止めを撃たせたりします。
其れから初動解体の仕方を教えて貰います。
其れが終わると軽トラまで死んだ鹿を運びます。
そしてどこかで本格的な解体の仕方を教えて貰います。
其の時点である程度自分がハンターに向いているかいないかを感じてクレー射撃の方に行く方もお金持ちには多いです。
鹿の解体の現実はグロいですからね。
本格的「狩猟ハンター」を育てるのは大変なんです。
熊を仕留められるハンター等本当に少ないのですよ。
危険なわりに報酬は少ないですから寧ろ鹿肉専門店と繋がって居たり地域に鹿肉も解体出来る解体工場が在ったりするとハンターは少しは仕事がしやすいでしょう。
地域によってはそう言う地域もあるようです。
其処はちゃんと人間が食べれる鹿肉も特産品として扱っています。
北海道は広いですから其処まで仕留めた鹿肉を持って行くにはガソリン代がかかりますし冬道のアイスバーンとブリザードの中を軽トラを走らせて持って行くにはリスクが多すぎます。
ハーフライフルの免許をとっても鹿撃ちハンターになって残る人が少ないのもそう言った理由があるからです。
つまり割が合わないのですよ。







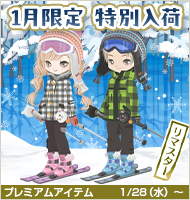





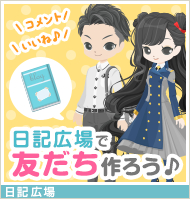















私が自分の解る範囲で詳しくハーフライフル(鹿撃ち用散弾銃、射程距離長くて腕が良ければ300m位)と本格的狩猟ライフル(射程距離600m位威力は散弾銃より別格にある)を説明するのは少しでも北海道の色々な現実を理解して欲しいからです。
狩猟免許を取る人が増えているのにハンターは減っていると言う現実を知って欲しいからです。
つまり狩猟免許をとっても「実質ハンター」と呼ばれる位になるのは難しいと言う事を知ってほしいのです。
~~~~~~~~~~
AI による概要
+3
狩猟免許保有者が増えている一方で実際のハンターが減っている主な理由は、「狩猟免許の取得者が増加している」という現状は事実ですが、そのほとんどが「ペーパーハンター」と呼ばれる実際に猟に出ない人が多いためです。ペーパーハンターが増加した背景には、アウトドア志向や趣味の流行などから免許を取得したものの、実際の狩猟に必要な知識や技術、登録への手続き方法がわからない、または高齢化により担い手不足が深刻化しているなど、複数の要因が挙げられます。
~~~~~~~~
そして今都会に出て来る熊が増えているのは単なる山の餌不足だけでないと言う事も理解して欲しいのです。
単なる山のエサ不足は昔からあったでしょう。
子供時代ですが漫画で「マタギ」を題材にしたのを読んだ記憶があります。
其処には人を恐れないで山里に降りて人を襲った熊を殺すまでの話が描いてありました。
山里へ下りて来た熊は必ず他の熊の見せしめとして殺さなければなりません。
更に人を襲って人間が弱いと認識した熊は殺さなければなりません。
何年もかけて執拗に其の熊を追って殺すまでの話だった様に思います。
一時一句覚えている訳ではありませんが主に熊の生息地の食糧不足を理由にしている人達の意見です。
私は熊の所謂生息地とされている場所に食料が大量に実ったとしても其れは其れで問題があると思っています。つまり食料が大量にあると其の年は雌の熊が繁殖する能力が多くなって子供を産んで熊の個体数が次の歳に増えると子供時代からヒグマの事は其れなりに聞いていますから次の年は熊が増えて危険だと聞いていました。
まあ、メガソーラーが熊の生息地に木を伐採して作って熊の生息地を狭めていると言うのは確かでしょうし其れは熊の生息地の木のみを減らす要因にはなっていると思います。
ですが其れではドングリを拾って山奥に大量に投下すれば済むとは思えないのです。
私は熊は人間は危険で無いと学習したと思っています。
其れが母親熊から小熊に伝わったとそして其の熊が大人になっても人間の近くで生息していて更に雌熊は大人になって人間の近くで繁殖して更に人間の生息地に来ていると思っています。
つまり山奥に餌が豊富にあって雌の繁殖が多くなって熊の個体数が増えて更に人間は危険で無く人間の食料を狙うのがおいしく栄養のある場所だと学習したと思っています。
つまり熊の個体数が増えたのと熊が人間は危険で無いと学習して人間の傍に栄養が在っておいしい食料があると学習したと思っています。
だから山にドングリを大量に投下して檻に捕獲した熊を山に戻しても何とかしてまた人間の傍に戻ってきますし、更に人間の生息地に近い場所で繁殖すると思っています。
其の人間の住んでいる場所に近い熊の生息地にメガソーラーを作る為に木を大量に伐採したと言うのも要因の一つだと思います。
私は熊に人間は危険だと学習させる必要があると思っています。
それと熊の本格的な生息地と人間の生息地との中間に作ったメガソーラーを作るのはやめた方が良いと思います。
人里に降りて来た熊は昔の様に必ず殺すと言う事をすべきだと思います。
態々本当の山奥へ危険を冒してまで行って熊を殺す必要はないですが
昔の人がやっていたように人里に降りて来た熊は殺すと人間は怖いと学習させる必要があると思います。