地震の発生確率の変更・これからの防災 保護
- カテゴリ:ニコリーあつめ
- 2025/09/27 07:59:57
バイオリンムシを保護しました。
2025/09/25

| 保護した場所 | 大きさ | レア度 |
|---|---|---|
| 神社広場 | 2.47cm |  |
【解説】南海トラフ地震の発生確率『60~90%程度以上』に見直し 80%程度からナゼ変わった? 専門家は「大きな地震が起きる可能性は少しずつですが高まっています」(MBSニュース) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a21ae500f5079df0f43e5f243df184a76d81f3f
9/26(金) 17:00配信 より
「今後30年以内の発生確率が「80%程度」とされてきた南海トラフ地震。政府の地震調査委員会は、その発生確率を「60%~90%程度以上」とする新たな発表」
「今回の大きな変更ポイントの1つは、室津港の隆起量データの見直しです。
新たな研究論文が発表されたことなどから、史料の記録や解釈を再検討し、隆起量データの不確実性を表す、つまり「データに幅を持たせる」ことに」・発生確率計算モデルの見直
「「時間予測モデル」ではひずみの蓄積は一定としていましたが、
・地震を起こすひずみの蓄積が一定ではなく、はらつきがある ・地震が起きた時のひずみの解放は、地震の規模によって異なる ・発生間隔は前の地震の規模に比例するがばらつきもあることを考慮した「すべり量依存BPTモデル」という新たな計算モデルを採用」「気をつけないといけないことは、今回の発表は、史料の解釈と計算方法の見直しによるもので、南海トラフの状況が変わったのではない」
取材と文:福本晋悟 MBS報道情報局 災害・気象デスク。おもに津波避難に関する課題をテーマに取材。人と防災未来センター特別研究調査員。神戸学院大学非常勤講師
◇ ◇
読みやすい記事だった。
これで 地震保険の掛け金が下がるといいのだけどなぁ・・
はっきり言って 今の料率では 地震保険に加入する意味がないといいたくなるほど 掛け金は高く保証が低すぎる
あと、南海地震に関して言えば、伝え聞く1946年の時と同程度なら、耐震設計の今の家屋の建築密度によっては、かなり被害が軽くなるのではないかと言う気がする
むしろ 地区ごとの建造物の質と割合によって 地震被害の差が大きく開くのではないかという気がするのですが・・。
隠れ断層の位置情報の全公開・周知徹底と建造物の規制を徹底し、
隠れ断層の上には 建物をたてず、
街の耐震・耐火住宅・建築物の比率を90%以上にできれば95%以上にしたり、
地盤の質にあわせて建造物の密度を定めたり 建築時の防災設計の課題を設定することにより
直下型以外の地震被害はかなり防げる(人命にかかわらない程度に抑えられる)と思います。
せっかくの建築基準と建築技術水準を維持し
より確かなものにすることによる防災効果をもっと着目すべきではないかと考える
そして クルクル東海地震も何回(南海)トラフも オオカミ少年のようなたわごとは廃止すべき。
日ごろの備えは 個人の責任と 行政の責務、の両面から実効性を高めるべきと考えます。
ゆくゆくは 水被害にあいそうな場所、地震リスクの高い場所
など 地形・地盤・気象条件といった立地条件に合わせた 建築基準・許認可基準を定めることにより 自然災害により強い日本国に成長できると考えます。
日本人の出生率が安定し、新規住宅需要が一段落している今こそ、根本的な街づくり、各種防災に特化した住宅街・商業地区の割り振りのやり直しが 可能なのではありませんか?
いつまで 2・30年に一度は浸水する場所、がけ崩れしやすい場所、津波被害が50~100年に一度発生する場所に住宅地を建て続けるのですか?
そのような 災害多発地区には 新規の住宅建設を規制すべきでは?
少なくとも 土地売買・建造物販売時には その情報を告知する義務をおわせるべきでは?
代わりに そのような土地・建造物の相続税は廃止、固定資産税も軽減する代わりに、そのような土地・家屋を貸し出す人・売買を仲介する業者の収入には100%の特別税を課してはどうですか?
さらにそのような不動産を物納する者には優遇措置をとるとか・・
つまり 物納することにより、それらを取得した時の費用相当額を 今後の賃金労働による所得税・住民税等の減免で相殺するなど。
・一極集中・分散化云々の空論を展開するよりも
各地区ごとの 災害リスクを明確化し
建造物の密度・道幅による 被災程度の深刻度を明確に公表することにより、
密集化リスクを避けたり、安全確保のための防災設備投資額と予算額を考えて、 人々は 適度な分散居住を選択すると思うのですがねぇ。
少なくとも 生粋の日本人なら それだけの判断力と教養を身に着けていると思う。
またそのような日本人を育てるために 日本の学校教育12年間+αがあるのですから。
そういう意味でも 「目先のことしか考えられない外国人」がゴキブリのように侵入繁殖することは 日本国を滅ぼす禍根にしかならない=防災の妨げ・災害救助の妨害要因・国富の流出と浪費する寄生の温床となる、と考えます。
◇
日本人と同じだけのモラルと文化的水準を持たない異邦人の流入はお断り!
日本人が 自腹を切って よき社会人たるための素養を身に着け、日本社会の生活水準をたもっているのに、
そこに寄生するだけ= 教育水準も社会的秩序も身に着けていない外国人が侵入して
補助金という名の我々の納税資金を食らって、遊行にふけったり本国送金をしながら、
日本国で各種減免措置だけを求め(つまり日本社会で暮らすための応分の自己負担を免れることばかり画策して) 日本人のような華やかな生活ができないのは差別だといいがかりだけをつける存在
日本で暮らすための日本国に対する自己負担分を拒否する輩
(本国の人間から借金して渡航してきたのは あんたの勝手
日本人にも日本国にもかかわりのないこと
そのような借金持ちが来日しては日本国を荒らすのは害虫と同じ、迷惑)
◇
話を元に戻すと 津波対策で でっかい防潮堤を作り
避難小屋を作っても
「避難小屋=津波に耐える高層建造物」の主材が、海風でさびやすい鉄骨であれば、当然維持費用=ペンキの塗り替えが必要となるわけで、
そこを 悪徳業者の手抜き工事で建設から10年たたないうちに使用できない状態にしてしまうようでは意味がない
かつての長田町や道頓堀沿いのように 防災基準無視の密集地は
火災が起きれば どうしようもないのだから
大阪駅前や天王寺の再開発のように たとえ50年近い年月をかけてでも
都会の一等地の密集地解消策を講じるべきなのです!!
(長田町で亡くなった方々のご遺族には申し訳ない記載ですみません。
あの被害拡大は 「幸いにも死者無し」とがれきと化した街中に立って連呼した女アナウンサーとそれを垂れ流した糞メディア、それをうのみにして 八尾方面隊の救助活動を妨害したり、速やかな救助活動を展開しなかった当時の内閣の責任にあります。
でも 私たち大阪府民のかなりの者は 自分たちの就労の機会を兵庫県からの被災移入組に譲るという 己の収入・生活を犠牲にして 生き残り被災者のための救済に当たり、
そのことをだれに認められることもなく その後の20年以上もの生活を送ってきたわけですから、これくらい書いても許してくださいね!
それでも 火に巻かれて亡くなった方々のことを思うと胸が痛むから、 みんな黙って 生き残った被災者のために自分たちの就労の機会を譲ったのですけど。













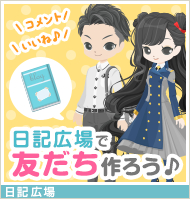













x研究費予算月聞きにくく
〇 がつきにくく
・「くるくる東海地震 何回トラフ」の功績は、海底の隆起測定などが 実現したことにあると思う
日本の海洋探査技術が 海溝のへの潜水深度を競い合う時代が終わってから研究費予算月聞きにくくなっていたかもしれないけど、「なんかトラフ」のおかげで 海底の断層調査とか 隆起調査とか 具体的な課題ができて再び始動し始めた様ですから
真面目な話し 日本列島の地震対策には、日本列島を取り巻く海底探査なしには 進みませんもの
1960年代前半の大阪湾岸臨海工業地帯の建設のときから、大阪湾沿岸の断層の存在は、その埋め立て担当企業間では知られていた。そして 関空建設の為の埋め立て(人工島建造)の時にも
でも 隠れ断層が防災のための基礎データとして活用されることなく、阪神淡路大震災がおき
その後も まだまだ 府下でオープンにされているとは言いがたい
(調査結果を記した地図の存在は 府下の公務員の一部では常識でありその記載を元に私有地の売買をやっている公務員も割と多いのに、一般市民には ちっとも情報公開されてない)
でも これからは 地震発生モデル構築・検討の基本資料として 防災モデル構築のための有効資料として
もっと積極的に活用され 情報公開がすすむことを期待してます
あと 閲覧手続きをもっと簡単に 申請方法を各市の広報に毎号記載するくらい、情報公開しろや!
・個人的には 阪神淡路大震災発生前の2・3年前から 日本海側の2方面、そして太平洋側を合わせた3方面を震源とする地震で大阪府で深度2・3の地震が続き その流れから阪神・淡路大震災が起き、東日本大震災・能登半島地震と続いたことで、歴史上周期的に繰り返されてきた日本の大地震の流れは一巡して 新鏡面に入ったのではないか?(=歴史資料に残りにくい 地震・噴火等のパターンに入ったのではないか?)と思っている
もう少し大きな目で見れば、阪神淡路大震災前の 大島噴火辺りから、大地震3つのパターンなのかもしれないが(あくまでも歴史資料を基にした仮説)
・ただ プレートテクトニクスという視点でみれば 日本列島は 複数のプレートの接点だから
今年起きているトカラ列島のように別の力学によるパターンもあるだろうし
九州以南と北海度あたりの地震・噴火関連は、京・大阪を中心とした視点では歴史資料が少なく
パターンがよめない
双方には科学的な優劣がつけられず、二つの値とも「最も確率が高い『IIIランク』」と分類される「26%以上」となる。ただ、防災上はより高い「60~90%程度以上」を引き続き意識するよう呼びかけた。
調査委委員長の平田直・東京大名誉教授は「わかりにくいとは思うが、現在の科学として最善の計算結果を示した。南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくないことを示すデータだ。いつ起きるとは残念ながら言えないが、すぐに対策をしていただきたい」と話している。(竹野内崇宏
◇ ◇
正直 口から魂が飛んでいきそうな話しだ。
昨年 お盆営業を妨害するかのように発生された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」のうそ臭さに悩んだ身ととしては、あの扇情的な注意と曖昧表現・曖昧会見のいかがわしざに顔をしかめながらも 注意深く推移を見守り、予告期間すぎたあとに出た記事を通して、あの政府デマの作成者が 例の くるくる東海地震一派であると知って がっくりきました
その流れを受けて 今回の発生確率の各論併記になったのでしょうが・・
こんなん 自治体の行政担当者も 保険の料率算定者も 困るヤン!!
もはや 政策基準とするには 破綻してるやん! といいたくなる。
まあね 発生確率計算の 恣意的データ取り扱いについては 以前から 察してましたが・・
根拠の不確かな現実問題として検証できない仮説を 補助金関連の政策と結びつける危険性も 過去半世紀近く指摘したくても 潰されてきましたけど・・
その 根本(算定基準のもととなる仮説の多様性(?)任意過ぎる基準)の一端が
こうして 公になったことそのものを 評価します。
・けっきょく 常識的な範疇、「大地震被害が置きやすい場所は 歴史的にわかってるけど それがいつくるかは 大雑把にしかわからん(よそで大地震が起きたら ここで発生する時期が遅くなるという現実)」という認識を 社会的共有して 都市設計モデル・行政的対策をかんがえにゃぁいかん!
という原点にもドルのが 一番ということでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7ca81180f4be574cc8f13384d5ea0a41a923da9a
9/26(金) 17:00配信 朝日新聞
政府の地震調査委員会は26日、南海トラフ地震の発生確率について、算出法を見直し発表した。複数の計算方法を採用し、今年1月の時点で30年以内に「80%程度」としてきた数値を、今後は「60~90%程度以上」または「20~50%」と併記する。一つの地震の発生確率を併記することは異例。
静岡県から九州沖の南海トラフ沿いのマグニチュード8~9級の地震についてで、計算手法の見直しは12年ぶり。震源域の状況が変わったわけではなく、確率の計算のみ変更した。今回の発生確率の見直しに伴い、地震の想定規模や地域などは変更していない。
このため、最大で死者が約29万8千人に上るなどとする、政府が算出した被害想定には影響しない。双方とも高い確率だとして、備えを進めるよう呼びかけている。
静岡県から九州沖の南海トラフ沿いでは、おおむね100~200年間隔で大地震や津波被害が繰り返されてきた。前回の地震からは約80年が経っている。
これまでの「80%程度」の算出には、江戸時代の2回の南海トラフ地震で高知県内の港が隆起した高さと、次の地震までの時間に関係性があるとする理論に基づいた「時間予測モデル」(計算手法)の1種類が使われてきた
高い確率値の出る計算式に「水増し」批判も
ただ、根拠となる江戸時代の記録は古文書の解釈が分かれ、潮位の考慮などデータの精度に不明な点が多い、とする研究論文が昨年発表された。このモデルを使う南海トラフのみ高い確率値が出るとして、「水増しではないか」との批判が昨年の国会で取り上げられた。
このため調査委は、モデルに隆起量や計測値の不確かさを考慮できる新たな計算手法を取り込み、80%程度から「60~90%程度以上」に更新した。誤差を反映するため、幅を持った数値になった。
さらに、他地域の地震に使う別モデル(BPTモデル)で計算した「20~50%」も、主な確率として新たに併記する。
年齢層によっては、被災者雇用のために内定を取り消された大阪人達(その後の人生のチャンスを奪われた大阪の年代層)も現実に居ましたよ!
それでも 生き残り組に いつまでも被災者面されても、いつまで言ってんの?とは言わずに 黙ってやり過ごしてますけど。
そして 長田町の悲劇を繰り返さないためにと、東日本大震災等でいち早く救援策をとった大阪の公務員・一般市民たちも多数いました
(残念ながら 東北人の自己中心性のために その思いが無にされてしまった部分がありますが。)
だからこそ 自然災害に関しては、人口密度の調整・建造物の許認可から徹底して防災・減災に努めること「地の利に沿った発展の抑制・調節」が大切だと思います
そして 際限のない「拡大・拡張・開発要求」も「救済・援助」も ただの強欲にすり替えられるだけだとも。