重陽
- カテゴリ:人生
- 2025/09/09 00:15:31
こんばんは!9日(火)は、
北日本から西日本では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。
雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。
落雷や突風、急な強い雨等に注意してください。
南西諸島は晴れたり曇ったりとなり、
所によってにわか雨や雷雨がある見込みです。
【執事にしたい有名人は?】
A、菅田将暉(すだまさき)さんです。
〇菅田将暉 さん
1993年(平成5年)2月21日生まれです。
俳優、歌手の方で大阪府箕面(みのお)市出身で、トップコートさん所属です。
@理由
・格好が良く、気配りが出来そうです。
・楽しい会話が得意そうだからです。
ヘアスタイルをオールバックにすると、
執事姿に身を包みますと、かなり似合いそうです。
ドラマ「3年A組」で演じた、
主人公の柊一颯(ひいらぎいぶき)さんのような、
少し癖のある執事さんも面白いかと存じます。
☆柊一颯 さん
魁皇(かいおう)高校の美術教師で、物静かなおとなしい性格をしています。
【重陽】 ちょうよう
★重陽の節句は中国から伝わった五節句の一つで、
無病息災や不老長寿を願う日です。
<概要>
〇重陽
9月9日「重陽の節句」は別名「菊の節句」といいまして、
菊の花を用いて不老長寿を願う行事で五節句の一つです。
@五節句の一つ『重陽の節句「別名:菊の節句」』
☆五節句
江戸時代に定められた5つの式日をいいます。
*5つの式日・・・現在でいう祝日
・1月7日:人日(じんじつ)の節句(七草粥)
・3月3日:上巳(じょうし)の節句(桃の節句/雛祭り)
・5月5日:端午(たんご) の節句
・7月7日:七夕(たなばた)の節句
・9月9日:重陽 の節句
古来、奇数は縁起の良い陽数で偶数は縁起の悪い陰数と考え、
その奇数が連なる日をお祝いしたのが五節句の始まりで、
めでたい反面、悪いことにも転じやすいと考えられ、
お祝いとともに厄祓(やくばら)いをしていました。
中でも一番大きな陽数(9)が重なる9月9日を、
陽が重なると書いて「重陽の節句」と定め、
不老長寿や繁栄を願う行事をしてきました。
今では五節句の中で影が薄くなりましたが、
五節句を締めくくる行事として、昔は最も盛んだったといわれています。
@重陽の節句(菊の節句)は中国伝来、平安時代に菊の花で不老長寿を祈願
こうした節句は、行事と関係する植物の名前を冠して呼ばれることが多いです。
・1月7日:七草の節句 ・3月3日:桃の節句
・5月5日:「菖蒲(しょうぶ)の節句 ・7月7日:笹の節供(せっく)
・9月9日:菊の節句
このように呼ばれています。
★古来、菊は薬草
古来、菊は薬草としても用いられまして、
延寿(えんじゅ)の力があるとされてきました。
菊のお陰で少年のまま700年も生きたという、
「菊慈童(きくじどう)」伝説があります。
又、菊は他の花に比べて、花期も長く、
日本の国を象徴する花としても親しまれています。
☆中国由来の行事
日本では平安時代頃に、貴族の宮中行事として取り入れられました。
当時は、中国から伝来したばかりの珍しい菊を眺めながら宴を催し、
菊を用いて、厄祓いや長寿祈願をしていました。
これが時代とともに、民間にも広がって、
江戸時代には五節句の一つとなって、親しまれるようになりました。
★様々な風習がある
菊といえば「晩秋の花」という印象がありますが、
旧暦の9月9日は新暦の10月中頃にあたりまして、
まさに菊の美しい季節でした。
この頃は農繁期であることや、
新暦に替わって、季節感が合わなくなったことから次第に廃(すた)れ、
収穫祭に吸収されたりしましたが、寿命を延ばすと信じられていた菊を使い、
様々な風習が伝えられています。
□くんち
庶民の間では「お九日(くんち」と呼ばれて親しまれまして、
秋の収穫祭と合わせて、祝うようにもなりました。
・長崎くんち :長崎県長崎市
・唐津(からつ)くんち:佐賀県唐津市
これらの地域で行われるくんちはその名残でありまして、
新暦の10月に開催されています。
@重陽の節句(菊の節句)の楽しみ方:菊酒
重陽の節句に味わいたい菊酒ですが、本来は菊を漬け込んで造りましたが、
お酒に花弁(はなびら)を浮かべてみるだけでも良いです。
長寿につながり、風流な気分を味わうことが出来ます。
@重陽の節句(菊の節句)の楽しみ方:被せ綿(きせわた)
正式には赤色、白色、黄色の真綿(絹の綿)を用いまして、
綿を一輪ずつ被(かぶ)せたり、全体に被せたりします。
そんな風情を楽しむように、
ベールのようにアレンジしまして、お部屋に飾るのも優雅です。
@重陽の節句(菊の節句)の楽しみ方:後の雛(秋の雛・菊雛)
重陽の節句には「後の雛」という風習もあります。
桃の節句(雛祭り)で飾りましたひな人形を、
半年後の重陽の節句で虫干しを兼ねて、再び飾ります。
・健康
・長寿
・厄除け
これら等を願う風習で、江戸時代に流行しました。
秋に菊とともに、ひな人形を飾りますので、
別名「秋の雛」や「菊雛」とも呼ばれています。
最近は「大人の雛祭り」として、女子会等を楽しむ方もおられるようです。
@重陽の節句(菊の節句)の楽しみ方:菊湯、菊枕、菊合わせ、
茱萸嚢(しゅゆのう)
★菊湯
湯船に菊を浮かべて入ります。
現代でいうと、ハーブバスです。
☆菊枕
菊を詰めた枕で眠りまして、菊の香りで邪気を祓います。
菊のポプリやアロマテラピーグッズを枕元に置いても良さそうです。
★菊合わせ
菊を持ち寄りまして、優劣を競います。
今でいいますと、菊のコンクールです。
この時期になりますと、菊祭りや菊人形展が各地で開催されています。
☆茱萸嚢(しゅゆのう)
呉茱萸(ごしゅゆ)の実を緋色(ひいろ)の袋に納めたもので、
身に着けたり、飾ったりして厄除けをします。
問題 重陽の節句(菊の節句)の食べ物:栗ご飯、秋茄子についてですが、
次の文章の???に入る言葉を教えてください。
重陽の節句は秋の収穫祭と結び付いていた為、
重陽の祝い膳には悪の食材が並びます。
長寿につながる菊酒とともに楽しむことも出来ます。
重陽の節句の食べ物には、不老長寿を願う気持ちが込められていますので、
敬老の日(9月の第3月曜日)に活かすことも出来ます。
■栗ご飯
江戸時代から重陽の節句に栗ご飯を食す習わしがありまして、
「栗の節句」とも呼ばれています。
□秋茄子
「お???に茄子を食べると中風にならない」といわれています。
焼き茄子や茄子の煮浸しが人気のメニューです。
1、嫁
2、くんち
3、台風
ヒント・・・〇??? 九州北部における秋祭りに対する呼称
多くの???ではひらがな表記の「お???」を、
正式名称として使用していますが、
語源の節により「(御九日」、「(御)宮日」と、
幾つかの漢字表記があります。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。





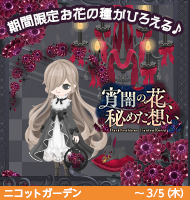

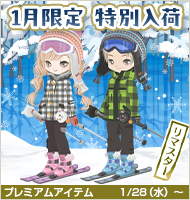


















こんにちは!晴天の水曜日をお疲れ様です。
はい、そうですね、とてもお似合いと推測しました。
おおお~、枚方パークでは「大菊人形展」なる催しがありましたか。
そうですか、復活進化しての開催ということは2005年に人気があった証ではないでしょうか?
問題の答えですが、2番のくんちが正解になります。
流石ですね!!どうもおめでとうございます(祝)
御存知「くんち」とはお祭りという意味です。
今年は各地暑いですから、お祭りで体調を崩さないとよろしいですね。
重陽の節句で菊といえば、
2005年に終了した枚方パークの「大菊人形展」を思い出します。
2023年頃から復活進化して開催されているみたいですが、見に行ってないのでよく分からないです。
答え 2