ユウガオ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/08/05 16:51:54
ニコットおみくじ(2025-08-05の運勢)

こんにちは!九州から東北の太平洋側は晴れる。
日本海側は雨で、東北の日本海側と北海道は大雨の恐れ。
沖縄は晴れ。
関東は最高気温が40℃の所も。
【ユウガオ】 夕顔 Lagenaria siceraria var.hispida
bottle gourd
calabash
☆ウリ科ユウガオ属の植物で、蔓(つる)性一年草です。
<概要>
〇ユウガオ
ユウガオは、干瓢(かんぴょう)の原料となる野菜です。
@干瓢
干瓢はウリ科の「ユウガオ」を紐状に剥いて乾燥させた食材で、
カルシウムやカリウム等の栄養素がたっぷり含まれています。
★干瓢の正体と栄養価
干瓢はウリ科の「ユウガオ」を原料とした、日本の伝統的な食材です。
この食材は独特の形状をしていて、
細長く紐状に剥かれた後、乾燥されます。
一般的には居酒屋や和食店で見かけることが多く、
その存在は和食において、重要な役割を果たしています。
□栄養面においても、干瓢は優れた食材
・カルシウム ・カリウム
・リン ・鉄分
これら等のミネラルが豊富に含まれています。
◆特に注目すべき点
食物繊維が非常に多いという点です。
これは便秘の解消や腸内環境の改善に寄与し、
健康維持に役立つとされています。
さらに、乾燥された状態で保存が可能ですので、
手軽に栄養を摂取出来ることも魅力の一つです。
◇干瓢の見た目は独特
食材としては地味な印象があるかもしれませんが、
その栄養価は思いの他、高いです。
例えばですが、干瓢100g中には、
食物繊維が約22g含まれているといわれています。
これだけの食物繊維を摂取することで、
腸の動きを活発にしまして、消化をサポートします。
又、カルシウムやカリウムは、
骨や血圧の健康にも良い影響を与える栄養素です。
◆料理
干瓢は日常の食事に取り入れるべき重要な存在です。
例えば、干瓢を使用した料理は、
煮物や巻き物等、様々な形で楽しめます。
又、味付けや調理法によって、
その風味が異なり、幅広い料理にアレンジすることが可能です。
特に干瓢巻きはお酒のおつまみとしても人気があります。
干瓢を普段の食事に取り入れることで、
健康維持だけではなく、料理のバリエーションも広がります。
☆干瓢の歴史と文化的背景
干瓢の歴史は古く、日本の食文化の中で長い間、
その地位を確立してきました。
■干瓢の起源
奈良時代から平安時代に遡(さかのぼ)るといわれています。
当時、食材の保存方法として乾燥が重要視されていて、
特にユウガオがその方法で保存されていることが、
干瓢の誕生につながったと考えられています。
乾燥させることで、長期間の保存が可能になり、
食糧不足の際にも役立つ食材になりました。
□江戸時代
江戸時代に入りますと、干瓢はさらに人々の広まりました。
この時期、農業と商業の発展により、食材の流通が活発になりまして、
干瓢も多くの家庭に取り入れられるようになりました。
◆江戸の庶民の食卓
干瓢を使用した料理が人気を博しまして、調理法も多様化していきました。
さらに、当時は「かんぴょう巻き」という寿司スタイルが流行しまして、
これにより、干瓢の存在は益々広がりました。
◇文化的な面
作事や祭りの際には干瓢が用いられることも多く、
特に「奉納料理」として神事に供されることもあります。
又、干瓢を使用した料理は、
地域ごとに異なる特徴を持ちまして、各地の食文化を反映しています。
このように、干瓢は単なる食材であるだけではなく、
日本の歴史や文化を形作る大切な要素です。
◆和食の再評価
近年では和食の再評価が進む中で、
干瓢はその健康的な要素や多様な使い方が見直されています。
特に食物繊維の重要性が再認識される中、
干瓢を使った料理が見直され、多くの人々に愛されるようになってます。
干瓢は古き良き日本の食文化を反映しつつ、
現代の食卓にも自然に溶け込んでいます。
干瓢の歴史を知ることで、
私達はこの食材の持つ、深い意味や価値を理解することが出来ます。
そして、干瓢を通じて、日本の伝統的な文化を感じ取りながら、
健康的な食生活を楽しむことが出来ます。
@瓢箪(ひょうたん)
ウリ科ユウガオ属の一年草で、同じ仲間にヒョウタンがあります。
ヒョウタンは外側の皮だけ乾燥させて、容器として用いられます。
食用にはされませんが、このユウガオは苦味も無く、食用になります。
「夕顔」と聞くと、「アサガオ」や「ヒルガオ」等と同じ仲間に聞こえますが、
全くの別種ですので、混同しないように注意が必要です。
@特徴
ユウガオには「冬瓜(とうがん)」と同じように、
ずんぐりと丸いタイプと、長い円筒状になるタイプがあります。
形は違っても、味は同じと考えても良いです。
ただ、干瓢に加工されるのは主にマルユウガオです。
☆表皮
比較的固めですが、それ程厚くはなく、中の果肉は真っ白です。
★肉質
緻密で癖はありません。
中心部に綿状の部分がありまして、ここに沢山の種が詰まっています。
ウリ科ではありますが、香りはあまり強くはないです。
@ユウガオの主な産地と旬
☆主な産地と生産量
主な産地はカンピョウの生産が盛んな栃木県で、
政府が纏(まと)めた平成24年産の生産を見ますと、
382トンで全国の98%を占めています。
又、茨城県では5トンが生産されまして、
その多くは青果として出荷されています。
その他の地域でも、各地で極僅かに栽培されています。
滋賀県の水口も古くからカンピョウが作られていまして、
現在では生産量が少ないですが、特産となっています。
★ユウガオの収穫時期と旬
ユウガオはウリ科の野菜ですので、収穫時期は夏で、7~9月です。
@ユウガオに含まれる主な有効成分とその働き
☆苦味成分、ククルビタシン
同じ仲間のヒョウタンには強烈な苦味の成分、
ククルビタシンが多く含まれている為、食用になりません。
ユウガオはこのヒョウタンから長い年月をかけて、
苦味の少ないものが選抜されてきたものといわれています。
このククルビタシンという成分は、
キュウリの蔕(へた)近くに含まれているものと同じで、
沢山食すと、食中毒を起こすこともあるとされています。
問題 ユウガオの生産についてですが、
栃木県がなぜ?全国トップなのかを次の文章の???に入る言葉を、
教えてください。
栃木県ですが、夏は???が長く、温暖な気候に恵まれています。
この為、ユウガオの栽培に最適な環境が整っています。
1、気温が高い期間
2、日照時間
3、雷雨の期間
ヒント・・・〇栃木県宇都宮市???
夏場は太平洋側気候です。
30年間の???はランキングが24位です。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。







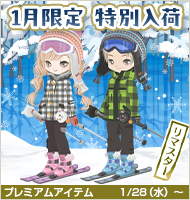





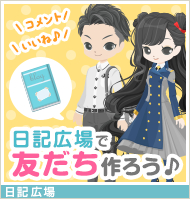












こんにちは!こちらにもコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、晴れの水曜日をお疲れ様です。
そうですか、干瓢は節分の日に巻き寿司に使用ですか。
おお~、次の日の昼ご飯の干瓢巻きが美味しいでしょうね。
ああ~、はい瓢箪を乾燥させて器にしてですね。
そうですか、壊れてしまいましたか。
そうですか、その1つがとても貴重になりますね。
問題の答えですが、2番の日照時間が正解になります。
スズラン☆さん、どうもおめでとうございます(祝)
本日も日照時間が長く、暑い日となっている所が多いようですので、
どうか水分補給等をして、体調を崩さないようにお過ごしくださいませ。
なので、買ったら使い切るように頑張ります。
次の日の昼ご飯は干瓢巻きにして食べきります。
瓢箪は子供の頃、祖母が日避けに瓢箪育ててました。
作った瓢箪は器にして、数個飾ってましたが、いつの間にか壊れて捨てて、
今は1つの゙みです。
答え 2