橋の日/吊り橋の日
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/08/04 01:17:59
こんばんは!4日(月)は九州から中国、四国や東北北部から北海道、
南西諸島は雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。
その他の地域は概ね晴れますが、
関東甲信から東北北部では午後は山沿いを中心に、
所々でにわか雨や雷雨となりそうです。
尚、台風9号は日本の遥か東を、
台風10号は日本の東をそれぞれ東寄りに進む見通しです。
〇橋の日/吊り橋の日 Bridge Day/Suspension Bridge Day
☆8月4日(はし)「橋の日」は、宮崎発祥の記念日です。
★8月4日の「吊り橋の日」は、吊り橋に囲まれた奈良県十津川村が、
地域の歴史と文化を伝える為に制定した記念日です。
<概要>
〇橋の日
@橋の日が生まれた背景
1986年、橋梁会社に勤める湯浅利彦さんの提案によって生まれた、
「橋の日」です。
宮崎県の「橋の日」実行委員会さんが制定し、
日本記念日協会さんによって認定されました。
なぜ8月4日が選ばれたのかというと、
「は(8)し(4)」と読む語呂合わせからです。
☆記念日の目的
河川と橋を通じて地域愛を育み、自然環境の大切さを再認識することです。
私達の生活に欠かせない橋に、あらためて注目を集めようという試みです。
■宮崎「橋の日」実行委員会 さん
住所:宮崎県宮崎市佐土原町下那珂2574-6
◇目的と活動
昭和60年、湯浅利彦さんが「橋の日」を提唱。
昭和61年、延岡市にて第1回「橋の日」を開催。
昭和61年、宮崎市にて有志により実行委員会を発足。
会長に大田原宜治さん(元宮崎県土木部長)他会員40名と各団体、
橋梁メーカー・行政機関の協力により、開催しています。
▲橋の日の目的
・8月4日(ハシ)を「橋の日」と定め、
私たちの郷土の心のイベントとします。
・私たちの生活と文化に、密接な関わりを持つ川や橋に感謝し、
橋や河川とのふれあいの日にします。
・郷土を愛する心と河川の愛護・浄化への関心を育みます。
・「橋の日」を通して、多くの人達との心のかけ橋をつくり、
「橋の日」を全国的運動に発展させます。
・毎年8月4日に宮崎市の橘橋北詰めにて、
様々な催し物や広報・啓発活動を行い、
「橋の日」制定運動を展開しています。
▽宮崎の象徴ともいえる「橘橋」
人々の暮らしには、絶対欠かせない橋。
大淀川に架かる「橘橋」を誕生させる為に立ち上がったのは、
1人の男性であった。
医者として活動をしていた福島邦成さんが、
故郷を愛する想いから行動に移したその背景とは。
「宮崎『橋の日』実行委員会」さんの、
事務局長・鶴羽浩さんに話を聞いた。
宮崎市は2024年に市制100周年を迎えたが、
大淀川に架かる橘橋が誕生したのは、それより前のことだった。
『橘橋の歴史』
橘橋が誕生したのは144年前。
架けたのは行政ではなく1人の男性だった。
鶴羽浩さん:
「橘橋は福島邦成という医者が架けた。
自分の私費をもって何とか町の為にしたいという思いで、
架けたというのが橘橋の始まりだ」
●福島邦成 さん
(1819年ー1898年)
橋が架かる前、人々は渡し舟で行き来していた。
しかし、船は天候に左右され生活に必要な物資が途絶えることも。
「橋を作らなければ」 → 「なかなか難しい」
建設許可が下りたのは3年後の明治13年3月。
川幅350m、費用は現在のお金で8000万円。
延べ2600にのぼったといわれています。
着工から1カ月余りの明治13年4月に完成。
長さは382m、幅4mの木の橋です。
現在の大淀川に架かる橋は6代目、
これからも宮崎の人々の暮らしを支え続けます。
〇吊り橋の日
@記念日の成り立ち
「吊り橋の日」は語呂合わせから選ばれた日付、
「は(8)し(4)」をもって制定されました。
この日は十津川村にとって特別な意味を持ち、
村の象徴である吊り橋への感謝の気持ちを表す日とされています。
谷瀬(たにぜ)の吊り橋は、その長さだけではなく、
村の景色に溶け込む美しさでも知られていて、観光地としても人気があります。
吊り橋が多いことから、村全体が「吊り橋の村」として親しまれています。
記念日は、一般社団法人・日本記念日協会さんによって、
認定・登録されており、公式な記念日として認知されています。
☆奈良県吉野郡十津川村(とつかわむら)
奈良県の最南端に位置する村で、面積は672、38㎢と、
北海道・北方領土にある留別村、紗那村、留夜別村、
蘂取村(しべとろむら)に次ぎ、日本で5番目に大きな面積を持つ村です。
しかし、北方領土は日本の施政権が及んでいない為、
施政権の及ぶ範囲では最も広い村です。
紀伊半島の内陸にある山村で、三重県や和歌山県と接しています。
十津川村は、日本で一番大きく広い村です。
電車が通っておらず、交通手段は車又はバスでの移動になります。
バスでの移動は奈良県は近鉄八木駅から、
又、和歌山県はJR新宮駅から奈良交通さんが運行されています。
村内では村営バスが運行されています。
五條からお越しの際には、
以前の五新鉄道さん(未開通五條~新宮間)の面影を見ることが出来ます。
吊り橋で有名な「谷瀬の吊り橋」は村の北部にあり、
五條市からは国道168号線を南へ約1時間、
和歌山県新宮市から、国道168号線を北へ約2時間の所に位置しています。
■空中散歩「谷瀬吊り橋」
日本有数の長さを誇る鉄線の吊り橋です。
上野地と谷瀬を結ぶこの巨大な吊り橋は、
長さが297m、高さが54mです。
聳え立つ深い山々に囲まれ、
眼下には十津川(熊野川)が流れ、まさに絶景で最高のロケーションです。
歩くたびにユラユラと揺れる吊り橋はスリル満点で、
まるで空中を散歩している気分で、十津川村NO1の観光スポットです。
問題 日本で最古の橋だった猪甘津橋(いかいつのはし)があった、
都道府県名を教えてください。
記録に残っている猪甘津橋は、
324年に現在の〇〇市付近に架けられました。
1、大阪府
2、奈良県
3、京都府
ヒント・・・〇猪甘津橋
現在は残っていないのですが、
江戸時代以降に鶴橋として名付けられた橋であり、
その橋の跡地があります。
@橋のあった場所については諸説ある
猪飼野(いかいの)(現:〇〇市生野(いくの)区、
桃谷(ももだに)付近の百済川(くだらがわ)に、
架けられていたものと推定されています。
旧平野川のこの橋に、鶴がよく飛来してきていたので、
鶴橋と命名されてきた橋が架けられていました。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る都道府県名をよろしくお願いします。







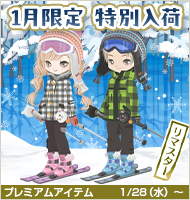


















こんにちは!お忙しいなか、こちらにもコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
おお~、そうですか、谷瀬の吊り橋に行かれたことがありましたか。
そうですか、初夏にですか。
なるほど、景観が良く、往復が楽しかったのですね。
問題の答えですが、1番の大阪府が正解です。
素晴らしいですね!!どうもおめでとうございました(祝)
確か初夏頃でした。景観も良く、往復したのが楽しかったです。
答え 1