ムロアジ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/07/29 17:05:47
ニコットおみくじ(2025-07-29の運勢)

こんにちは!九州から近畿は青空が広がる。
東海から東北も晴れるが午後は局地的に雷雨。
北海道は朝晩に所々で雨。
沖縄は雨で、夜は曇り。
広く猛暑となる。
【ムロアジ】 室鯵 鰘
Decapterus muroadsi(Temminck and Schlegel,1844)
Amberstripe scad
Mackerel scad
☆スズキ目スズキ亜目アジ科アジ亜科ムロアジ属に属する魚の総称です。
<概要>
〇ムロアジ
ムロアジはムロアジ属の魚で、
味は良いのですが、産地以外ではスーパー等、一般のお店で、
鮮魚で並ぶことはほとんど無い為、目にしたことが無い人も多いと思われます。
@クサヤ
クサヤと呼ばれる干物をはじめ、
カツオと同じように節に加工されることが多いです。
世界には匂い学才食べ物が色々とあり、
クサヤも5番目にラインナップされています。
こういった臭い食べ物は、一般的に好き嫌いが大きく分かれますが、
食しているうちにその独特な風味が好きになったりと、
新たな味覚や楽しみを提供してくれるものでもあります。
★アラバスター単位(AU)
アラバスター単位(AU)とは、B&Hラボさんという会社が販売していた、
「アラバスター」という周期測定用探知機によって計測された、
臭いの強さを表す単位です。
発酵学舎の小泉武夫さんが
食べ物臭さを比較する為、臭気の計測にアラバスターを使用し、
その計測値を「アラバスター単位(AU)」として、
著書等で紹介したことが始まりです。
*アラバスター単位は、国際的な臭いの単位ではありません
□小泉武夫(こいずみたけお) さん
1943年8月27日ー
醸造学、発酵学者で東京農業大学名誉教授(農学博士)で、
「健康や老化の防止は発酵食品に宿る」と説く、異色の博士です。
1994年から日本経済新聞社さんの夕刊に、
25年にわたり連載中のコラム「食あれば楽あり」をはじめ、
食・食文化に関する数多くの書籍を執筆し、
その数は単著で143冊を数えます。
又、数多くの国や地方自治体の委員や理事を兼任しまして、
各地での講演会も積極的に行っていまして、
2~3カ月前では日程がいっぱいで入らない程の人気講師でもあります。
講演内容は専門分野の食・農分野は勿論、
知識や経験の幅広さから「人生」や「セカンドライフ」をテーマにした、
お話も人気を博しています。
■世界の臭い食べ物ランキング
*アラバスター単位の計測値をもとにしています
順位 名称 アラバスター単位(AU) 国・地域
1位 シュールストレミング 8070 スウェーデン
2位 ホンオフェ 6230 韓国
3位 エピキュアーチーズ 1870 ニュージーランド
4位 キビヤック 1370 アラスカ、
グリーンランド
5位 くさや(焼きたて) 1267 日本
6位 鮒ずし 486 日本
7位 納豆 452 日本
8位 くさや(焼く前) 447 日本
9位 沢庵の古漬け 430 日本
10位 臭豆腐 420 中国、台湾、
香港等
☆伊豆諸島の名産「クサヤ」は魚の干物
クサヤとは伊豆諸島の名産である魚の干物で、
原料として以下のものが使用されています。
・ムロアジ ・シイラ
・トビウオ ・サンマ
血合いや内臓を取り除いて、
開きにした魚をくさや液に1~2日程漬け込みます。
それを洗い流してから天日干しにして乾燥されるのが、クサヤの作り方です。
離島である伊豆諸島に暮らす人達が、
貴重な魚を長期保存する為に試行錯誤した結果、
生まれた発酵食品がクサヤです。
★クサヤが臭い理由
干物であるクサヤが臭い理由はくさや液にあります。
クサヤは江戸時代から続いている製法とされていまして、
そもそもは塩水に魚を漬けるだけでした。
江戸時代は塩を用いて干物を作るのが一般的でしたが、
離島である伊豆諸島では貴重品だった為、塩水で代用しました。
魚を漬けた塩水を無駄にしないよう、
数十年から数百年にわたり、塩を継ぎ足しながら使用しました。
継ぎ足した塩水には魚の成分が溶け出している為、
微生物が発生してしまいます。
その結果、魚を漬けていた塩水が発酵しまして、
現在の臭いくさや液となりました。
@ムロアジの別名
・アカゼ ・アジサバ
・マムロ ・モロ
・ミズムロ ・キンムロ
このように呼ばれています。
@学名の種小名
学名の種小名muroadsiは和名のムロアジに因んでいます。
@生態
☆分布
北海道太平洋沿岸、津軽海峡~九州南岸の太平洋沿岸、八丈島、
秋田県~九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、
稀に瀬戸内海、屋久島、さらに済州島、オーストラリア西岸、
ハワイ諸島北部、東太平洋、セントヘレナに分布しています。
★食性
主に動物性プランクトンやアミエビ等を捕食しながら暖流に乗って回遊し、
夏季には北海道付近の北日本まで北上します。
☆産卵期
5~6月にかけてで、外洋に面した沿岸部や島嶼周辺に近づき産卵します。
@特徴
標準体長が約40cmで、大きいものだと約50cmです。
ムロアジ属胸痛の特徴として、体形がマアジに比べてスリムな紡錘形で、
側扁はあまり強くなく、脂瞼(しけん)が発達しまして、
尾柄部に小離鰭(しょうりき)が付いています。
ムロアジの稜鱗(ぜいご)は側線直走部の後4分の3を占めていまして、
体側に黄色い縦縞が1本あり、尾鰭の上葉が黄色く、
下葉は赤みを帯びた淡灰色であることで、他のムロアジ属と区別出来ます。
問題 むろあじ類の漁獲量についてですが、
漁獲量が2位の都道府県を教えてください。
順位 都道府県 漁獲量(t) 割合(%)
全国 27105 100
1位 宮崎 8459 31
2位 ここ 4565 17
3位 和歌山 3239 12
4位 長崎 2209 8
5位 大分 1632 6
*平成28年漁業・養殖業生産統計より抜粋
1、東京
2、鹿児島
3、高知
ヒント・・・〇正解のムロアジの主要産地
@肝属郡肝付町(きもつきぐんきもつきちょう)
大隅半島東部にある町で内之浦宇宙空間観測所があります。
お分かりの方は数字もしくは、
ムロアジの漁獲量が2位の都道府県をよろしくお願いします。













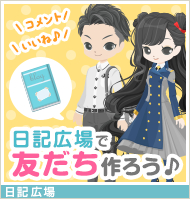













こんにちは!こちらにもコメントとお答えをどうもありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですか、ムロアジという名前を御存知でしたか。
そうですね、獲れる産地であれば、全国各地ですから忘れやすいですね。
そうですか、クサヤは伊豆諸島や小笠原諸島が主ですね。
東京駅近くの「ふくべ」さんという老舗居酒屋さんで提供されていますよ。
そうですね、シュールストレミングは私も食したことがありません。
TVで視聴した限りですが、知らないで食すととんでもないことになる方も。
現地の方はパンの上に乗せたりして、美味しそうに食していました。
はい、下の3種類も私は食したことがありません。
そうですね、日本産のものが上位にランキングされていますよね。
それだけ、発酵食品が盛んな国の証拠ですね。
はい、問題の答えは2番の高知県です。
ここは島々では無くて、鹿児島県の大きな半島のうちの東側の方ですね。
大隅半島には知覧という地域があり、お茶でも有名な土地です
夏場は発酵食品や漬物、そして殺菌効果のあるお茶等をすすんで摂取してまいりませんか?
以前どこかで食べたと思いましたが、
どこだったのか思い出せませんでした。
クサヤは臭いで有名ですが、未だに見たことも嗅いだこともないです。
シュールストレミングも名前だけ知っていましたが、
数値が凄いですね! その下の3種類は名さえ知りません。
クサヤ以降9位まで日本産ばかりに笑いました。
答え 2