京都祇園祭
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/07/17 01:21:38
こんばんは!17日(木)は、
全国的に曇りや雨となり、雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。
東日本から西日本では、土砂災害や低い土地の浸水、
河川の氾濫に警戒してください。
又、落雷や竜巻等の激しい突風、降雹に注意してください。
【おすすめのお土産】
A、福島県の薄皮饅頭(うすかわまんじゅう)です。
〇福島県の薄皮饅頭
福島県を代表する銘菓の一つに、柏屋さんの薄皮饅頭が挙げられます。
すっきりとした甘さの餡子(あんこ)をたっぷりと包む薄皮には、
創業当時からの変わらない思いと、磨き上げた技術が込められています。
@福島県の柏屋さんの薄皮饅頭
「福島県の定番お土産」と聞かれましたら、
高確率で名前が挙がるのが柏屋さんの薄皮饅頭です。
ぽってりとした茶饅頭の中に、ぎっしりと詰まった上品の餡子です。
そして、皮は薄く滑らかで、餡子を柔らかく閉じ込めています。
柏屋さんの薄皮饅頭は、日本三大饅頭の一つに数えられています。
その美味しさや全国に広まり、オンラインショップの他、
東京都や栃木県、宮城県にも販売店舗を構えています。
☆日本三大饅頭
・塩瀬総本家 志ほせ饅頭 さん :東京都
・大手饅頭伊部屋 大手まんぢゅう さん:岡山県
■塩瀬総本家 志ほせ饅頭(東京都)
現代の饅頭の始祖といわれている「林浄因(りんじょういん)」さんが、
1349年(室町時代)に奈良で創業したのが始まりといわれています。
小倉あんを入れた饅頭はここが始まりです。
つまり、日本の饅頭は塩瀬総本家さんから始まったという説が有力です。
◇会社概要
社名 :株式会社 塩瀬総本家 さん
所在地 :東京都中央区明石町7-14
電話番号:03-3521-8811
▲オンラインショップ
【テレビ紹介】志ほせ饅頭 12個入 1944円(税込)
日本三大饅頭にも選ばれた和菓子の原点、塩瀬さんのお饅頭です。
甘い餡子の分化はここから始まりました。
毎朝職人が大和芋の皮を一つ一つ手作業で皮を剥き下ろし、
その日の温度と湿度で調整しながら米粉と合わせて、
こね上げて生地を作っています。
大和芋のしっとりとした風味に、
厳選された北海道のエリモショウズと、
ザラメ糖から作られる塩瀬の餡が合わさり、上品な味が楽しめます。
「材料落とすな割守れ」と厳格な教えとともに伝わってきた、
その味を是非お召し上がりください。
□大手饅頭伊部屋 大手まんぢゅう(岡山県)
伊部屋さんは天保8年(1837年)に、
岡山城大手門近くのお菓子屋で作られたのが始まりといわれています。
備前藩主の池田氏一族にとても気に入られ、茶席にも出されていました。
麹(こうじ)から作り始めるということで、
ほんのりと甘酒風味が感じられるのが特徴です。
薄皮饅頭を超える、非常に薄い皮もインパクトがあります。
因みに「伊部屋」さんはいんべやさんと読みます。
■日本三大饅頭の由来
日本三大饅頭は1993年に発行された「日本三大ブック」という本に、
そのように書かれていたところがスタートです。
「日本三大ブック」は講談社さんから発行されています。
柏屋さんは福島県郡山市に本店をおいて営業しています。
その歴史は古く、薄皮饅頭を考案したのは1852年のことです。
当時の東北では珍しかった薄皮で、こしあんがたっぷり入った饅頭は、
奥州街道を行き交う旅人の間で話題となりまして、その名を広めていきました。
現代の社長は5代目ですが、
初代から受け継がれる美味しさへの拘(こだわ)りは健在です。
厳選された小豆と、
創業当時からの技術を受け継ぐ薄皮職人の技で、美味しさを常に守っています。
又、柏屋さんでは信用される企業を目指して、
地域で様々な取り組みを行っています。
その一つが昭和49年から続く、朝茶会です。
月に一度、手作りの薄皮饅頭と季節のお菓子を食しながら、
お喋りを楽しむ会を開催しています。
参加費は無料で、元気な挨拶が参加資格です。
朝茶会では子供からお年寄りまでが集いまして、
美味しいお菓子が生む、笑顔の繋がりを大切にしています。
☆株式会社柏屋 さん
本社 :福島県郡山市富久山町久保田字宮田127番地の5
電話番号:024-956-5551
■オンラインショップ
◇柏屋薄皮饅頭 こしあん5個入(スマートパック)
×のし不可 常温便 おいしさ長持ち! 価格:858円(税込)
*その他の商品もあります
【京都祇園祭】 きょうとぎおんまつり
★祇園祭は、京都市東山区の八坂神社さんの祭礼です。
<概要>
〇京都祇園祭
古くは平安時代に疫病や災厄の除去を祈った、
祇園御霊会を始まりとする、八坂神社さんの祭礼です。
1カ月にわたり、様々な神事や行事が行われます。
期間 :7月1日(火)~7月31日(木)
場所 :八坂神社 さん
住所:京都府京都市東山区祇園町北側625番地
電話番号:075-561-6155(八坂神社)さん
@祇園祭
7月1日の「吉符入(きっぷいり)で始まる祇園祭は、
7月17日山鉾巡行(前祭)、神幸祭(しんこうさい)、
7月24日の山鉾巡行(後祭)、花傘巡行、還幸祭(かんこうさい)を中心に、
7月31日「疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしさい)」で幕を閉じます。
☆7月17日(木)9:00 山鉾巡行(前祭)
山鉾は本来、疫病等の災厄を齎(もたら)す疫神を鎮める為、
依り代(よりしろ)として鉾や山を作り、町中を回ったと考えられます。
鉦(かね)や笛、太鼓で囃(はや)すのは、
荒ぶる疫神(怨霊)を鎮める為でした。
神輿の渡御(とぎょ)(17日夜神幸祭)に先立って、
都大路の清祓(きよはらい)をしたとも考えられています。
★7月17日(木)16:00 神幸祭
八坂神社さんの三基の神輿が、
氏子区域内をそれぞれ所定のコースに従い、渡御します。
午後8時頃から9時頃までに四条御旅所(おたびしょ)に到着します。
以降24日まで御旅所に留まります。
又、神輿に伴い、宮本組さんの神宝奉持列、
豊園泉正寺榊さんの行列がそれぞれコースを巡行します。
問題 7月17日(木)の18:00からは、神輿渡御ご出発式が始まりますが、
次の文章の〇〇に入る言葉を教えてください。
神輿渡御出発にあたり、
石段下にて三基の神輿の差上げが行われます。
その後、氏子区域を夫々(それぞれ)所定のコースに従い、〇〇します。
又、古例により久世稚児(くぜちご)の供奉(ぐぶ)、
宮本組さんの神宝列の供奉があります。
午後9時頃より相次いで四条御旅所に着輿しまして、
後24日まで奉安(ほうあん)されます。
1、渡御
2、行脚
3、巡回
ヒント・・・〇神輿〇〇
神輿は神様の乗り物とされまして、
祭りの日には氏子達によって街を巡ります。
神輿の歴史は869年に京都で行われた、
「祇園御霊会」が現在の祇園祭の起源です。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。


















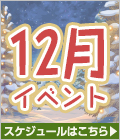







そうですか、薄皮饅頭を食した経験をおもちでしたか。
そうですね、薄皮饅頭は勿論お店によってですが、さっぱりした味が多くありませんか?
そうですね、昨日少しだけ祇園祭を視ました。
雨が降っていましたね、京都市は。
ああ~、真夏の京都は現地の方も危ない暑さという方もおられる程ですものね。
なるほど~、それは残念ですね。
外国人はさておき、街の美観を損なったというのは、
壊されたやその為によるものなのでしょうか?
法律違反で損傷系の場合は問題ですね。
問題の答えは、渡御になります。
流石ですね!どうもおめでとうございます(祝)
外国人もしっかりとマナーを守って、楽しんでいる方も多々おられるでしょう。
そして、外国人も同じで京都市の真夏は非常に危険な気温の日が多いですので、
しっかりと水分を補給して、ご無理をせずに過ごしていただきたいと願っています。
薄皮饅頭は百貨店の特産品特集で食べたことがあります。
美味しかったです。
今年の祇園祭もテレビで見ることになります。
夏の京都は暑すぎて、行く気もおきません。
近年観光は外国人観光客で溢れて、街の美観も損なったと、
地元の人が嘆いてました。
答え 1