ぼん送り火
- カテゴリ:人生
- 2025/07/16 01:13:43
こんばんは!16日(水)は、
西日本から東日本日本海側や南西諸島では概ね晴れますが、
にわか雨や雷雨の所もあるでしょう。
西日本から東日本太平洋側や北日本では曇りや雨となり、
雷を伴った激しい雨の所もある見込みです。
西日本から北日本では土砂災害等に注意・警戒してください。
【ぼん送り火】 Okuribi is a ceremonial fire lit on the last day
☆送り火とはお盆の期間に一緒に過ごした先祖や故人の霊が、
あの世へ無事に帰れるようにと願いを込めて焚く火のことです。
<概要>
〇ぼん送り火
@迎え火と送り火の意味
お盆にご先祖様の霊を・・・
・お迎えするのが「迎え火(むかえび)」
・お送りするのが「送り火(おくりび)」
このようにいいます。
お盆にはご先祖様の霊が帰って来るとわれていまして、
迎え火はその時の目印になります。
送り火はご先祖様の霊が、
あの世へ戻って行くのを見送る為のものといわれています。
@お盆
お盆とは仏教用語の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という言葉を略したものです。
★盂蘭盆会
日本の夏に欠かせない伝統行事であるお盆を指します。
◇正式名称
「盂蘭盆会」といいまして、
先祖の霊を供養する為の大切な仏教行事です。
■盂蘭盆会の基本的な意味と由来
盂蘭盆会は仏教の伝統的な行事で、先祖供養を目的として行われます。
その起源はサンスクリット語の「ウランバナ」に由来しまして、
「逆さ吊り」や「苦しみ」を意味します。
この言葉はお釈迦様のお弟子様である木犍連(もくけんれん)様が、
亡き母の苦しみを救うための行いに基づいています。
木犍連様は亡き母が地獄で苦しむ姿を見まして、
お釈迦様の教えに従って、供養を行いました。
その結果、母の魂が救われたことから、この行事が始まったとされています。
□盂蘭盆会と「お盆」の関係
盂蘭盆会と「お盆」という名称は、
同じ行事を指している場合が殆(ほとん)どす。
ただし、「お盆」という言葉は日本独自の呼び方で、
仏教における盂蘭盆会の行事が、
日本の祖霊信仰や風習と結び付いて発展したものです。
お盆の期間は地域によって異なりますが、
一般的に7月又は8月の13日から16日に行われます。
◆盂蘭盆会とお盆の違い
仏教色が強い盂蘭盆会に対しまして、
地域の風習が組み合わさった行事を総称して、お盆と呼ぶ傾向があります。
□盂蘭盆会における重要な仏教的教え
盂蘭盆会は仏教の教えに深く基づいています。
◆もっとも重要な教えの一つ
「供養の精神」です。
これは故人や先祖に対して感謝や祈りを捧げることを通じて、
現世での徳を積むという考え方に根差しています。
又、木犍連様のエピソードから、
自分だけではなく、他者の為に尽くす重要性が説かれています。
このことは現在の「お供え」や「お布施」といった、
行為にも反映されています。
さらに盂蘭盆会を通して、家族や先祖に思いを馳せ、
日頃の生活での感謝や絆の再確認をすることが教えの一環になっています。
□盂蘭盆会の起源:サンスクリット語と盂蘭盆経
盂蘭盆会の起源は古代インドの仏教経典である、
「盂蘭盆経」に基づいています。
この経典の名はサンスクリット語の「ウランバナ(側懸)に由来していまして、
「逆さ吊りのような苦しみ」を意味しています。
この「側懸」という言葉が表すように、
人々が供養を通じて亡くなった方の苦しみを救おうとする行為が、
盂蘭盆会の基本的な精神となっています。
盂蘭盆経には釈迦のお弟子様である木犍連様が、
地獄で苦しむ亡き母を救おうとしまして、
その方法をお釈迦様に尋ねた話が記されています。
お釈迦様は木犍連様に、
多くの僧侶を供養する「僧伽作法(そうがさほう)」を行うよう助言しました。
この教えが「盂蘭盆会」の起源とされています。
この背景には、
先祖供養への感謝と亡き人への魂への祈りが深く根付いています。
■古代中国から日本へ伝来
盂蘭盆会は中国を経由して日本へ伝わりました。
仏教が中国に広まる中で、盂蘭盆会も独自の進化を遂げまして、
中国の祖霊信仰や道教の文化と結び付きまして、
祖先を敬う祭りとして定着しました。
中国では中元節(ちゅうげんせつ)と呼ばれる行事と融合しまして、
先祖や亡き人に対する供養の行事として一般化していきました。
やがて日本に仏教が伝来した6世紀頃、
この盂蘭盆会の分かも一緒に日本に入ってきました。
当初は寺院中心の行事として行われていましたが、
時を経るにつれて民間にも浸透しまして、
特に祖先供養の行事として重要性を増していきます。
古代中国の要素を取り入れつつも、日本独自の伝統や信仰と結び付きまして、
現在の「お盆」の原型が形成されていきました。
□日本での発展:飛鳥時代から現代まで
盂蘭盆会が日本で公式に行われるようになったのは、
飛鳥時代の推古(すいこ)天皇の治世とされています。
当時、仏教の隆盛とともに盂蘭盆会も宮廷行事として取り入れられまして、
上流階級の間で大切な行事と位置付けられました。
その後、平安時代には家族や地域単位での開催が増えまして、
祖先供養と家族の絆を大切にする行事として広がっていきました。
鎌倉時代から江戸時代にかけて、仏教がさらに一般庶民の生活に浸透しますと、
盂蘭盆会は多様な形式を持つようになります。
迎え火や送り火、精霊棚、お供え、お経を唱える行為等、
各地で独自の工夫が生まれました。
又、地域によっては精霊流しや灯篭流しといった、
独自のお盆行事も発展しました。
明治時代に新暦が採用された後、東京等一部の地域では7月に、
地方では8月に行われるようになる等、現在の形に至っています。
現代では家族が集い、先祖を敬いながら故人への感謝を伝える機会として、
盂蘭盆会が営まれています。
又、その意味や風習が継承されつつ、新しい在り方が模索されています。
★お盆の意味と日にち
日本古来の祖霊信仰(それいしんこう・ご先祖様を祀り感謝する信仰)と、
仏教が融合した行事です。
7月15日又は8月15日を中心とした期間に行われることが多く、
7月13日~7月16日の所と、8月13日~8月16日の所があります。
問題 送り火は16日の夕方に行うのが一般的です。
迎え火と送り火に必要な道具は「オガラ」と「焙烙(ほうろく)」ですが、
次の文章の〇に入る植物名を教えてください。
〇オガラ
迎え火と送り火の際に燃やす木のことで、
木皮を剝ぎ取った〇の茎です。
〇焙烙
オガラを燃やす為の素焼きのお皿のことです。
1、藁(わら)
2、麻(あさ)
3、樫(かし)
ヒント・・・〇オガラ
「漢字」では「芋柄」と表記されます。
オガラは〇柄とも呼ばれまして、
岐阜県の庄川(しょうがわ)流域の、
白川郷(しらかわごう)の屋根にも使用されています。
*白川郷・・・合掌造りの集落がある世界遺産
お分かりの方は数字もしくは〇に入る植物名をよろしくお願いします。













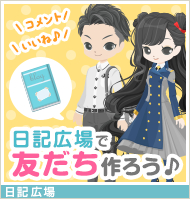













そうですね、お盆は8月中旬の所が多いですね。
そうですか、暑い中での遺品整理や諸々の片付けは大変ですね。
どうかお怪我をしないように、ゆっくりといかがでしょうか?
問題の答えは、2番の麻(あさ)が正解になります。
麻は今すぐどこにでもあるものではなくなりましたので、
輸入しないといけないようですね。
しかし、輸入先も温暖化の影響を受けて減少しているでしょうから、
こうした問題は互いに何とか考えなければならないですよね?
こちらのお盆は8月なので、
それまでに実家の遺品整理、諸々の片付けが、
済むようにしたいです。
答え 2