コールラビ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/07/02 17:06:23
ニコットおみくじ(2025-07-02の運勢)

こんにちは!暑さが続く。
九州から近畿は概ね晴れ、午後は所々で雨や雷雨。
東海から北海道は雨が降りやすく、激しく降る所も。
沖縄は晴れ。
【コールラビ】 毬茎甘藍 Brassica oleracea var.gongylodes
kohlrabi
chou-rve
chou-navet
☆コールラビは、アブラナ科の越年草です。
<概要>
〇コールラビ
コールラビはアブラナ科のヤセイカンランの変種とされている野菜で、
根元の肥大した茎の部分を食用とします。
@ヤセイカンラン 野生甘藍 Brassica oleracea L.
wild cabbage
★アブラナ科アブラナ属の野菜です。
<概要>
☆分布と生態
ヤセイカンランは主に西ヨーロッパ沿岸部に分布し、
具体的には地中海沿岸からイギリスにかけての地域で見られます。
特に海岸付近の石灰岩質の崖地や斜面といった、
比較的痩(や)せた土地を好んで、自生する性質があります。
ヤセイカンランは二年生植物で、
最初の成長期には、地面に広がる大きな葉を付けまして、
太陽光を受けて光合成を行い、根や茎に水分と栄養分を蓄えます。
冬の間は葉が地面に張り付いたロゼットという状態で、
寒さに耐えて、越冬します。
そして、二年目の春になると、
前年に蓄えた豊富な栄養分を用いて、急速に茎を伸ばします。
この茎は高さが1~2mにも達しまして、
先端には多数の黄色い花を咲かせる花穂(かほ)を形成します。
そして、花後に種子を作りまして、一生を終えます。
■ロゼット型植物の特徴
◇ロゼット葉
ロゼット型植物は、葉が地面にピッタリと這うように広がりまして、
中心から放射状に配置される形状をしています。
この形状は薔薇(ばら)の花弁に似ていることから、
「ロゼット」と呼ばれています。
★特徴と多様性
ヤセイカンランの最も顕著な特徴の一つは、その形態の多様性の高さです
これは自分自身の花粉では受精しにくい自家不和合性という性質や、
遺伝子の多様性が高いヘテロ接合性を持つことに起因しています。
その結果、同じ場所で生育している個体であっても、
葉の形や大きさ、茎の伸び方、全体の姿(草型)等が、
大きく異なることがよくあります。
この遺伝子的な柔軟性と変異性の高さを生み出すことが出来た、
最大の要因と考えられています。
又、自生地である石灰岩海岸の土壌は栄養分が少ないことが多いですが、
より肥沃な土壌で栽培しますと、大きく成長することも知られています。
これはこの植物が本来持っている、潜在的な生育能力の高さを示しています。
ヤセイカンランの近縁種としてはイタリアに自生する下記のものです。
・Brassica robertiana J.Gay
・B.cretica Lam
これらの近縁種がヤセイカンランを原種とする野菜の品種改良の過程で、
遺伝資源として導入された可能性も推測されています。
□ヘテロ接合性
遺伝学において、
二倍体生物のある遺伝子座が異なる対立遺伝子からなる状態を指します。
具体的には、各遺伝子座に存在する、
2つの遺伝子が異なる対立遺伝子で構成されていることを意味します。
例えば遺伝子座がAaのように評される場合、Aとaは異なる対立遺伝子です。
◆ヘテロ接合体
特定の形質を決定する対立遺伝子の組に、
優性対立遺伝子と劣勢対立遺伝子の両方が存在することを示します。
☆人類との関りと変種
ヤセイカンランは古くから人類に利用されてきました。
少なくとも古代イベリア人によって、
薬草として用いられていたと考えられていまして、
その知識は後にケルト人の間にも伝わったとされています。
しかし、この植物の真価は食用作物の改良によって発揮されました。
ヤセイカンランが持つ多様な変異の中から人類は・・・
・葉が巻いて球になるもの
・花や蕾が大きくなるもの
・茎や根が肥大するもの
これら特定の形質を持つ個体を選抜しまして、栽培と育種を繰り返しました。
この長いプロセスを経て、ヤセイカンランは以下のような、
ヤセイカンランは、現在の私達の食生活に欠かせない、
多くの野菜の原種となりました。
■原種がヤセイカンラン Brassica oleraceaの野菜
・ケール ・キャベツ
・ブロッコリー ・カリフラワー
・ハボタン
このようにヤセイカンランは、
単一の種からこれ程までに多様な姿と用途を持つ、
野菜が生み出された、驚異的な例です。
まさに「野菜の母」とも呼べる存在でありまして、
その生物学的な特性が今日の豊かな食文化を支える基盤となっています。
@名前の由来
ドイツ語由来の名前であるKohlrabiは、
「Kohl(キャベツ)」+「Rabi(カブ)」を組み合わせたものです。
フランス語ではシューラブ「chou rave」、
これも2つの野菜の名前の組み合わせです。
☆日本名
「カブカンラン(蕪甘藍)」又は「カブタマナ(蕪玉菜)」とされていますが、
それ以外にも「球茎キャベツ」等ともいわれています。
★中国や台湾
球形甘藍の他「大頭菜」や「結頭菜」等とも呼ばれています。
@緑色のものと赤紫色のもの
コールラビには幾つか品種がありまして、
大きめのものや小さいものがあります。
又、一般的な緑色のもの以外にも、赤紫色のものもあります。
ただ、この赤紫色のものも色が付いているのは表皮だけで、
中は緑色のものと同じ白色をしていますので、
皮を剥いてしまえば分からなくなります。
@収穫時期は初夏と晩秋
日本では春に種を蒔いて6~7月にかけて収穫するパターンと、
夏の終わりの8~9月に種を蒔いて、
10月中下旬から12月初旬に収穫することが出来ます。
食べ頃の旬は6~7月の初夏と、11~12月初旬の晩秋です。
@栄養価
コールラビは取り立てて多く含まれている栄養成分は見当たりませんが、
全体的にキャベツの持つ栄養成分のバランスと似ています。
・ビタミンC
・茹でても流失しにくい
問題 クールラビを栽培している、
文章の中の〇〇に入る県名をよろしくお願いします。
クールラビは、国内では〇〇県、茨城県、愛知県等で栽培されています。
特に〇〇県〇〇市清武町では盛んに栽培されています。
1、宮崎
2、高知
3、大分
ヒント・・・〇〇〇県〇〇市清武地域
〇〇県の中南部に位置していまして、
黒潮が流れる太平洋まで約4kmです。
〇〇ブーゲンビリア空港まで自動車で約10分、
〇〇港まで約30分、〇〇自動車道と東九州自動車道と清武JCT。
そして、東九州自動車道の清武ICや清武南ICが近くにあります。
@清武町の特産品
・パパイヤ ・日向夏
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る県名をよろしくお願いします。













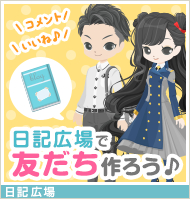













はい、おみくじは「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
そうですね、塊茎ですね。
お忙しいところ、いつも調べてくださりましてありがとうございます。
はい、そうですね、ヤセイカンランは歴史がある植物ですね。
問題の答えですが1番の宮崎ですね。
かつての宮崎県知事であった東国原英夫さんが脳裏に浮かびましたでしょうか?
宮崎県はマンゴー等でも有名な県で、ピーマンの生産量も多いですね。
スズラン☆さん、勿論、大正解です。
どうもおめでとうございました(祝)
コールラビは、画像を見て変わってると思いましたが、
タマネギかと思うカタチは茎だったんですね!
ヤセイカンランからキャベツ等に変化したんですね( ..)φメモメモ
答え 1