ユウゲショウ
- カテゴリ:友だち募集:30代以上
- 2025/05/11 16:29:17
ニコットおみくじ(2025-05-11の運勢)

こんにちは!低気圧や寒気の影響で全国的に雲が多い。
九州から関東は昼過ぎから雨の範囲が広がる。
東北と北海道は朝夕に雨が降る。
沖縄は雨。
【ユウゲショウ】 夕化粧 Oenothera rosea
Rose evening primrose
☆アカバナ科マツヨイグサ属の多年草です。
<概要>
〇ユウゲショウ
ユウゲショウは、アカバナ科マツヨイグサ属に分類される帰化植物です。
明治時代に園芸種として日本に持ち込まれたものが野生化し、
現在では道端や河原でよく見かける花になりました。
控えめで可愛らしい花のイメージとは裏腹に、
花期が長く、逞(たくま)しい生命力を持っています。
@基本情報
★別名
アカバナユウゲショウです。
□和名の由来
午後遅くに開花し、艶っぽい花色を持つことからとされていますが、
実際には昼間でも開花した花を見ることが出来ます。
オシロイバナの通称と紛(まぎ)らわしいですので、
アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)と呼ぶこともあります。
◆オシロイバナ Mirabilis japlapa
Four o’clock
この名前はラテン語で「素晴らしいを意味する「Mirabilis」と、
メキシコの町名「Jalapa」に由来しています。
オシロイバナには別名として、
「Marvel of Peru(マーベル オブ ペルー)もある為、
幾つかの名前が考えられます。
<概要>
オシロイバナは、オシロイバナの多年草です。
△原産
南アメリカ原産で、
日本には江戸時代初め頃に渡来し、観賞用に栽培されました。
気候上、一年草として扱われていましたが、
温暖化により、宿根草として広く野生しています。
リンネさんの「植物の種」(1753年)で記載された植物の一つです。
《カール・フォン・リンネ》さん
Carl von Linne
1707年5月23日ー1778年1月10日
スウェーデンの博物学者、生物学者で植物学者です。
カール・フォン・リネーさん、
ラテン語名のカロルス・リンナエウス(Carolus Linnnaeus)さん、
同名の息子特別する為に大リンネとも呼ばれています。
又、「分類学の父」とも称されています。
▲特徴
発芽率が高く強壮で、踏まれたり折れたりしても、
維管束(いかんそく)が断絶しなければ成長をし続けます。
茎はよく枝分かれして灌木状となりますが、
節がはっきりしていまして、木質化はしません。
多年草になっても瑞々しい緑色をしています。
花は五裂しますが、花弁ではなく萼(がく)で、
雌蕊と5本の雄蕊がありまして、
基部は緑色で膨らみ、萼のように見える総苞(そうほう)があります。
そして、芳香があります。
色はベタレインの発現差による赤色(ベタシアニン)、
黄色(ベタキサンチン)、白色(発現無し)の三色が基本で、
さらに不完全優性によるピンク色(赤色と白色の混合)、
トランスポゾン発現とその時期による源平咲き、咲き分け、
絞り模様が見られまして、白色と黄色の絞りは少ないです。
*源平咲き・・・一つの株に二つの色の花が咲く
*咲き分け・・・一つの花が二つの色に区分される
*絞り模様・・・節、斑、斑点状に二つの色が分散する
▽ベタレイン又はベタライン Betalain
ナデシコ目の植物に存在する赤色及び黄色のインドール誘導色素です。
これらの植物では、アントシアニンの代わりに存在しています。
ベタレインは幾つかの高等菌類でも見られます。
花弁で目立ちますが、果実、葉、茎、根の色も担っています。
そして、テーブルビートに含まれる色素もこの仲間です。
▼トランスポゾン transposon
細胞内においてゲノム上の位置を転移することの出来る塩基配列です。
動く遺伝子、転移因子(toransposable element)とも、
呼ばれています。
DNA断片が直接転移するDNA型と転写する逆転写の過程を経る、
RNA型があります。
トランスポゾンという語は、狭義には前者のみを指しまして
後者はレトロトランスポゾン(retrotransposon)、
又はレトロポゾンと呼ばれています。
レトロポゾンは、
レトロウイルスの起源である可能性も示唆されています。
レトロポゾンのコードする逆転写酵素は、
テロメアを複製する、テロメラーゼと進化的に近いです。
転移はゲノムのDNA配列を変化させることで、
突然変異の原因となり、多様性を増幅することで、
生物の進化を促進してきたと考えられています。
トランスポゾンは遺伝子導入のベクターや変異原として有用であり、
遺伝学や分子生物学において、様々な生物で応用されています。
咲くのは夕方4時頃で、和名としてはユウゲショウとも呼ばれますが、
この名はアカバナ科のものにも使用されていますので注意を要します。
☆原産
原産地は南米から北米南部です。
現在は帰化植物として、世界の温暖な地域に広く分布しています。
日本では明治時代に観賞用として移入されたものが、
関東地方以西に野生化していまして、道端や空き地でもよく見かけます。
帰化した範囲は広いですが、個体数は少ないといわれています。
★分布
関東地方以西です。
@花の特徴
花の色はピンク色で1~1、5cmと小ぶりです。
丸い花弁が4枚ありまして、赤い筋が入っているのが特徴です。
花の中心は黄緑色で雄蕊は8本、
雄蕊は先が4本に分かれた十字形になっています。
そして、小さなカップ咲きの花姿が可愛らしく目をひきます。
@茎と葉の特徴
根元から束のように生える茎は高さ20~60cmになりまして、
表面には短く、白い毛が生えています。
葉は互い違いに生える互生(ごせい)で、
長さは3~5cmあり、縁がギザギザと浅く、波打つ楕円形です。
問題 根についてですが、次の文章の〇に入る文字を教えてください。
根はひげ根を指し、主根を持たない〇い根が多数付いています。
1、細
2、太
3、丸
ヒント・・・〇主根系根茎(しゅこんけいこんけい)
主根と呼ばれる太い根と、
そこから出る側根(そっこん)という〇い根からなります。
@主根と側根
「双子葉(そうしよう)類が持つ根」のことです。
☆双子葉類
子葉(初めに出てくる葉)が2枚の植物のことです。
@根毛
根の表面が広いと、水分をよく吸収出来ます。
お分かりの方は数字もしくは〇に入る言葉をよろしくお願いします。







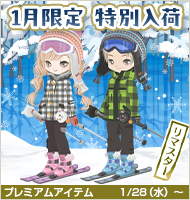


















スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
はい、おみくじは「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
そうでしたか、御実家帰りに見かけましたか。
そうですよね、早く帰宅しないといけないや、用事もありますよね。
その場所は素敵な所なのでしょうね。
オシロイバナかユウゲショウに似た花を、
実家帰りに見ました。
小花は色々種類があるからはっきり断言出来ません(〃▽〃)ゞ
夕食時の多忙な時間に、コメントとお答えをありがとうございます。
そうですか、調べてくださりましたか。
今回もどうもありがとうございます。
問題のお答えですが、1番の細が正解になります。
流石ですね!素晴らしいです!!
どうもありがとうございます。
気圧の変動が夜、可能性がありますので、
どうかご無理をせずに、お過ごしくださいませ。
今回も調べました。
1、細
ですね。