食糧管理法公布記念日
- カテゴリ:勉強
- 2025/02/21 01:12:16
こんばんは!21日(金)は、
山陰から北の日本海側を中心に雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。
その他の西日本から北日本は晴れる所が多いですが、
太平洋側の所でにわか雪やにわか雨がありそうです。
南西諸島は雨が降るでしょう。
【ふわふわかわいいで思いつくものは?】
A、雲です。
[雲]
雲は大きく分けると、発生する高さに応じて3種類あります。
さらに分けると、10種類に分けることが出来ます。
〔上層雲〕 じょうそううん
<雲の種類「十種雲形(じゅっしゅうんけい)」>
10000m 巻雲 巻積雲 巻層雲
5000m 高積雲 高層雲
乱層雲
2000m 層積雲 積雲 積乱雲
層雲
上層運はその名の通り、
上空の最も高い所(5000~13000m)に発生する雲をいいます。
上層運には・・・
・巻雲(けんうん)
・巻積雲(けんせきうん)
・巻層雲(けんそううん)
これらがありますが、とても高い場所に位置しているので、
こちらの雲から雪や雲が降ってくることはほとんどありません。
地上に辿り着くまでに蒸発するからです。
又、上層雲は高度が高く低温ですので、ほぼ全て氷の粒から出来ています。
≪巻雲≫
巻雲は、糸のように散らばった白い雲で、「すじ雲」と呼ばれる雲です。
刷毛(はけ)で描いたような形が多く、秋から冬によく見られ、
数ある雲のうち、最も高い所に現れます。
巻雲同士が重なり合ってあばら骨状になると、
次第に天候が悪化することが多くなります。
≪巻積雲≫
巻積雲は小さな雲の塊(かたまり)が、
魚の鱗のように規則的に集まっている雲です。
・いわし雲
・うろこ雲
このようにも呼ばれていますが、よく耳にする「ひつじ雲」とは別ものです。
「ひつじ雲」は中層雲である「高積雲」を指すので、
雲が発生する高度が異なります。
巻積雲の方がより高い場所で発生するので、
私達の目からは小さく見えることになります。
判別するのはやや難しいのですが・・・
・巻積雲(いわし雲・うろこ雲):一つ一つの雲が小さい
・高積雲(ひつじ雲) :大きい雲
このようになります。
巻積雲が現れ、次第に高積雲へと変化していく場合は、
徐々に天候が悪化することが多くなります。
≪巻層雲≫
巻層雲は、薄いベール状で太陽が透けて見える雲です。
この時、
太陽の周りにぼんやりと輪っかのようなものが見えることがあります。
これを「ハロ(暈)といいます。
この光の輪は太陽の光が雲の中に含まれる氷の粒に当たり、
屈折することにより、発生します。
太陽の近くで起こる現象の為、観察する時は、サングラス等をかけます。
ハロ(暈)が起きる時、即ち巻層雲が現れている時は、
すぐに天候が悪くなるということはありませんが、
徐々に天候が悪化することが多くなります。
ここまで説明した3つの上層雲は、温かい地域程、高い場所に発生します。
日本付近では高くても13000mくらいが限界ですが、
熱帯地方では15000m以上の高さになることもあります。
上層雲は太陽光をあまり遮(さえぎ)らないですので、
太陽の近くを観察する時は、注意しながら行います。
【食糧管理法公布記念日】 Food Contorol Law Proclamation Day
☆2月21日は「食糧管理法公布記念日」です。
1942年(昭和17年)2月21日に、
「食糧管理法(通称:食管法)」が公布されたことを記念しています。
この法律は戦時中の食料供給の安定を目的として制定されました。
<概要>
〇食糧管理法公布記念日
@戦時下の食糧確保
当時の日本は第二次世界大戦において、
多くの資源を戦争遂行の為に使用し、
国内における食料供給は後回しにされがちでした。
その結果・・・
国民は食糧不足に苦しんでいたのです。
★食糧管理法
そんな時代背景の中に生まれた法律です。
この法律により、食料の生産から流通や消費に至るまで政府が介入し、
管理することが可能になりました。
□目的
特に米の需給と価格の安定が主な目的でした。
@食糧管理法の具体的な内容
食糧管理法は米をはじめとする食料の需給と価格の安定を目的としていまして、
米は全量政府管理下に置かれました。
これにより、地主による小作米の販売も禁止される等、
従来の流通構造に大きな変化が齎(もたら)されました。
米の生産量や流通経路が厳しく制限されまして、
国民は配給制度によって生活を送ることになります。
政府は食糧の配分を行いまして、国民はその枠内で生活をする他ありません。
当時の人々にとりまして、
非常に厳しい制度であったことは想像に難しくありません。
このように食糧管理法は国民生活に大きな影響を与えるとともに、
日本の食文化や社会構造にも変化を齎しました。
@食糧管理法の廃止とその後
食糧管理法は1955年(平成7年)に、
米の最低輸入量を定めた輸入開始に伴いまして、廃止されました。
そして・・・
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)
こちらに引き継がれます。
この法律の廃止は、日本の食料政策の大きな転換点となりました。
食糧管理法による厳しい規制が解かれまして、
市場原理に基づいた食料流通が可能となりました。
しかし・・・
これによりまして、日本の食料自給率は低下しまして、
食の安全性や国内農業の保護に関する当たらな問題が浮上してきました。
国内農業の振興と食料自給率の向上は、
今なお、日本が直面している重要な課題です。
食糧管理法の廃止は単に一つの法律が無くなったというだけではなく、
日本の食料政策の歴史における一つの節目でありまして、
その後の日本社会に多大な影響を与えた出来事でした。
問題 食料自給率の現状からでありますが、
食料自給率の低下背景についての文章の中の???に入る、
言葉を教えてください。
食料自給率の低下背景には・・・
・国内での農業従事者の高齢化
・???
・農地の減少
これらが挙げられています。
又、食文化の多様化によりまして、
国内産の食糧だけでは消費者のニーズに応えられないという、
現実もあります。
1、農業にかかる費用
2、後継者不足
3、技術・育成問題
ヒント・・・〇農業における人手〇〇の実態
「就農人口の推移」や「技能実習生受入数の推移」を踏まえ、
日本の農業が直面する人手〇〇についてです。
・2015年:175、7万人
・2021年:130、2万人
外国人技能実習制度は発展途上国から労働者を受け入れ、
日本での仕事を通じて技能や技術を学び、
母国の経済発展に寄与してもらう制度です。
就業割合は建設関係(20、8%)、食品製造関係(19、5%)、
農業関係は9、6%です。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。


















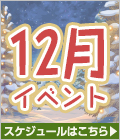









雲は10種類と数は少ないですが、変化する数がかなりありますものね。
そうですか、食糧管理法の復活を希望ですか。
なかなかこればかりは色々な利害関係がありそうですよね?
記憶が安本丹だから無理だろうなぁ・・・
これだけ外国勢にいいようにされると、
また食糧管理法を復活してほしいです。
かげねこちゃん、お忙しいところ、どうもありがとうございます。
いえいえ、今回も難しい問題です。
そうですか、半分当てずっぽうですね。
ありがとうございます。
おお~、問題のお答えですが2番の後継者不足が正解です。
この難しい問題を素晴らしいですね。
かげねこちゃん、どうもおめでとうございます(祝)
かげねこちゃんも御存知のはずですが、
全国的に農業の後継者不足問題は非常に色々なことが重なっていることが多いので、
どこから解決していくかも鍵ですよね?
これは我々にも関することですので、後継者の方が現れてくれることを強く願っています。
本日も冷えませんか?
どうか暖かくしてお過ごしくださいませ。
調べ方が悪いのか、よく分かりませんが半分当てずっぽうで答えてみますね。
2、後継者不足
これでどうでしょうか???ダメかも???