雨水
- カテゴリ:占い
- 2025/02/18 15:27:44
ニコットおみくじ(2025-02-18の運勢)

こんにちは!冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に雪が降る。
北陸、東北、北海道は吹雪く所も。
東海と関東の平野部は晴れる。
沖縄は曇りのち晴れ。
【雨水】 うすい
☆雨水は二十四節気の第2節の節気で、
雪が雨に変わって降り、春が始まる時期とされる二十四節気の一つです。
<概要>
〇雨水
日本には二十四節気という1年を24分割した季節の指標があります。
その中の一つで、雪融けと芽吹きの季節となるのが雨水です。
実際にはまだまだ寒い毎日が続くものの、
いたるところで春の色が見え始める頃です。
二十四節気 候 七十二候
雨水 初侯 土脉潤起き(つちのしょううるおいおこる)
意味:雪が融けて大地を潤す
次侯 霞始靆(かすみはじめてたなびく)
意味:春霞がたなびき始める
末侯 草木萌動(そうもくめばえいずる)
意味:草木が芽吹き始める
@二十四節気
太陽の黄経上(太陽の周りを地球が1周する軌道)の動きを、
春分日を0度として1周360度をほぼ15度ごとに24分割して、
15度ごとに季節を表す言葉をつけたものです。
さらに分かりやすく説明しますと、1年を通した季節の変化を24分割して、
それぞれの分岐点に季節を表す言葉をつけたものです。
雨水はそんな二十四節気の2番目であり、春の2番目にあたります。
立春(1番目)の次であり、
「啓蟄(けいちつ)(3番目)」の前に位置する節気です。
@雨水の意味・由来
江戸時代に発行された暦便覧(こよみびんらん)では・・・
「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となれば也」
このように解説されています。
気候が徐々に暖かくなり、雪は雨に変わり、
降り積もった雪や氷や水が融けて水になるという意味があります。
まだ寒い時期ではありますが、
ピークは越えたことで、寒さは徐々に和らぎ始め、雪融けが始まる頃です。
そして、大地が緩(ゆる)み、草木が芽吹く時期です。
又、土や水が動き始める雨水は、昔から農耕を始める目安にもされていました。
その年初めて吹く強い南風「春一番」が吹きやすいのもこの時期ですが、
突如大雪が降ることもあります。
★春一番
春一番は立春(2月4日頃)から春分(3月21日頃)の間に、
その年で初めて吹く南向きの強風を指します。
風は気圧が高い所から低い所へ流れる性質があります。
立春の頃は日本海側で低気圧が発生しやすく、
一方、太平洋側では高気圧が優勢になります。
この為、太平洋側から日本海側へと吹き抜ける風が、
「春一番」と名付けられています。
気象台によると、春一番は北日本の一部地域を除外しています。
その為、北海道や東北、甲信、沖縄では、
春一番の発表が行われないこともあります。
又、内陸部等で海から離れた地域では、春一番が吹かないこともあります。
地方により、
春一番が発生する際や風速やその他の条件が各地で設定されています。
◇春一番の発表基準
地域 最大風速 気温 気圧配置
関東地方 8m/s以上 前日より高い 日本海に低気圧がある
北陸地方 10m/s以上 前日より高いか 日本海で低気圧が
ほぼ同じ 発達する
東海地方 8m/s以上 平年値より高い 日本海に低気圧がある
近畿地方 8m/s以上 平年 日本海に低気圧がある
(又は前日)より
高い
中国地方 10m/s以上 前日より高い 日本海側で低気圧が
発達する
九州北部 7m/s以上 前日より高い 日本海に低気圧がある
地方
九州南部 8m/s以上 気温が上昇する 九州南部が低気圧の
地方 暖域に入る
対象地域には関東、北陸、東海、近畿、四国、九州の北部と南部、
奄美が含まれ、風速は概ね7m/秒以上から10m/秒以上とされています。
さらに前日の気温が平年と比べてどうかや最高気温がどうか、
時期が立春から春分の間であるか、風速がどうか等、
春一番を判断する為の条件は地域ごとに異なります。
春一番は初春の風物詩として知られていて、
春が近づくにつれて、天気予報やニュースで頻繁に取り上げられます。
しかし、春一番の条件が揃わない年もあり、
その場合は春一番が観測されなかったとされることもあります。
■春一番の起源とその歴史的背景
春一番という言葉の起源には様々な説がありますが、
特に壱岐(いき)島での海難事故と関連付けられる話がよく知られています。
壱岐島は長崎県にあり、
かつての壱岐の漁師達は春の初めに吹く、強くて冷たい風を、
「春一(はるいち)」又は「春一番」と呼び、警戒していました。
安静6年(1859年)の旧暦2月13日に、
五島列島沖で延縄(はえなわ)漁に出た漁師達は、
南方向に暗雲が立ち始めた時、「春一だ」と叫びまして、
漁師達は急いで延縄を切り、壱岐へ戻ろうとしました。
*旧暦2月13日・・・新暦では3月10日頃から3月20日頃
しかし、突然の強風と高波によって、
船は次々と沈み、最終的に53名が命を落としました。
現在の壱岐にはこの悲劇を記念する「五十三得脱の塔」という、
慰霊碑が郷ノ浦港ターミナル近くに建立されていまして、
近くの元居公園には「春一番の海難記」と刻まれた銘板が設置されています。
@雨水の時期
雨水は毎年2月19日頃です。
☆雨水の期間
2025年は2月19日(水)から3月4日(火)です。
@雨水の季節の食べ物
・独活(うど)
・春キャベツ
・蛤(はまぐり)
@雨水の頃の季節の花
・梅 ・木瓜(ぼけ)
・福寿草(ふくじゅそう) ・沈丁花(じんちょうげ)
・クリスマスローズ
問題 春一番という言葉が広まりましたのは、民俗学者の宮本常一さんが
民俗学者の宮本常一(みやもとつねいち)さんが壱岐を調査しまして、
その風習を「俳句歳時記」に記述したことがきっかけです。
宮本常一さんが次のように記した、
文章の中の〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。
<春一番(仲春)>
壱岐で春に入り最初に吹く〇〇をいう。
この風が止むまでは、漁師たちは海を恐れる。
昭和30年代には朝日新聞さんが「地方の漁師は春一番を恐れ・・・」と、
報じまして、全国に知れ渡りました。
《宮本常一》さん
1907年8月1日ー1981年1月30日
日本の民俗学者で、農村指導者、社会教育家です。
1、花風(はなかぜ)
2、花嵐(はなあらし)
3、東風(こち)
ヒント・・・〇〇〇
早春に吹く東からの風で、春の季語とされています。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。





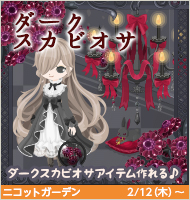




















はい、大吉でした。
どうもありがとうございます。
はい、雨水という節気がありますね。
そうですね、恐らく気温が低いからではありませんか?
もうしばらくして、春一番になる可能性ですよね?
今夜は20時までです。
お互いに頑張りましょう。
雨水という節気もあるんですね。
この前風が結構強い日が2日程続いたけど、
条件が揃わなかったんですね。
かげねこちゃん、ねこさん、お忙しいところ、
コメントとお答えをありがとうございます。
かげねこちゃん、通院は疲れますよ。
とんでもありません!疲労のあるなか、お答えとコメントをありがとうございます。
当てずっぽうで、3番の東風(こち)ですか。
実は正解で、流石ですね。
かげねこちゃん、どうもおめでとうございます(祝)
ねこさん、絵文字とコメントをありがとうございます。
そうですね、お互いにぬくぬくとまいりましょうね。
ねこさんの3番の東風(こち)ですが正解です。
ねこさん、どうもおめでとうございます(祝)
布団に丸まって、かぶって、そして・・・かけてですね。
お二人共、今夜はかなり冷え込んでいませんか?
ねこさんの絵文字とコメントのように、
しっかりと防寒をして、体調を崩さないように暖かくしておやすみくださいませ。
どうもありがとうございました。
∧_∧
(゚Д゚ )_
r⌒と、| )
ノ ノ ヽ /
/ )/
( ノ/
〈二二二二_ノ
かぶってよし!
∧_∧
/(*゚Д゚)
/ У~ヽ
(__ノ、_)
まるまってよし!
/⌒⌒⌒ヽ
(゚Д゚*)__)
フトンサイコー!!
お今晩は☆
いつも、ありがとうございますo(_ _)o
お互い、ぬくぬくで過ごせますように~☆
3、東風(こち) でしょうか?
今日は通院で疲れちゃったので、当てずっぽうで答えます。(ごめんね)
3、東風(こち)
ダメかなぁ・・・???