八幡市道路陥没穴が巨大な水たまりに?
- カテゴリ:ニュース
- 2025/02/04 23:43:55
埼玉 八潮 道路陥没事故 発生から1週間 男性は依然安否不明 捜索急ぐ 節水呼びかけ 生活面の影響は | NHK | 事故
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250204/k10014711461000.html
2025年2月4日 19時31分 から
・この記事にある画像を見ると、直径40m深さ15m(発生から72時間 4日前)と伝えられれていた陥没穴に 大量の水が溜まっているのがわかる。
事故発生当初は陥没穴に降り注いでいたのは「下水管の上部にあった雨水路が 陥没時に破損してそこから雨水が」と言われていたが、
今では 陥没穴にたまっているのは下水だろうと別記事(どこのメディアかは忘れた)では言われるようになった。
そしてのこの記事でも『汚水とみられる水もあふれ出しています。』と明言されている。
ただ その水量とか たまり具合が具体的には従来の記事ではわからなかったが、この記事添付の写真を見ると相当量であるように見える。
この記事の1週間の変遷を示す写真を見ても
2月3日の写真では まだ 「がれき撤去作業中の穴」
別の動画では すでに 水が噴き出していたが・・
それが2月4日の拡大写真を見ると、別動画で水が噴き出していた箇所周辺(それが最初の陥没地点周辺らしい)と思われる穴が すでに水没しているようだ。
・NHKのこの記事を 抜粋を交えて要約しながらコメントをする。
①『この現場の下水道管の中はふだん3分の1程度の高さまで汚水が流れています。
汚水からは、含まれている有機物から硫化水素が発生していて、その硫化水素が空気に触れると硫酸になりコンクリート製の管の腐食を引き起こします。
陥没現場の下水道管は、カーブするように埋められていることや、勾配がゆるやかなことで有機物が流れずにたまり、硫酸が発生しやすく管の腐食が進みやすかったのではないかとみられています。』←下水に亀裂が入った原因
②『軟弱な地盤』だから 亀裂から周囲の土砂が下水管に流れ込んで(道路下に)空洞ができ、陥没穴になった
③従来は 2・3mの陥没穴に落ちた車両の運転手はすぐに助け出せた。
今回のように『長時間に、災害が拡大する現場はおそらく初めて』
④『ボックスカルバートが邪魔』
以前から私も指摘していたが、下水管の上の雨水路を形成する「ボックスカルバート」)四角のブロックが、陥没穴の中に大量に落ちていて 作業の妨げになっている
⇓
今後の課題として 下水管の上に 雨水路を設置するのはやめたほうがいい。
下水管の亀裂による空洞ができたときに、上部にある雨水路のボックスカルバートが自重により落下して雨水路が崩壊するから。
歴史的経緯としたら 下水管のほうが先にできたので 後から作った雨水路が上に来るのもわかるような気がするけど
あのコンクリートブロックを張り合わせたような雨水路はあくまでも しっかりとした地盤の上にブロックを並べているのが前提でしょ!
それを軟弱地盤の上に設置したのは もしかしたら設置基準に関する法令違反かもしれないし、まだその手の規制基準ができていないのなら 早急に制定すべき!
そして ひび割れ程度だった下水管は 上から落ちてきたボックスカルバート(=雨水管のパーツ)により 広範囲に破壊された =下水だまりが拡大する一方の今の状態に!
この①~④の要因が「初めての被害が拡大し続ける現場」の実態なのでは・・
・だからこそ
⑤『救助は「短期決戦」』
『穴の中から水が引いた瞬間を狙って一気に大勢の隊員が穴に入り、運転手の男性を見つける「短期決戦」で勝負をかける』
『「運転席のキャビンが見つかれば周りの土砂を重機で払いのけキャビンの近くは、隊員が手やスコップで掘り起こせると思う」』
⑥『水止めないと何も進まない』
⑦『下水は止まらない』
『下水は自然に勾配で流れているので止めることができない。市民の皆さんが水の使用をおさえていただくしか止める手段がない』
報道で 始めれ⑥⑦について明言されました。
さすがNHK
ただし このセリフは 事故発生の翌日、遅くとも3日目には報道してほしかった!!!!
⑧地域では 通学路の自動170人で、何度もコースを変更して教員たちが登下校につきそっているそうだ。
『県は陥没現場直近の5軒の家の住民たちに避難を要請』
通信ケーブルの断線により固定電話が使えない
◇ ◇
今後に向けての提言
・現場における 1分辺りの排水能力、
今日の3時間の節水呼びかけによる水位の変化をもとにした
現場への1分辺りの下水の流入量、
現在 たまっている水量(推定)
をもとに 『水道使用制限時間=上水道による配水を止める=断水時間』を割り出して、
陥没穴の水抜きを敢行したうえで 一気呵成に運転席を掘り出す作業を行う
⇓
現場より下流に当たる下水道の詰まり具合の確認
⇓
下水路・雨水路の復旧
と3段階に分けて 対応
(上水道への配水を停止しないと 下水の流入は止められない! 節水の呼びかけ程度では 現場の水抜きは無理なのでは? よっぽど強力な排水方法がない限り、と 私は考えます
そんな 水をくみ上げて それを 近くの川まで運んでいくというピストン輸送みたいなことをしていては 対応できないのでは?
そのあたりは現場の人がこの1週間の状況を集計・分析すれば明白な予測が立つと思いますが・・)
政治的判断ではなく 現場作業の現実に即した
市長・知事の対応(必要物の確保 関係自治体・周辺自治体との折衝・市民への指示・命令の発令等)を きちんとやっていただきたい。
この1週間 現場で できる限りのことをやって
今の巨大な「排水だまり」ができているという現実を
真剣に受け止めて 排水の流入を遮断するために必要な行政的決断をするのが首長の責務です!
・今後の課題:国会・内閣レベルでなすべきこと
以前から
塩素系洗剤と酸素系洗剤を混ぜると 硫化水素が発生する(「混ぜるな危険」表示が 洗剤についたw)
下水管の中で発生した硫化水素や 硫化水素から硫酸に変化したものが 下水管を腐食し、亀裂を引き起こす
ということは 繰り返し報道されてきました。
(※上記の認識の誤りに気付いたので 正しい対策については 下のコメント欄に書きました。巨額な資金が必要なようです だから 国会・地方自治体は そのための予算を組め!)
今回初めて、「下水管に亀裂ができると そこから周囲の土砂が下水管の中に張り込み それらは 下水によって下水管の中を押し流されていくから、下水管が詰まるのではなく 下水管の周辺に空洞が広がった 道路陥没になる」ということが 明確に 全国ニュースとして報道されました。
それ系の話は チラチラ聞いたことはこれまでもありましたが・・
為
なのでまず、亀裂防止の為に 塩素系洗剤と酸素系洗剤の販売制限を検討すべきでは?(※この辺り私の誤認識の反映です)
業務用に関しては、それらの洗剤を使用した場合の処理方法
(脱塩素・中性化した水でなければ排水してはだめ
使用した水から現場で脱塩・中性化できないならば
すべて固形化して 専用処理場を作ってそこで処理する)
などの 規制と 処理方法や処理施設の開発を
そして 家庭用洗剤は・・
(私個人としては 塩素系の漂白剤は不要、酸性の洗剤もさほど必要がないと思う。
日ごろからこまめに掃除していたら 塩素系洗剤も酸性の洗剤もいらない
どうしても 落とせない汚れが付いたら 1・2年に1度くらいの頻度でサンポール(酸性)を使います)





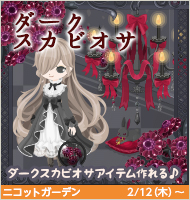

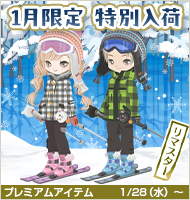





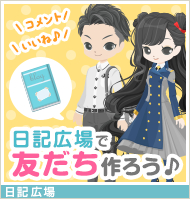












ただ 削除すると話の流れがおかしくなるので、続けて 認識修正に至った過程と 正しい対策について書かれたサイトの紹介を コメント欄で続けて投稿しました。 (記事本文だけなら削除訂正も可能だったのですが
コメント欄まで使ってしまっていたので 編集すると さらにややこしくなるので)
まことにすみません
ちなみに、02/05 04:30 2025/02/05 04:32 に引用投稿した 元サイトの投稿主は
圧力式下水道収集システム - 日本産業機械工業会 だと思います
(2) 小規模施設での対策
圧力式下水道収集システムや真空式下水道収集システムなどの収集システムは、汚水発生源に隣接した施設であり新鮮な汚水を短時間で収集するため、本質的に硫化水素が発生しにくい施設といえます。又、圧送距離が短いマンホールポンプ施設などの小規模輸送システムも嫌気状態が短時間となるため、硫化水素が発生しにくい施設といえます。
硫化水素の影響が生じると前記のような対策が必要となりますが、小規模ポンプ施設ではコスト的に十分な対策を行うことが難しいため、施設の設計段階で硫化水素が発生しにくい施設とするために次に点に留意する必要があります。
①
圧力管路内の滞留時間を短くする。
圧送距離が長くなると1回のポンプ運転で圧力管路内の汚水を入れ替えることが難しくなり管路内の滞留時間が長くなるため、圧送距離は可能な限り短くします。
②
圧力管路内の流速を確保する。
一般的に圧力管路内の最低流速は0.6m/s以上といわれていますが、理想流速としては1.0m/s~1.5m/sともいわれており、管内流速を1.0m/s以上を確保することで管内堆積物の低減が図れます。
③
汚水発生源の近くにポンプ施設を設置する。
流入管路内での管内堆積物が硫化水素発生の原因となりますが、汚水発生源の近くにポンプ施設を設けることで流入管路が短くなり管内堆積物の低減が図れます。
④
ポンプ運転間隔を短くする。
供用開始直後など汚水流入量が少ない時期は、ポンプ槽内での汚水滞留時間が長くなるため、ポンプ運転水位幅などを調整してポンプ運転間隔を一時的に短くすることで、滞留時間の低減が図れます。
※本文は、雑誌「月刊下水道」に投稿した原稿を加筆修正したものである。
作成日:平成19年12月18日
(社)日本産業機械工業会 排水用水中ポンプシステム委員会
よりコピペ
https://www.jsim.or.jp/haisui/web-4/pump_085b.html
下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2001年版 日本下水道協会 より
図-1 圧送管内での硫化水素の生成と腐食域の概念図
硫化水素対策
(1) 基本的な対策
管路施設における腐食対策は、コンクリートの腐食メカニズムを断ち切ることが重要であり、次の対策があげられます。
表-6 硫化水素対策
①
硫化水素の生成を防止する
空気、酸素、過酸化水素、硝酸塩等の薬品注入により下水の嫌気化を抑え硫化水素の発生を防止する。
②
管路を清掃し微生物の生息場所を取り除く
管路の清掃により硫化水素発生の原因となる管内堆積物を除去し、また硫酸塩還元菌や硫黄酸化細菌の生息場所を取り除く。
③
硫化水素を希釈する
硫化水素ガスが低濃度の場合、硫黄酸化細菌の増殖が抑制される。換気により管内硫化水素を希釈する。
④
気相中への拡散を防止する
酸化剤の添加による硫化物の酸化、金属塩の添加による硫化水素の固定化等の方法により硫化水素の気相中への拡散を防止する。
⑤
硫酸塩還元菌の活動を抑制する
硫酸塩還元細菌に選択的に作用する薬剤を注入し殺菌又は細菌の活動を抑制する。
⑥
硫黄酸化細菌の活動を抑制する
硫黄酸化細菌に選択的に作用する薬剤を混入したコンクリート(防菌、抗菌コンクリート)を用いる。
⑦
防食材料を使用して管を防食する
樹脂系資材や被覆(ライニング)等により腐食を受けるコンクリート表面を防護する。
排水処理施設における硫化水素の問題と,
薬剤を用いた対策技術
小島 英順
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/49/4/49_254/_pdf#:~:text=%E5%87%A6%E7%90%86%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%20%EF%BC%88%E5%BC%8F%201%EF%BC%89%EF%BC%8E
・もしかしたら 洗剤の混ぜるな危険ではなく
,微生物が水中の硫
酸イオンを利用して有機物を代謝する際に生成される
(式1).
SO4 2-+2C(有機物)+2H2 O → 2HCO3-+H2 S が原因
,工場では生産プロセスで硫酸塩類が使われたり,排水処理においても中和処理や凝集処理に硫酸塩類が使われたりするため,排水からの硫化水素発生はごく一般的に起こる現象
とありましたので、 洗剤は関係なかったかもしれない。 すみません m(__)m
排水処理施設における硫化水素の問題と,
薬剤を用いた対策技術
小島 英順
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/49/4/49_254/_pdf#:~:text=%E5%87%A6%E7%90%86%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%20%EF%BC%88%E5%BC%8F%201%EF%BC%89%EF%BC%8E
・もしかしたら 洗剤の混ぜるな危険ではなく
,微生物が水中の硫
酸イオンを利用して有機物を代謝する際に生成される
(式1).
SO4 2-+2C(有機物)+2H2 O → 2HCO3-+H2 S
が原因で 洗剤は 関係なかったかもしれない。 すみません m(__)m
「混ぜるな危険」は何を混ぜてはダメ?危険性や混ぜてしまったときの対処法を解説
https://meetsmore.com/services/bathroom-cleaning/media/79815
最終更新日: 2024年11月07日
・化学式 塩素系漂白剤・洗剤から発生する塩素による健康被害、 それぞれの製品名など 具体的に書いてます
さらに 家庭でよくやりがちな「使い方」の危険例も具体的に、⇓の引用
「便器のカビ取りにカビキラーを使い、その後にサンポールで便器の掃除をする
お風呂掃除にクエン酸を使い、その後にカビ取りをするためにカビキラーを使う
食器用酸性洗剤で食器を洗い、その後にシンクの排水口掃除でパイプクリーナーを使う」
「塩素系のカビ取り剤を浴室の天井に使い、床面の水垢汚れを酸性洗剤で落とそうとする
洗濯で服に付いた油を落ちやすくするために食器用酸性洗剤を付け、そのまま洗濯機で塩素系漂白剤を使って洗う」
「台所の排水口掃除にパイプクリーナーを使い、その後シンク掃除に酢配合の洗剤を使う
カビキラーで掃除したのにお風呂の黒い汚れが落ちず、カビキラーをサッと流しただけの状態で、お風呂用酸性洗剤で掃除する」
「酢配合の洗剤でシンクを掃除した後、軽く洗い流しただけで、パイプクリーナーで排水口を掃除する
お風呂用酸性洗剤で掃除したのに黒い汚れが落ちず、洗剤が残ったままでカビキラーを使う」
硫化水素と下水の腐食問題を初めて知ったときから、家庭で使う洗剤をどちらか一方に絞ろう・量を減らそうと試行錯誤の末に 私が出した結論であり実体験に基づく所見であります)
「洗剤=洗い流すときに使う=使った洗剤はそのまま排水として下水に流れ込む」という観点にたてば、
洗剤の使用・販売制限をやらんと どうしようもないでしょう。
しかも 液体洗剤だけでなく 固形タイプ・粉タイプについても 同様の規制が必要と考えます。
最低でも 「洗剤コマーシャルの禁止」は必要と思います
家庭用洗剤なんて なければないで かなりの部分何とでもなるのですから
実際の生活場面から どうしても「必要」を感じて、店にホームセンターに行って、そこで製品を購入する
そういうスタイルでいいのではないかなと思う、洗剤に関しては。
そして 「効果が実感できる製品を持続的に使い続ける」ようになれば・・
そんなに多種類の洗剤が排水に交じって化学反応なんてことも起きにくいと思うのだが・・。
・下水管が腐食してからでは遅すぎる
下水管の腐食を発見する点検コスト、下水管の取り換えコストを考えれば
洗剤の使用・販売規制をするほうが 社会的には無駄なく・対費用効果が高い 合理的対応と考える
洗剤メーカーだって 無駄な開発費用・コマーシャル費用を節約できて 地道に 良い自社製品を売り続けて経営安定・健全化すると思う
損するのは 販促バックマージン狙いのチェーン店とTV会社だけ。
それらの会社利益は いわゆる社会に寄生する輩の利益だら
それらをカットするのが 健全かつ持続的発達可能な日本国を維持するための 国としての必要な選択であると 考えます。
・「公共の利益」とは 声の大きい輩が 日本の納税者を搾取する口実として使うものであってはいけないのです!