節分
- カテゴリ:占い
- 2025/02/02 15:55:40
ニコットおみくじ(2025-02-02の運勢)

こんにちは!低気圧の影響で、西日本は曇りや雨。
東海と関東甲信は午前に雨が降り、積雪の恐れがある。
北日本は大体晴れる。
沖縄は曇り。
【節分】 せつぶん
☆節分は季節の変わり目に邪気を払う伝統行事です。
<概要>
〇節分
@2025年の節分は例年より1日早い
節分といえば2月3日と認識されることが多いですが、
2025年の節分は例年より1日早い2月2日(日)に行われます。
@地球の公転周期により変動
節分は「季節を分ける」という意味があり、立春の前日を指します。
この立春の日付は固定されておらず、地球の公転周期によって変動します。
その為、節分の日付も変わることがあります。
@地球の公転周期と暦のズレ
地球が太陽を回る公転周期は約365、2422日です。
この「0、2422日」という端数が4年ごとの閏年で調整されますが、
完全には一致しません。
この為、年々少しずつ暦とのズレが生じます。
このズレが積み重なり、節分の日付が変更されるタイミングが訪れます。
@2025年の2月2日は124年ぶり
1、立春が2月3日の23時59分
2、2月3日が立春の日
3、その為、その前日の2月2日が節分になる
日本の伝統行事である節分は明治時代から令和の時代まで、
ほぼ毎年2月3日に行われてきました。
この長年の慣習が124年ぶりに変更しました。
1901年(明治34年)2月2日に実施されて以来、
節分は2月3日で定着してきました。
★暦法の精密さを示す機会
この変更は単なる暦の調整ではなく、
日本の暦法が持つ精密さが前回の法則と調和を示す貴重な機会です。
この歴史的な節目は、
日本の伝統文化における天文観測の制度の高さを物語っています。
江戸時代から続く歴訪の知恵が、
現代の科学技術で裏付けられた形で実現される瞬間です。
☆新たな暦の周期の始まり
特筆すべきは、この変更が一度限りではないという点です。
2029年にも同様に2月2日となることが予想されていて、
新たな暦の周期が始まることを示しています。
日本の伝統行事が持つ科学的な側面と文化的な価値が、
より多くの人々の関心を集めることになるはずです。
★立春の日付変動が節分の日付を決定
立春の日付は、地球と太陽の位置関係により微妙に変動します。
◇地球の自転と公転(地軸の傾きと四季)
地球は太陽の周囲を周回する惑星です。
様々な地球の現象(雨・雪・風等)や、
人間の営み(都市の形成、文化、農業)は、
地球という星の環境を前提に成り立っています。
▲地球の自転
北極と南極を結んだ直線(地軸)を回転軸(自転軸)とし、
おおよそ24時間で地球が1回転する現象のことを指します。
△地軸(自転軸)の傾き
太陽から見ると、地球の地軸は23、4度傾いています。
この為、季節により地表と太陽の位置関係が変わり、
地表が太陽から受け取る太陽光の量(日射量)が変わります。
この違いが季節による気温差を生み出し、
日本等の中緯度地域で四季がみられます。
▼地表から見た太陽の位置は1年間で周期的に変化
・夏至:太陽は北回帰線(北緯23°26′)の真上に位置する
・冬至:太陽は南回帰線(南緯23°26′)の真上まで動く
この為、北半球では日射量が多い6月前後が夏となり、
反対に日射量が少ない12月前後が冬となります。
南半球はその逆になります。
△地球の公転
地球の公転とは、地球が太陽の周りを約1年で1周する現象です。
地球の地軸が傾いている為、
季節によりまして、太陽との位置関係が変わります。
その結果、季節によって気温が上下しまして、
日本では四季を作り出しています。
この天文学的な現象が、節分の日付決定に直接的な影響を与えています。
2025年は、特に注目すべき年になりまして、
124年ぶりに節分が2月2日に実施される理由も、
この立春の日付変動に基づいています。
★節分と立春の定義
節分は「立春の前日」という明確な定義を持つ伝統行事です。
立春は二十四節気の最初を飾る重要な節目で、
太陽の黄経が315度に達した時点を指します。
日本の伝統暦では、立春を春の始まりとして重視してきました。
☆2025年の立春と天文学的な精度
2025年の立春は2月3日午前11時50分に訪れます。
太陽の位置を精密に決算した結果、立春の時刻が決定されました。
現代の天文学では、地球上のどの地点でも立春の瞬間を正確に把握出来ます。
立春の日付変動は、地球と太陽の位置関係を正確に反映しています。
★伝統と科学の調和
一般的なカレンダーでは見過ごされがちな天体の動きを、
日本の伝統暦は繊細に表現しています。
興味深いのは、節分の日付変更が単なる暦の調整以上の意味を持つ点です。
☆伝統と最新技術の融合
日本の暦法は古来より、こうした自然界の法則を尊重して、
必要に応じて調整を行ってきました。
現代では原子時計やGPS等の最新技術を用いて、
地球の公転周期をミリ秒単位で測定しています。
このような高精度な観測データに基づき、暦と自然の調和を図っています。
★新しい暦の周期の幕開け
2025年の2月2日の節分は、
新たな暦の周期の始まりを告げる歴史的な出来事です。
天文学的な計算によりますと・・・
・2029年
・2033年
・2037年
このように今後は4年周期で2月2日の節分が訪れます。
国立天文台の暦計算によりますと、
21世紀中に2月2日となる節分は合計19回出現する予報です。
☆規則的な周期の特徴
この現象は、
地球の公転軌道と太陽の位置関係が規則的なパターンを反映しています。
注目すべきは、この4年周期が約100年続くという点です。
2120年代までは、
閏年の翌日に2月2日の節分訪れる規則性が保たれます。
問題 節分の行事は古代中国の風習が起源とされ、
鬼を追い払う為に行う「豆撒き」は邪気を払うとともに、
福を呼び込む意味が込められていることは有名です。
そして、恵方巻は元々関西地方で食されていた巻き寿司がルーツですが、
その関西地方の発祥した都市名を教えてください。
1、大阪
2、京都
3、神戸
ヒント・・・〇「節分の巻きずし丸かぶり」は、
その起源が詳(つまび)らかではない謎多き行事食
・船場で幕末から明治の初めに商売繁盛、無病息災、
家内円満を祈願して行われるようになった説です。
・船場の色街に勤める女性が階段の中ほどに立ちまして、
巻き寿司を丸かぶりしながら願い事をすると、
それが叶ったというジンクスにあやかったとするものです。
@船場(せんば)
豊臣秀吉公の大阪城築城による労働力需要がきっかけで、
生まれた町とされ、繊維業者で知られる商業地になりました。
お分かりの方は数字もしくは恵方巻発祥の都市名をよろしくお願いします。




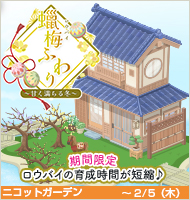

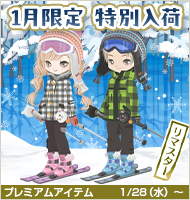






















はい、立春は天文学的精度で出しますね。
ああ~、そうですね、日本の暦の歴史が重いですね。
なるほど~、案外風習というのは子供の頃、
親等がやっていたからと、難しく考えないで当たり前のことだと思ってが多いですね。
それでよろしいのではありませんか!?
日本の暦の歴史が重いです(。-人-)
丸かぶりは昭和初期生まれの父の頃から、
祖母の時代から気がついたらやっていたという感じで、
起源とか考えてないのが大阪らしいなと思っています(笑)
コメントとお答えをありがとうございます。
かげねこちゃん、どうお疲れ様です。
おおお~、調べてくださりましたか。
嬉しいですね!どうもありがとうございます。
問題ですが完璧ですね。
定かではなくても、1番の大阪が正解なのですよ。
素晴らしいですね!やった!やった!
どうもおめでとうございます(祝)
私はきちんと豆撒きをして、恵方巻も食しました。
かげねこちゃんがなされたのかは分かりかねますが、
していなくても、食していなくても、
かげねこちゃんの分の「無病息災」の願いも兼ねてです。
今年も体調に気をつけてまいりましょうね。
疲れたはずです、どうかゆっくりとおやすみくださいませ。
1.大阪
では如何でしょうか?