東映時代劇をYouTubeで
- カテゴリ:コーデ広場
- 2025/02/02 14:06:59
まだ寒いけど、庭の梅のつぼみはかなり膨らんできた♬
もらったステキコーデ♪:23
ひょんなことから 現在 東映時代劇(TV)が、YouTubeに多数アップしていることを知った。
コマーシャルなしで まるっと見れるので お得感満載。
・古くは 「仮面の忍者赤影」
私は 高校時代に再放送で見て、赤影さんハンサム~h♡、
(元祖お醤油顔かもw)
白影さん 素敵なおじさま~♡ とキュンキュンしましたが(笑)
あれ よく見ると、竹下半兵衛役で里見浩太朗さんが出ているのよね(笑)
・「旗本退屈男」月形龍之介←母のごひいきw
エンタツとか わりと関西でおなじみの方々が出ているらしい。
私は、青池さんの漫画によく出てきたので知ってる程度です
・昭和で同じみの 「桃太郎侍」高橋英樹さん
第1話を見ると、殺陣以外のシーンでは ほとんど 出演者がしゃべりまくり、しかもセリフが長い!
子供は寝なさいと寝室に追いやられ、でも隣の部屋は父が時代劇を見ていて、 私は そのあらすじをしっかり把握できたのも ラジオドラマなみに セリフが充実していたからでした。そして効果音による臨場感と 音楽による場面づくりも
ふすま越しに聞く時代劇の音から学んだw。
何しろナレーターなしで 役者さんたちのセリフのみで話が進行していた桃太郎侍。
あるいは ナレーションで進行するその他のTV時代劇など
いろいろなパターンのある脚本・構成のしっかりとしたドラマ達だったから。
当時は、芝居の台本としては 劇団のシナリオより よっぽどしっかりしていたと思う。
だから 小学校高学年のころ 台本書きをや芝居の演出を趣味でやっていた時も それまでに聞いて覚えていた時代劇の場面転換やつなぎのシーンが おのずと反映されました。
しかも 歌舞伎界から TV時代劇に出ていた方々もいたので 自然に歌舞伎町のセリフ回しも覚えました、小学生のころに。
と、幼き日々を思い出しつつ 新鮮な目で 過去作を見て・・
・それが 「3匹が斬る」になると、同じ高橋さんでも 表情でしゃべるようになるんです。セリフがかなり短くなったからかな。 時代の変遷を感じました。
ちなみに 「3匹が斬る」の第1話は かなり荒っぽいので
びっくりしました。
高橋さんが 貫禄ある男の色気駄々洩れで、役所広司さんが
大人になりかけの青年っぽい向こうみずさをまき散らし、その間をとりもつ小朝さん、この3人の組み合わせが好きでした♡
などなど 時代順にみていると 日本の時代劇・TV時代劇の変遷と その中を生き抜いた役者さんの姿を見ることが出きて
なかなかに面白いです。
・松竹時代劇(映画)とは また違った魅力の東映時代劇(TV)
総踊りが毎回出てきたのは どこの会社の時代劇だったっけ?
かなり幼いころ あらすじもさっぱりわからない未就学児のころかな、家族そろってみたTVの時代劇映画は、とにかく 殿様を囲んだ歌と踊りが 楽しかった。
あるいは 道中ものでも 突如始まる歌と踊り(芝居の一座)
そして たいてい 漫才やら 演芸つきで。
それが いつも楽しみでした。
今から思うと 昨今のインド映画(踊るマハラジャなど)の原型みたいな時代劇映画だったなあ。
あの楽しい映画時代劇も ユーチューブにアップされるといいのになぁ。
そういう過去作に比べると、昨今のドラマも時代劇風ドラマも出演者がすごく少ないし 殺伐としていると思う。
つまり 製作費に 芸のある出演者をほとんど使ってないのが昨今の作品><
昔は どんな端役の人でも ちゃんと芸を身に着けていたのに><




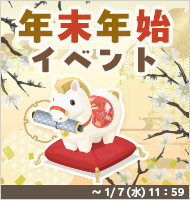


























時代劇がきっかけです
マトリックス以後の映画のスタントは ワンパターンになって面白くない
バートレイノルズたちが 古典的スタントの終焉を 祭りのように映画でたたえたのちは
大掛かりな機械力を使ったスタント(例えば https://gigazine.net/news/20160516-10-sfx-movie/ で紹介されているやつとか)とワイヤーアクション(リーリーチェンは 自分とわが子の競演で 縄を使って ロープアクションの実態をストーリーに組み込んで演じてましたw あれ リーリーチェンの地強くと親子の信頼関係があるから こどもをふりまわせたんだよなw)になり あっという間にCGの小道具化した俳優たち
そういう意味では ジェラシックパークで あれだけCGを多用しながらも 役者の演技・個性・人間味と人間の存在を常に中心に置き続けた映画監督とプロデューサーは やっぱり偉いわ。
というわけで 今の日本のTV関係者が どれだけ 腐った人間が 人の尊厳を否定して金儲けに走った作品ばかりを垂れ流しているか (だからもうこの30年近く 私はほとんどTV作品をみないし 民放も40年くらい距離をあけ続ける一方なんだけど) こうして書き出してみると 改めて思うわ
その結果として 実生活なり生き方によき影響が出ればそれでよし
そこまでいかずとも 見て楽し 演じることにより己の希求する道を歩むことができれば
それもまた良し
といった感じのものではなかったっけ?
そこに お金とか 商売とか 金儲けとかって物欲と、演じることによって評論することによって認められたい、ほかの役者に負けたくない・上に立ちたいとかいう私欲が混じって ワヤワヤに
さらに 各種方法論が まるで金科玉条のセオリーか はたまた その方法論を実行することが目的であるかのような 各種転倒が起きて ガチャガチャに
とどめが 安易に金を稼ぐための手続きに堕ちたのが 今のTV・週刊誌・ネットが一体化した複合メディアの 総演出体制、それが 大衆をも絡めとって 虚を実だと主張して リアル社会を動かし始めたのが
今回の「中居」騒動。
イチバンの問題は 松本を代表とする吉本集団とフジTVなのに
そこを隠すために 中居さんや 挙句の果てには鶴瓶まで生贄にして!!
スシローはぜろ ですな。 もともと足を踏み入れたこともない店なので ボイコットの仕様がないもんで。
ちなみに 今回のフジTVの動きは 完全に 劇場型自己演出そのものですわ。さすが 自社にとって都合の良い台本書きと演出がうまいですな 実に下らん! N党並みのくだらなさ&害悪ですわ
そういう意味では 学校の活動に なんでも間でもコンテストだの全国大会だのを持ち込んだのが
誤りだと考える
受け持った子供たちを通して 己が褒められることを望む教師
大会の成績を通して 己の評価を上げようとする学校長
平静以後そんなのしか いなくなったのではないかといいたくなるほど ひどい学校現場
教育の荒廃は 実は教師から始まっているのです
なぜか 「荒れる子供たち」って記者どもは書きたがるけどね
あれほどひどい嘘はないと思う
今も昔も 成長パワーが荒(すさ)みとして発言してしまう子供たちはいる。
それを しっかりと受け止めて その子にとっての「現実」「耐え難い状況」を 乗り切って次のステップに導くのが 教師の役目・大人の責務だろうに。
腐った根性の子供は 周囲の大人が許容する範囲を見極めて悪しき行いをする。
だから どんだけ悪いことをしていても、大人からは眼をつけられることはない
荒んでる子は、その子自身では消化できないほどの厄介ごとを抱えて(押し付けられる状況で) それを吐き出して 何とか前に進もうともがいているだけ
その見極めもせずに よくもまあ すべてを子供の問題に置き換えて 「荒れる学校・荒れる子供たち」なんていうなと思う。
教師=子供を上手に食い物にして生活している輩 そういっても過言ではない状況が蔓延している学校という枠の中に子供たちを押し込めているから「崩壊」しているだけだと思いますよ。いわゆる「学校崩壊の実体は。
大衆演劇の質を見れば 社会の質がわかる
そういう意味では この半世紀で 日本社会の根底がずいぶん腐ってきたなと言わざるを得ない
とほほ それは いいかえれば 自分もまた 非力だったなぁ 大勢におされちまったぜ><ってことになるから しくしく
その手前には 戦前の生活つづり方運動があるのだけど
あれは・・ 教師が 本当の意味で 子供たちと生活感覚を共有してないと ただの空論になる
だから あれ系の台本を見れば 書き手が ほんまもんの教師なのか 似非なのか一目瞭然だと私は感じた。
ほんまもんの教師は稀有です。そういう教師にあこがれてうにゃうにゃ言って「実践」なるものを自分が受け持った子や後輩に吹きまくる奴に 碌なもんはおらんかったというのが 私の実感ですわ(笑)
そして それを 受け持った子供たちとともに演劇に昇華している教師に 嫉妬心むき出しに攻撃していた
臨床心理の某教授は 糞そのものだったなと 今になって思う。
生活劇だったかな 子供たちが成長の場として劇を教材にできる教師というのは、本当の意味で、子供の涙を受け止められる人だと思うのだけど、「ふふん」でごまかすカウンセラー殿には 生涯かけても実践することのできなかったであろう世界だわ。
そして あれは 発表のための劇ではなく、劇として練り上げていく過程にこそ全てが含まれているのだということがわからない糞教師(日教組かぶれ)があまりにも多すぎたのが 日本の学校教育が 落ちぶれた一因でもあると思う
(ビバ名古屋市の公立図書館!! )
それで思い出したのですが、観阿弥世阿弥の能学論から、戯曲とか シェークスピアやフランスでは誰だっけ まあ一応 ドイツも含めて有名な作品も せっせと読んで セリフのけいこを一人でこっそりとやって シェークスピアもモリエールも なんやらかんやら そしてNHKBS放送開始当時は それらのあちゃらの国立劇場とかの演目の字幕付き全編中継も多かったので それもせっせと見て、ミラノスカラ座の来日公演以後はオペラに感心が映ったけどそれまでの数年間は かなり古典から当時としての現代劇(別役実あたりまで)まで いろいろ見てました。ほんとNHKさまさま。台本を読んだ時の印象と 劇になったときの印象の違いとか。あのころは 心も頭もフル回転で集中してましたねぇ 演劇に。だからギリシアの野外劇場の復刻形式の演劇も当時出来立てほやほやのをNHKで見たと思う。 読書の一環としては 女の闘いが一番面白かったけど。(一つには 巫女さん?達の運命の詞が付かない形式だから 読みやすかったというのもある)
で 思うわけ、本来、芝居も演劇も、演じる側・台本を書く側からすれば、自己のありようを客体視する営みの一環として演劇があり、あるいは客体化したものを 観客にアピールする劇があり、さらに踏み込んで
己を取り巻く社会の実相を描きつつ、観客や演じる子供たちに、己の理想・夢・希望などを観客に伝えようというする営みでもある演劇
それが 商業化する中で、同じ場に集った者たちの共感の場における ひと時の楽しみをというエンターテイメントになり・・
(これを 究極まで行ったのが アメリカのエンターテイメント・ショービジ)
まあ このあたりまでが 映画時代劇~初期のTV時代劇
ところが 1980年代後半あたりから あれよあれよいう間に TVにおいては、 金稼ぎのために耳目を引けばそれでOK 令和においては バズらせて稼ごうぜ 中身なんぞどーでもいい、の世界になってしまった
思えば TV時代劇の変遷は 日本における 演芸・劇の世界の堕落と歩調を共にする写し鏡みたいだなと思った。
だから 私は 吉本とジャニーズが嫌い。昨今のTV俳優さんの大多数は見たくもないと思っている
くだらない