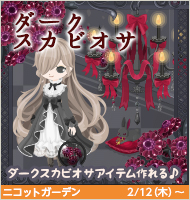囚人のジレンマ
- カテゴリ:小説/詩
- 2017/01/12 18:13:48
(お題消化)
現在まで、学校の授業以外で「詩」というものを読んだことは無いので、これについては書くことがありません。
小説についても、大学時代は歴史小説を読みあさりましたが、社会人になると読まなくなりました。
どうも小説を読み始めると、最後まで読まないと気が済まない性格なので、時間が自由な学生時代だけのものでした。
社会人になって読んだ小説は二つ。
一つは「銀河英雄伝説」で、その後アニメのDVDも購入・・・とはいっても、ヤン・ウェンリーファンだったので、ヤンが死んだ後の第四部は買わなかったし、小説も九巻以降は記憶にありません。
もう一つは、「ネバーエンディングストーリー」で、これは先に映画の方を観て、「いくつでも・・・」という台詞に人間の思考を超える思想を感じました。
しかし、小説を読んでみると、それはこの小説の半分でしか無く、実際にはそんな美味しい話では無かったのですが・・・
で、この冬読んでおきたい・・・小説とは言えないかもしれませんが・・・ものは、「リヴァイアサン」(トーマス・ホッブズ)という、どちらかというと哲学書かな。
トーマス・ホッブズは、17世紀の英国の哲学者で、人間には社会性が無いという人類学上の見解を基本として、それでも社会を形成する必要性と問題を明示しています。
勿論、他のヨーロッパの哲学者達も同様な観点から、様々な知見を提示しています。
つまり、そもそも哲学とは特定の学者や偏屈な爺さんが語る難しい学問では無く、社会性の無い人類が、現在の人口を維持しながら平和的に存続する手段として、どの様に社会を形成していくべきものなのかを、全ての人間が考えていくべきものなのです。
「IQ246」というドラマでも、「一人一人の歩みは小さくても、それが前に向かっていればいい」という台詞がありました。
何故、トーマス・ホッブズの著書を読もうかと思ったのかは、だいぶ以前に書きましたが、放送大学の山岡龍一教授の講義を聴いてからです。
その山岡教授を含めた数人が行っている講義に、「公共哲学」というものがあります。
そして、第十四回目の講義は、「国際条約」についての話でした。
そこで出てきた話に、表題の「囚人のジレンマ」というものがあります。
「囚人のジレンマ」とは、次のことが前提となります。
A、Bという二人は犯罪を共謀して犯罪を犯しています(つまり、共犯)。
二人は別件で逮捕され、検事の取り調べを受けています。
取り調べは別々の部屋で行われ、互いに連絡をとることが出来ません。
もし黙秘したまま、例えば共犯者の自供などによって犯罪が確定したなら、黙秘した方は重い罪(利害指標:-6)が与えられます。
一方、自供した方は減刑され、比較的軽い罪(利害指数:-4)となります。司法取引の様なものでしょうか。
しかし、両方とも自供しなければ、つまり黙秘し続ければ別件逮捕の要件であるとても軽い罪(利害指数:-1)となります。
そこで二人の犯人はどう考えるかという問題です。
お互いは連絡できないのですから、一方の共犯者はどう答えるかは分かりません。
しかし、相手がどう答えようと、自分に利益があるのは「自供」で、-6から-4になり、利益が+2となります。
では自供した方がいいと考えるかというと、両方黙秘して別件のみの罪となる-1(利益+3)よりも遙かに利益は少なくなります。
これが「囚人のジレンマ」です。
観点は少し違いますが、国際条約にも同様なジレンマが起こります。
多数の国家が締結する国際条約が発効されれば、各国は+10の利益を得るとします。
しかし、その条約を履行する為には、各国は負担を強いられ、その負担による利益は-5となり、差し引き+5の利益になります。
そこで、多数の国家が参加するのですから、自分の国は参加せずに、つまり負担をせずに、世界公共利益だけを得ようとする国があれば、まるまる+10の利益を得ることができ、いわゆる「ただ乗り」となります。
そういう自体を避ける為、国際条約を締結する際には、加盟国数を規定し、一定以上の加盟国が無ければ発効しない様にしています。
加盟数に満たなければ、協力的な国家も、非協力的な国家も、その条約による公共利益を得ることができません(利益0)
それなら協力した方が利益があるだろうと、参加加盟国が増えることが期待されます。
しかし例えば、規定を、関係する全ての国の加盟が条件となれば、一国でも反対すれば、その条約は発効されず、多くの国の利益が失われる為、大多数の参加加盟国だけで条約を締結しようとするでしょう。
そうなれば、非参加国の「ただ乗り」が成立することになります。
こういう国際条約の話をすると、核拡散防止条約におけるイランや北朝鮮のことを思い浮かべる人も多いと思います。
しかし、これは元々おかしな条約なのです。
既に持っている国は持つことが許され、これから持とうとする国は持つことを許されない。
どう考えても不平等条約です。
銃を構えた相手と、丸腰で対等に話し合えるでしょうか?
既に持っている全ての国家が、その管理を国連にゆだね、それぞれの国の都合で発射できない様にしてからなら、核拡散防止条約も効果があるかもしれません。
何故そうしないのでしょう?
私は、どちらかというと、この国際条約の話を聞いて思い浮かんだのは、京都議定書に非協力的な米国や中国のことでした。
まぁ、それ自体に排出権の売買とか、黒い部分がありますが、それはとりあえず置いておきます。
中国は経済発展中のため、多少の猶予は与えてもいいかもしれませんが、既に発展を遂げ、世界支配的な国家となった米国は何故非協力的だったのでしょう。
まさに、「ただ乗り」しようとしているとしか考えられません。
米国に対する反感を持つものが少ない・・・それ自体がマスコミによるマインドコントロール状態にあると言っていいと思います。
少し本題からズレますが、今日の夕刊に「サイバー攻撃、ロシアの関与認める」という小見出しがありました。
これを読んだ人はどう思うでしょう。
通常、こういう書き方をした場合、犯人が自供したかの様な印象を持つのではないでしょうか。
つまり、この場合も、「ロシアによるサイバー攻撃をロシアサイドの人が認めた」という印象を持ちやすいと思います。
しかし実際には、米国の次期大統領が、「ロシアや中国が関係したものと思われる」という単なる米国サイドの憶測によるものでした。
それに、仮にそういう事実があったとしても、逆に米国は同様なサイバー攻撃はしていないのかという疑問を持つべきでしょう。
これがマスコミの本質なのです。