人間には社会性が無い
- カテゴリ:人生
- 2015/07/12 20:24:36
人間は社会性のある動物だと、なんとなく教育されてきた様な気がします。
特に、マスコミや心理学の領域では、強く強調されてきました。
しかし、文明が生まれて数万年、何故未だに戦争や犯罪が絶えないのでしょう。
犯罪と言っても、法律上の犯罪では無く、人倫に対する犯罪のことです。
他者のものを強奪したり、肉体や心を傷つけ、命を奪う・・・そんな犯罪のことです。
そして、戦争をその様な人倫に対する犯罪と切り離して考えること自体、極めて異常なことだと思います。
戦争に行き、自分の命が誰かに奪われるかもしれないし、生還したとしても誰かの命を奪うことになるかもしれない。
いずれも、人倫に対する犯罪と言えるでしょう。
そんなことを考えていた時、放送大学の人類学の講義で、「人間には社会性はありません」という話を聴き、目が覚める様な気持ちになりました。
人間には社会性が無い・・・・なるほど、それなら現在人間社会で起きていることが説明できます。
考えてみれば、人類つまりホモ・サピエンスが類人猿から進化して数十万年、そんな短時間で次の進化が起きるとは思えません。
つまり、人間はボノボやチンパンジーと言った類人猿と大差ない本質を持っていると考えられます。
もし地球上に人類が十万人程度しかいなければ、恐らく社会は形成されなかったでしょう。
そして、個々のテリトリーを守り、そこには十分な果実が在り、小動物などの食糧も十分で、恐らく「働く」という概念は無かったと思います。
他の個体と出会うのは、繁殖相手を選ぶ時くらいだったでしょう。
類人猿のボノボにも見られる様に、メスは疑似発情期を獲得していて、特定のオスを引き留めておく能力が人類にもあります。
これは、他のチンパンジーなどの類人猿には見られないことです。
もし、この疑似発情期が無ければ、オスは他の発情期にあるメスを求め続けなければなりません。
何故なら、メスの発情期は受精可能時期に限られ、月に数日程度に限られ、そして発情期以外のメスは交尾をすることが不可能な状況になっているからです。
つまり、疑似発情期を獲得したことで、本物の発情期以外にも交尾可能となり、特定のオスを引き留めておくことが可能となりました。
それは、家族社会という社会単位を形成することが可能となったことを意味しています。
哺乳類は、胎内で子供を育て、産まれた後も子供を育てる様になり、母子社会という社会単位を形成することが可能となりました。
家族社会は、脊椎動物において獲得した二つ目の社会であり、いずれも遺伝学的変化に基づいた進化を伴っています。
そして、いずれもメスの進化であったことが興味深いところです。
しかし、それ以上の進化は人類は起きていませんし、その時間もありませんでした。
つまり人類には、家族社会より大きな社会、例えば集落、村などの社会を形成する能力は持ち合わせていません。
まして、市や県、国などの社会を形成する進化はしていないのです。
それでは何故、人類は社会を作り、その中で生きているのでしょう。
それは、地球上に人類が増えすぎた為です。
個々の家族が十分に満足できる自然の食糧を得るテリトリーを確保することが出来なくなったのです。
また、家族以外の他者と頻繁に出会わない訳にはいかなくなった為です。
「~なった為」と書きましたが、実際にはその様な自然状態は、人類発祥当時から無かったのかもしれません。
ホモ・サピエンス発祥した時には、既に他のネアンデルタール人などの類人猿との競争状態にあったと考えられます。
結果的に、ホモ・サピエンスはネアンデルタール人に勝利し、絶滅させ、ホモ・サピエンスの世界となりました。
つまり、人類が発祥し、類人猿間闘争に勝利した時には、既になんらかの社会を形成していたものと思われます。
しかし、本質的には、その様な大きな集落社会を形成する進化はしておらず、社会性を獲得してはいません。
つまり、原初状態の個々の家族社会によって、自然の食糧を確保できるテリトリーを持つ世界というのは、人間の本質的な性質であり、実際には存在しない状態でした。
増えすぎた人間が食糧を確保するには、まず集落単位で生活し、共同で狩りを行ったり、木の実を採集したりして、効率を高める必要があったのだと思います。
そして、集落で生活することは、男女間の出会いも効率が良くなり、更に人口が増えたと考えられます。
そうなると、再び食糧不足になったことでしょう。
集落のテリトリーを広げようとして、隣の集落との争いも起きたことでしょう。
そんな時、人為的に食糧を確保する方法を発見しました。
それは、稲作などの農業、そして畜産などです。
この発見により、集落の食糧を確保することが可能となりました。
しかし、そのこと自体が爆発的な人口増加をもたらしました。
そして、またまた集落の食糧不足に陥りました。
集落内で、食糧の強奪も起きたことでしょうし、他の集落の食糧を強奪することもあったでしょう。
そして、集落間の争いも激化し、集落同士で同盟が結ばれたり、合併したりして、より大きな集落社会が出来てきたことでしょう。
この様に、人間社会はその繁殖能力と食糧との関係のバランスを崩しながら、なし崩し的に社会が形成されてきたのです。
それらの大きな集落社会の中で円滑に生きていく為には、集落内の取り決め、つまり法律の様なものができ、集落の取りまとめ役である王などが必要となり、そこには権力が存在し、社会の階層構造が出来上がってきたのです。
この様ななし崩し的に発生した社会は、現在でも極めて不完全なものですが、それでも無いよりはマシであり、もし社会が無く、原初的な人間のままだったとしたら、悲惨な状態になったことでしょう。
そもそも「働く」という概念は、集落社会以降の話です。
17世紀のイギリスの哲学者ホップスは、その様な原初状態を考え、その悲惨な状況から脱する方法として、社会、そして政治哲学を考えました。
難解な思想で知られる18世紀のドイツの哲学者カントも、同様な想定をしていたと思われます。
カントは「自分の欲求から生じた自由は、本当の自由では無く、欲求に支配された行動だ」ということです。
「自分の欲求から生じる」というのは、つまり人間の本質からの要求ということであり、もしその要求に従うのであれば、人類は悲惨な原初状態に戻ってしまうでしょう。
つまり、人間は社会性のある動物なのでは無く、悲惨な状況から免れる為に、社会を形成しなければならなくなった動物なのです。
だからこそ、現在の社会も不完全なものであり、より良い社会を目指す努力を怠ってはならないのです。
それはつまり、現在の社会を単に受け入れることでは無く、より良い社会を目指して変革をし続けなければならないのだと思います。





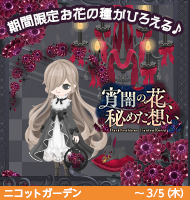




















とても面白い点に気がつかれていると思います。
老人が増え・・・これは、人間界では比例的にお爺さん、お婆さんが増えていることを意味しています。
これは後日書くつもりですが・・・
お爺さん、お婆さんを、「孫がいて、面倒を見ることもある人たち」と定義することが出来ます。
京都大学霊長類研究所の教授によると、この様なお爺さん、お婆さんが存在するのは、人間やオラウータン、ゴリラ、チンパンジーなどのヒト科の霊長類の中で人間だけだそうです。
そう考えると、その様なお爺さん、お婆さんの存在こそ、人間らしいところであり、人間による文明の発展もそこに原点があるのかもしれません。
人々は助け合い 社会性が一見あるように思えても
現実に起こっている戦争をはじめ残虐な殺し合いを見れば
社会性があるとは言い切れないし むしろないといわれた方が
納得いくような気がします
人類は文明を得て 長生きにもなり子供は減ったけれど その分
老人が長生きになり 色々な足りない現象をもたらしている感じです
自然界では 淘汰されていくものでも人類は少しでも長生きを祝って
老人社会に なり変わっていこうとしています
社会性は おっしゃるように 学びお互いを思いやり努力して
みんなが幸せに生きていくことができる社会を維持していくことでしか
存続していかないような現状ですね
毎日の暗いニュースを見ながら どんどん荒廃していく社会を
ただ見つめるしかない自分を 悲しいと思います
でもね~本音を言うと もう十分生きた感じがします。。
ただ 親をおくり 相棒をおくり・・それからでないと きっとお迎えはこないと
思って居ますから・・すこしでも自分の周りが穏やかな感じで過ごしていけますようにって
それだけを祈りながら毎日 少しでも自分が元気でいて 周りに迷惑かけないようにと
思うばかりです。 あたるさん お料理 慣れたかしらね~?
急に暑くなって 体がついていかないよねぇ~お互い体を大事にして 心元気に参りましょう(^^)/