今日のMY釣り堀
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2014/12/01 11:53:48
ニコット釣り で遊びました。
- 売った魚
- +23
釣った魚
- メダカ
- 3匹
- 3.90cm
- アメリカザリガニ
- 2匹
- 7.25cm
- ニジマス
- 1匹
- 25.34cm
- カワセミマリモ
- 1匹
- 5.36cm
釣り場所はいつもと同じです(・_・)
逃げられた魚は、ザリガニ2、カワセミマリモ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最高裁判事の国民審査について昨晩書きましたが、続きです。
昨日は眠かったので、信任、不信任という書き方をしましたが、正式には…
「×」をつけた場合は…罷免を可とする票
何もつけなかった場合は…罷免を可としない票
というそうです。(出典:ウィキペディア)
つまり、何もつけなかった場合は、「罷免を可としない」…罷免することを許さない判事であるという積極的に信任した意味を持ちます。
一方、他のマーク、「○」、「△」、「☆」、「□」、ハートなどの「×」以外の文字を書いた場合は無効となります。
さて、最高裁の判事は15人いますが、全員が国民審査を受ける訳ではありません。
また、投票用紙の名前順はくじ引きで決められ、順番に意味を持ちません。
そして、何より問題なのが…
この国民審査を受けるのは、就任後の初めての衆議院選挙であり、一度罷免を免れると次の国民審査は10年後となります。
しかし、実際に最高裁判事に就任するのは、60歳以上の場合がほとんどで(出典:ウィキペディア)、70歳で定年となる為、事実上最初の衆議院選挙での国民審査を受ければ、もう国民審査を受ける必要は無くなります。
衆議院選挙は最長でも4年以内に行われますから、就任後の4年間に目立った裁定を下さなければ、民衆も敢えて「×」をつけようとは思わないでしょう。
しかも、特別な場合を除いて、新聞やテレビで報道される裁判の記事に、裁判長の氏名が公表されることはごく希にあっても、個々の判事の氏名については見たことがありません。
裁判長となるのは、だいたいの場合、国民審査を終え、その後国民審査を受ける前に退官する判事がほとんどですから、どの様な裁定をしても民衆からの監視を免れてしまいます。
私達が知りたいのは、「最高裁判事になってどの様な判断をしたか」ということでは無いでしょうか。
衆議院選挙時の国民審査の前には、審査される各判事の経歴が紹介されますが、それぞれの判事が、最高裁でどの様な判断をしたか…については見たことがありません。
それに、法曹界出身なら、まだどの様な裁判に関わって、どの様なことをしたかについて調べることも出来るでしょうが、最高裁判事の中には官僚や大学教授出身の人達が多く混ざっています。
その様な人達については、まさに「最高裁判事となってどの様な判断をしたか」ということしか判断の基準がありません。
ただ、やはり問題となるのは、裁判に最も強い影響力を持つ裁判長が、もう国民審査を受ける事はなく、やりたい放題ということでは無いでしょうか。
そう考えた時、新任の判事より、むしろ裁判長経験者を国民審査するべきでは無いでしょうか。
そして、本来は、毎回の国民審査において、全員を審査するべきでしょう。
「裁判所には独自の判断があるべきである」と言いますが、最高裁判事を任命するのは内閣であり、極めて政治色の強い人事となっています。
そして、今回の衆議院選挙と同時に国民審査されるのは5人です。
その中には、第二次安倍内閣で内閣法制局長官を勉めた人が入っています。
このイメージからでは、「集団的自衛権の行使は、憲法解釈で対応できる」と言った人の様に見えますが、実際には「集団的自衛権の行使には、憲法改正が必要だ」と言った人でした。
つまり、憲法解釈でなんとでも出来てしまう様な判断をしたのは、この人ではありません。
この様に、大まかな経歴だけでは分からない部分が多々あります。
最初に書いた様に、最高裁の国民審査において何も書かずに投票箱に入れてしまうことは、積極的に信任したという意志表示になります。
もし、面倒くさい、よく分からないと思われたら、誰のところでも良いので、「×」を付ける位置にクマさんのマークとか描いて、無効票としたらいかがでしょうか。







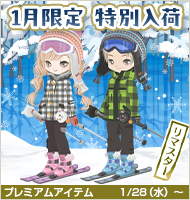


















うんうん、強い意志を持って投票する人達の投票を大事にしてあげましょう(^^)
最後の提案。。とてもいい感じです
私は、ニコちゃんマークでも書いておきます(^-^)/
うんうん、そう「×」を付ける行為そのものが、「何も知らないのに×をつけて罷免になってもいいのか?」という罪悪感を感じさせます。
それこそが罠と言えるでしょう。
仮に、「最高裁判事として信任する人に○をつけなさい」というものだったら、きっと罷免になった判事もいた筈だし、もっと自分たちの実績をアピールすることでしょう。
本当は、「罷免して欲しい人には×、信任する人人には○を付けなさい」という質問の方が公正な審査が行われるのだと思います。
そして、×は-1点、○は+1点、それ以外は0点として、集計結果がマイナスになった人は罷免という形が良いでしょう。
もし、よく分からなくて何も付けられないという場合は、棄権すれば良いと思います。
本文にも書きましたが、投票用紙を受け取らなくても、戻してもいいし、「×」以外の何かを書いて無効票としても良いでしょう。
今のままの状態では、例えば仮に、ある判事について…
A.「罷免したいと思っている」が100人…「×」印
B.「罷免したく無いと思っている」が10人…無印
C.「よく分からない」が9890人…無印
…となり、結果として…
「×」印(罷免を可)が100票
無印(罷免不可)が9900票
で、本来罷免したいと思っている人は、罷免したくないと思っている人より10倍多かったとしても…
投票結果としては、罷免したい票が、罷免したく無い票の100分の一となってしまいます。
これでは、民衆の意志が投票結果に表れておらず、民主主義とは言えません。
従って最低限、投票する前には、ウィキペディアの「最高裁判所裁判官国民審査」に未審査の最高裁判事の名前が分かり、そして一人一人にウィキペディア内のリンクがはってありますので、その内容を見て決めるべきだと思います。
もし、面倒で関わり合いになりたくなければ、「×」をつけるべきところに、悪戯書きでもして無効票にしてしまえば、少なくともC.の票が減って、より公正な審査ができると思います。
今回は5人ですので、5マスあると思います。
その5マスに、例えば…「あたるだよ」と書いたり、「にこたうん」と書いたりすれば、楽しく無効票にできます(^◇^;)
誰にもxを付けた事がありません
それこそ 無罪の人を罪に陥れる気がして^^;
だけど最近の 殺人容疑で1審2審が有罪だったのに最高裁で無罪になって出て来た直後
殺人を犯したオヤジ?の事件を見た時
ちゃんとそのオヤジの危険性を見抜けず 社会に復帰させてしまった最高裁の裁判長は
判決を間違ったと言わざるおえないと 今度は投票でxを付けても良いような気がしました
なのに 名前が公表されない為 どの人か分からないじゃないかあww
ねえ? あたるくん?? ヾ(*`Д´*)ノ" ギャーピー ギャーピーwww!!
晩秋の雨は、なんとなく身体を動かすのが嫌になりますよね~(__;)
ん~こちらは、日中には既に寒い…という状態です(^◇^;)
風邪は万病の元…つまり免疫力が下がっている証拠ですから、気をつけましょう(^^)
私も同様な感じなのですが、逆に全員に「×」を付けていました。
しかし、今はウィキペディアの「最高裁判所裁判官国民審査」の項目に、現在の未審査の判事が分かる様になっていて、それぞれ多少詳しくウィキペディアで調べられるので、それで調べて投票しています。
罷免を免れているのは、投票用紙を貰った私達が、誰が何をした人か分からないというのがあります。
ただ、もっと問題なのは、本文にも書きましたが、裁判長の実績のあるほとんどの判事が、もはや審査を受けない…というところにあるのだと思います。
うんうん、分からなかったら、顔でも描いてみましょう(^^)
レア魚GETおめでとうございます♪
私の方も朝から雨が降っていて、モチベーションが下がりますよぅ@@
特に今日は夕方から寒くなるみたいですね><
お互い、風邪などには気をつけましょうね^^
私も・・・罷免をする、しないの判断材料が
なくて・・・困ってしまい、結局は誰も
罷免にしたことはありません。
なんか、国民に罷免を委ねているのも
形だけって気がしてなりません。
そうですね^^今度は(・・?マークでも
書いてみましょうか^^