今日のMY釣り堀
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2014/11/22 11:56:50
ニコット釣り で遊びました。
- 売った魚
- +28
釣った魚
- メダカ
- 1匹
- 3.43cm
- アメリカザリガニ
- 2匹
- 7.67cm
- キンギョ(黒)
- 1匹
- 13.91cm
- アブラハヤ
- 1匹
- 9.74cm
- ブルーギル
- 1匹
- 16.74cm
- ヘラブナ
- 1匹
- 29.09cm
釣り場所はいつもと同じです(・_・)
逃げられた魚は、メダカ、カワムツ、長靴。
まぁ、普段よりはいろんな魚が釣れたと思います(^^)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
生物としての人間に到る進化として、重要なポイントがいくつかあります。
0.ウィルス様の何か
通常、ウィルスは子孫を残す為に重要な遺伝子や成分が十分ではありません。
従って、他の生物の細胞にとりついて、その細胞内でつくられたものや、遺伝子を利用して自分に必要な物質を揃えます。
つまり、ウィルスは細胞が無ければ子孫を残すことができず、単細胞生物が発生した後に発生したものと考えられています。
しかし、考えようによっては、例えば原始地球における水たまりの中に、多彩なウィルスがいて、互いに互いの作ったものを利用しあっていたと仮定すると、その大きな一個の水たまりという環境の中で、あたかもそれが一個の細胞であるかの様に発生していた可能性もあるのでは無いかと思っています。
1.原核細胞生物
最初の生物です。
恐らく、後の真核細胞の細胞内小器官となる、細胞核の前身、ミトコンドリアの前身、葉緑体の前身の様なものであったと思います。
原始地球に限らず、生物が居ない状態での惑星には、酸素がほとんど無く、二酸化炭素、窒素ガスなどが多い大気であったと思われます。
生物が発生したと思われる原始海水中には、生物が居なかったので糖分もほとんど無かったものと思われます。
その様な状態で、糖分を酸素によって酸化したエネルギーの利用を得意とするミトコンドリアの前身は、恐らく発生出来なかったものと思います。
つまり、先に発生したのは、二酸化炭素と水から太陽の光のエネルギーを利用して糖分と酸素を発生させることが出来る光合成生物、つまり葉緑体の前身だったと思います。
二酸化炭素が多い原始大気を持っていた地球では、暖かく、葉緑体の前身が繁殖するには最適な状況であり、恐らく大発生していたことが予想されます。
そして、原始海水中には豊富な糖分、原始大気中には酸素ガスが急上昇していたのだろうと思います。
しかし、酸素濃度が高くなり、二酸化炭素濃度が薄くなってきた原始大気の中で、徐々に地球も冷え、葉緑体の前身も増えすぎた数を減らしていったのかもしれません。
そして酸素は、強い酸化力という毒性を持つ物質でもあります。
そんな時、ミトコンドリアの前身となる生物が出現し、原始大気中の有り余る糖分と、原始大気中の酸素ガスを利用して発生したのだと思います。
結果として、葉緑体の前身となる生物とミトコンドリアの前身となる生物がバランスをとりながら、海水中で繁栄していたのでしょう。
一方、海底では、海底火山からの温泉、つまり熱水噴出口があり、そこからは硫化水素が大量に吹き出していたものと思われます。
そして、その硫化水素のエネルギーを利用して様々な生物材料、有機物を合成していた化学合成細菌が繁殖していたのだと思います。
化学合成によるエネルギーの利用は、恐らく光合成によるものや、ミトコンドリアの呼吸系によるものよりも、かなり効率が悪いものだったと思われます。
しかし、そのことこそが、その後の真核細胞生物が出来る土壌になったのでは無いかと思います。
2.真核細胞生物
葉緑体の前身は太陽光からエネルギーを作り出すのに優れ、ミトコンドリアの前身は作り出されたエネルギーを使うのに優れていました。
そんな時、直径数キロの隕石…というか、もはや小惑星と言っても良いものが地球に衝突したらしいです。
その衝突は核融合反応などを引き起こし、莫大な熱を伴った大爆発となり、地球全体を深さ10kmまでをはぎ取って、焼き尽くし、空中にばらまいたそうです。
恐らく、それまで繁栄していた葉緑体やミトコンドリアの前身となる生物も、ほとんどが死滅したものと思います。
空中には大量の粉塵が舞い上がっていて、太陽光は届かず、地球は冷却され、地球全体が大氷河期となる全球凍結と呼ばれる状態になったそうです。
僅かに残った葉緑体の前身も、太陽光が届かないので、更に大減少し、ミトコンドリアも糖分の不足や冷却状態によってほとんどが更に減少したのでしょう。
しかし、ほんの僅かですが、海底に逃げ込んだ葉緑体やミトコンドリアの前身もいたのだと思います。
海底にいた化学合成細菌は、エネルギー効率が悪いのですが、隕石の衝撃からは守られ、地上の冷却も、太陽光も無関係に熱水噴出口からの熱と化学エネルギーを利用して生き残っていたと考えられます。
そして、衝突の悲劇から逃れてきた葉緑体やミトコンドリアの前身は、その化学合成細菌の細胞内に逃げ込んだ…つまり入り込んで共生したのだろうと思います。
硫化水素などの化学物質を利用できないので、共生できなかった、つまり取り込んで貰えなかった葉緑体やミトコンドリアの前身は、死滅したものと思います。
エネルギーを使う効率に優れていたミトコンドリアの前身は、その入り込んだ細胞内でも絶大な威力を発揮し、ミトコンドリアを取り込んだものは、そうで無かったものより有利に生き抜くことが出来る様になったのだと思います。
一方、葉緑体の前身を取り込んだものは、特に有利にはならず、むしろエネルギーを使われているだけで、いわゆる寄生状態で、不利になったと思います。
ここで、次の様に大きく分類されると思います。
a.ミトコンドリアと葉緑体の前身を両方取り込んだもの。
b.ミトコンドリアの前身のみを取り込んだもの。
c.葉緑体の前身のみを取り込んだもの。
d.何も取り込まなかったもの。
そして、太陽光の届かない海底での有利性は、次の様な物であったと思います。
a = b > d > c
そして、葉緑体の前身のみを取り込んだcのグループは、絶滅したのかもしれません。
そして、どの段階か分かりませんが、細胞核が出来上がりました。
それは、取り込まれたミトコンドリアや葉緑体の前身をベースとしたものなのか、他の化学合成細菌を取り込んでベースとしたものかは分かりませんが、それは非常に効率が良いものだったのでしょう。
更に、葉緑体やミトコンドリアの前身が持っていた遺伝子は、共生まは寄生している化学合成細菌に養われる様になると、機能分化し、それ以外の遺伝子は捨てて、消滅したか、化学合成細菌の遺伝子に組み込まれていったのでしょう。
結果として、細胞核やミトコンドリア、そしてあるものは葉緑体と言った細胞小器官を持った真核細胞生物が誕生しました。
やがて地上に舞い上がった粉塵も治まり、太陽光が差し始め、火山の噴火によって熱や二酸化炭素が放出される様になり、再び太陽光が差す穏やかな気候となったのでしょう。
海底で潜み、地上の混乱をやり過ごしていた様々な真核細胞生物は、再び海の表面に浮上し、それまでお荷物でしか無かった葉緑体を持っている細胞は、光合成を始め、より有利に生きることが出来たのだと思います。
葉緑体を取り込まなかった生物は、やがて栄養をたっぷり持っている光合成生物を取り込み、共生や寄生させるのでは無く、過酸化物で破壊し、栄養のみを取り込む様になったものが出てきて、運動能力を獲得した可能性もあります。
(文字数が限界に近づいてきましたので、今回はここまで…)





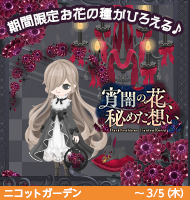




















天文学者によると、単細胞の初期の生物が発生するのは、必然的に近いものだそうです。
つまり、そういう環境の星であれば発生するものだそうです。
しかし、地球付近から観測可能な範囲には、まだ生物の痕跡は発見されていません。
宇宙誕生から約135億年、その間に消滅した星もあれば、出来上がったばかりの星もあるでしょう。
その中で、38億年にも渡って生物が存続してきた地球は、まさに軌跡の惑星と言えるでしょう。
地球誕生から6億年後には、生物が発生していたと考えられてます。
そして、恐らくすぐに光合成を行う原核細胞生物が発生したと思われます。
何故なら、生物発生の最適な場所は、恐らく海辺の水たまりであっただろうと思われ、つまり海水面近くから発生したと思われるからです。
しかし、この頃はまだ磁場が安定しておらず、また酸素も無かった為、太陽からの太陽風(素粒子や電子の風)や放射線や紫外線が強く、生物が生息するには過酷な条件だったと思います。
この段階で、生物が消滅してしまった惑星も少なく無いと思います。
光合成を行い、酸素を放出する生物が出現しなかったとしたら、海底の熱水噴出口付近に生息する化学合成細菌しかいない星ということにもなります。
金星の様に、超高温で、海水も蒸発し、生物が生き残れなかったかもしれません。
つまり、この光合成を行う原核細胞生物(ミトコンドリアの前身)が地球上に出現したのは、まさに奇跡と言えるでしょう。
その結果、生物が大増殖し、多様性が増大したことにより、小惑星の大衝突、そして大氷河期という生物絶滅の危機を乗り越えることができ、真核細胞生物を発生させたというのも奇跡と言えるでしょう。
そして、今後書いていくことですが、コラーゲンというタンパク質の誕生によって、単細胞同士が癒着し、群体生物となり、それが細胞同士が連絡し合う多細胞生物へ進化することが出来たことも奇跡と言えるでしょう。
細胞同士は連絡し合ったことにより、役割を分担(機能分化)する様になり、単細胞でいるよりも有利に生き抜くことが出来る様になった多細胞生物は、やがて海水を体内に封じこめ、陸上へも進出しました
それは、まるで細胞同士が社会を形成し、都市という文化を創り上げた様にも見えます。
今回の話は、8/13に書いた 「雑記 「生物」」の続きだったりします。
3ヶ月以上空けた続き…(;^_^A アセアセ…
宇宙誕生から人間までを書こうとしているのですが、だいたい途中で文字数制限になり、また気力も尽きてしまって…(__;)
宇宙の歴史、地球の歴史、生物の歴史、そして人間の歴史、穏やかな時もあれば、文字通り天地がひっくり返る様なこともあり、今になって歴史を振り返ると、まるで一本の意図した糸(シャレ…(__;))があったかの様に見えます。
若い時、皆、どの道に進もうかと悩みます。
しかし、そんな道など無いのです。
生きて、生きて、生きて…そして、ある程度何かになった時、過去を…後ろを…振り返ると、そこに道があったかの様に思えるのです。
(↑この言葉も、大学時代の哲学の先生のパクリ(__;))
今の地球は、とても穏やかな時です。
例え、地震や津波があったとしても…
福島の原発事故の時、「想定外」という言葉を頻繁に聴きました。
でも…人間に想定できるほど、地球は、宇宙は、甘くは無いのです。
将来、地球は太陽の赤色巨星化に伴って消滅するでしょう。
また、私達の天の川銀河系は、やがてアンドロメダ星雲と衝突し、一つの大きな銀河となるでしょう。
それでも生物は、この38億年の間、地球の大変動を乗り切り、私達人類まで辿り着いてくれました。
生物は確かに強い…ですが、それは固有の種が強いという訳でも、ある個体が強いという訳ではありません。
そして、機械が精巧なものほど環境に弱い様に、生物も高等になるほど環境に弱いものです。
精巧に作り上げられた身体を持つ私達人類、そしてそれぞれの人の身体、それを生かしてくれる環境を大事に子孫に引き継いでいきたいものです。
たった数十万年の歴史しか持たない人類が、原子力から出る放射能によって、生物全体を危機に落とし入れているなどということは、考えたくも無い大罪と言えるのでは無いでしょうか
あたるさんの一連のblogは なんだかとても新鮮に感じます
たった一つの細胞から 本当に奇跡的に進化してきて今があるのですね~
単細胞・・なんて悪口のように言われるけれど われわれよりもたくましく
自然に順応してきたのですね・・そして ものすごい能力を持っているものもあるとか
人間が計り知れない自然の営みが脈々と受けつがれてきたことを思う時・・
地球人として この星を 守らなければいけない・・本来ならば平和で美しい星なんですものね♪
何やら、壮大なドラマのようですね^^
(文字数ギリギリって、そういうとこに
妙に感銘したり・・・)
葉緑体というと植物の光合成しか想像できないのですが。
・・・強いですよね・・・太陽の光で生きられると
いうのは・・・