勉強、学び、探求
- カテゴリ:30代以上
- 2014/09/24 12:11:44
今朝、放送大学を観ていて、ふと思ったことです。
常々、「勉強」という言葉が嫌いだったのですが、いろんなところでコメントにも書いていますが、勉強とは、「勉め、強いる」、つまり「(自分ではやりたいとは思わないことを)、やる様に強制される」という意味があります。
しかし、かと言って、不要という訳ではありません。
例えば幼稚園や小学校で教えられる、最低限の知識やテクニック、いわゆる「読み書きそろばん(計算)」や、社会と関わる為に最低限必要なマナーなどは、例え嫌だったとしても、覚えておいた方が生きやすく、メリットがあると思います。
つまり、小学校でやるのは、勉強が主たる目的だと思います。
次に、放送大学でよく使われる「学び」はどうでしょう。
「学ぶ」という言葉は、「真似る」と同じ語源だそうで、つまり先人の生き様(先生)を真似ることです。
中学生や高校生は、基礎的なことは身につけていますが、高度化した社会を生きるにはまだ知識や技術が足りません。
中学校までが義務教育になっていますので、基本的には中学校を卒業することで、この高度化した社会を生きていける様にならなければなりません。
その知識は、何か仕事をする為のものというより、普段生活していく上で必要なものと言えるでしょう。
従って、師匠から直接一から教えられる職人的な職業につくのであれば、この段階でも十分と終えます。
しかし、会社などの企業で働くということであれば、企業においては師匠の様に一から教えることは出来ませんし、また企業一般の知識や技量も多いので、高等学校に行く必要があります。
また、大学においても同様で、研究職を目指すのであれば、高等学校に行く必要があるでほう。
しかし、中学校や高等学校の様な学びの場所は、先人の生き方(先生)を真似る時なので、教える側も、私情を挟まず、教科の内容も公平かつ客観的に教えなければなりません。
教える側というのは、先生だけでは無く、文部科学省や教育委員会も、ご両親も注意する必要があるでしょう。
では、大学とは何をするところなのでしょう。
大学とは、真理や真実を探求する場所だと私は思います。
つまり、自ら探求する場所であり、講義の内容も、一つの事実として受け止め、参考にしながら、自ら新しい事実、新しい概念を考えていく場所です。
その考える力を企業が評価し、利用することはあっても、企業の為の予備校という訳では決してありません。
もし、企業の為の予備校が必要なのであれば、その為の専門学校を作り、そちらで「学ばせれば」済む話です。
ハーバード大学のサンデル教授の講義がテレビで放映されましたし、ビデオも出ていますが、それを観れば本来の大学の在るべき姿が分かると思います。
学生は、その講義のテーマの為の知識を、講義の前に予め得て、自分なりに考えています。
講義では、サンデル教授がテーマを提示し、それに沿った議論を学生同士で行わせ、議論が発展的に行われる様に、議論を補完したり、コントロールしているにすぎません。
そして、哲学という特性もあるのですが、教授は正解も、自分の考えも言いません。
つまり、教える場所では無く、探求の為の場所なのです。
それは、理科系、つまり科学においても同様なことが言えます。
先人が数多くの法則や観察結果を提示していますが、決してそれが全ての事実では無いし、場合によっては一側面しか捕らえておらず、概ね間違っているかもしれません。
ただ、大学においては、講師の人達も、自分の意見を付け加えても良いと思います。
学生側が、自分で考え、探求することが分かっていれば、講師の意見や知見も一つの考え方として受け取ることができると思います。
そう考えると、放送大学が「学び」という言葉を使っているのは、大学として不適切であるとも言えます。
何故、放送大学が「学び」という言葉を使うのか?
それは恐らく、放送大学という放送メディアを利用した大学は、ほとんど一方通行であり、大学として十分な探求の場とは言えないからかもしれません。
しかし、そうであっても、学生側に探求する精神が在れば、放送大学の講義を手がかりとして、自ら探求することはできるでしょう。
つまり、放送大学において良い講義とは、学生が自ら探求する手がかりや意欲を与えられる様な講義のことで、それは既に「学び」の域を超えたものとなります。
実際、放送大学では、そういう良い講義もありますし、視聴する価値の無い講義もあります。
放送大学には、図書館が高度に整備されていて、また面接授業というのも何回かありますので、学生が探求する条件は整っている様です。
最近、政府は、「大学は社会人の為の予備校」の様なことを恥ずかしげも無く公言していたり、国立大学から人文科学系を事実上排除し、技術を習得する為の理科系だけ残し、まるで専門学校にしたい様な考え方を示しています。
なんと、未熟で、恥ずかしい考え方でしょう。
それは、「真理や真実を考える国民」がいては、政府が困ると言っている様です。
それが、政府の意向か、後ろにいるアメリカの意向かは分かりませんが…





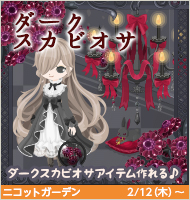







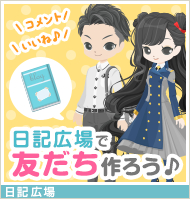












おそらく、政治家も官僚も、元財閥系企業幹部も、自分の一族だけは逃げ出す準備があるのでしょう(-_-メ)
そして、おそらく、自分の子や孫には、国民には安全と言っている、放射能汚染の疑いのある食品は食べさせていないと思います。
私の住んでいる街は、住宅街としては結構いい場所なのですが、原発事故の数ヶ月後の5月とか6月に、高級マンションで数多くの引越作業を見ました。
どう考えても、その時期での大量引越はおかしいですよね。
母親は、どうやら、思っていたより大変な事態で、今日は一日走り回って、ちょと疲れてしまいました(__;)
自分の歯医者の予約もキャンセルしてしまいました(__;)
子供たちに「先送りしたツケ」を払わせること・・・
政治家には子供がいないのか、と疑ってしまいます。
それとも・・・いざとなれば家族で逃げる場所を用意
してあるのでしょうか・・・・(疑心暗鬼)
お母さまのこと大変ですね。
どうか、お大事にしてあげて下さい。
「悲観より楽観がいい」とか「時が解決してくれる」とか言われますし、時には私も言いますが…
楽観的に経済成長を過ごし、時間が解決してくれると放っておいたら、今日の事態に陥ってしまいました。
時が解決してくれるどころか、どんどん最悪な状態になって、ついに楽観視出来ないところまできました。
そう考えると、このまま、これからの世代に押しつけてしまうのは、あまりにも無責任な気がして、せめてブログに書くことくらいはしようと思っています。
食糧自給率20%ということは、仮に食糧輸入、食糧援助が無ければ、食糧供給率20%ということであり、そこには地獄絵図が見えてしまいます。
それでも、農業従事者が増えていけば、それだけ自給率が上がり、危機も緩和されることでしょう。
ただ、問題なのが、狂った政治と、狂った市場経済によって、自ら供給するもの以外が馬鹿高いということかもしれません。
それらは、遠からず破滅するかもしれませんが、同じ日本円という貨幣を使用していれば、否応なく巻き込まれてしまうことになるでしょう。
人間は一人では生きていけないので、仲間で集まり、その仲間の間で生活必需品を相互に補完しあう必要があるかもしれません。
物々交換、もしくはそのグループだけで通用する様な代替通貨で、グループ内の独自の経済を成立しておくことが最も有効だろうと思います。
ただ、これによって所得税は免れますが、固定資産税などはやはり日本円で支払わなければならず、簡単にはいきませんが…
なります。
せめて子供には生き抜く力を与えたいものです。
私は「農業やりなさい」と言ってます。
ただ・・・もしもの時には・・・国に食糧を
取り上げられるかも・・・と
そこまで考えているのですが。
美術関係…私は青山昌文先生の芸術論関係が好きです(*^。^*)
芸術のことなんて、全く分からない私でも、青山先生の熱意と情熱が伝わってきて、いつも面白く視ています。
ディドロについても興味を持ち始めています(^。^)
これについては、カテゴリ「30代以上」で2014/08/12に書いた「放送大学」をご参照下さいm(__)m
歴史…地中海の歴史、東アジアの歴史などなどたくさんありますが、どれも面白いですね(^。^)
地中海の覇権の争い、そこでのギリシャ・アテネ、ローマ帝国、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の争いなどなど、ヨーロッパのホットスポットという感じです。
ラジオ科目で哲学関係などとも合わせて聴くと、更に面白さが倍増する感じです。
あと、それらとは関係が無いのですが、天文学関連の講義も面白いです。
個人的に面白く無いのが、資格関係と語学の講義かな…興味無かったり、苦手だったり…(;^_^A アセアセ…
いえいえ、言葉は過ぎていません、むしろ優しいくらいでしょう(*^。^*)
テレビのニュースも、新聞記事も、事実しか伝えませんが、全ての事実を伝えている訳ではありません。
その辺は、ここまで流れてき近代史において、その時に報道され、自分が受け取った印象が、その後結局どうだったのかを総合的に考え、推理してみて下さい(^。^)
そんな紫水晶さんへのお勧め図書:「日本テレビとCIA」、「原発ホワイトアウト」
例えば、金権政治の代名詞となった田中角栄さん。
彼は中国との国交正常化を果たし、日本の土木事業を推進し、ロッキード事件によって起訴され、しばらくキングメーカーとして動いた後、推定無罪のままこの世を去りました…というのがマスコミの見方です。
しかし、彼の政治生活を語るには、もう少し遡ってみることが必要です。
彼は、佐藤栄作内閣の時、通産大臣(経済産業大臣)でした。
佐藤内閣は沖縄返還をしましたが、その返還条約に嘘があったことは既に明白となっています。
しかし、その直前にもう一つの重要な交渉がありました。
それは、日米繊維交渉というやつで、詳しくは書きませんが、沖縄返還を餌に、日本にとってとても屈辱的な結果を強いられました。
その担当の通産大臣だったのが田中角栄です。
その時、田中角栄はどう思ったでしょう?
涙が出るほど悔しい想いをしたかどうかは分かりませんが、少なくとも今の(その時の)ままでは米国の属国になってしまうという危機感を覚えたのでは無いでしょうか。
その後彼が考えたのは、
1.日本を経済的に豊かにすること
2.あまりにも米国寄りの外交を、少しでも中立に近い方に戻すこと
3.それらの目的の為に長く政治の主導権を握ること
だったのではないかと思います。
そしてそれらは実現され、それ故に米国から睨まれた。
そして目的を果たす為にお金を活用し、倫理的に問題はあったとしても、それはかなり効果的でした。
当時はまだ政治と金についてはまだ世間が見逃していてくれたこともあり、それ故に米国によって仕掛けられたのがロッキード事件でした。
同様に鈴木宗男、細川護煕についても考えてみると、米国の怖さが分かると思います。
私は正直、マスコミのことなど、信じていません。
テレビも「あったことしか伝えないニュース」しか
みませんし。報道番組はコメント側で、随分内容の印象が
変わってくるから・・・
常にコメントの裏を考えてしまって・・・
それは私が「推理小説好き」だから・・・TVドラマの
推理サスペンスものなんて、すぐに犯人が分かってしまうので
つまらなくなってみなくなりました。
とにかく、娘には「本を読め」と言ってます。
記憶する学習より、知識を得る事が大事だと、教えています。
色んな知識があれば、色んな考え方ができる。
バカみたいにマスコミのいうことを鵜呑みにしなくていい。
・・・ごめんなさい。言葉が過ぎました。
なかなかに、教育は難しいです。学校の教えと、自分の教えが
食い違う時には、特に・・・・
長々とごめんなさい。
「記憶力が良い」という頭の良さは、権力側としては問題が無いのですが、「真実や真理を探究」」されてしまうと、いい様にコントロール出来なくなるので、彼らにとって都合が悪いのだと思います。
「ゆとり教育」の目的は、サラリーマンの週休二日制に合わせて、国内旅行、海外旅行などの観光産業を盛り上げることであって、決して子供達の為では無かったと私は見ています。
詰め込み型の教育は、脳の活動の大部分を記憶と技術(計算技術など)に使用させ、「考える」という活動に脳を使わせない為のものだと思います。
前にも書きましたが、覚える必要も無いものまで、記憶させられていたのだと思います。
仮に、「ゆとり教育」で、記憶する量が減ったとしても、「考える」教育をしなければ、「真理や真実の探求」をする能力がほとんどの場合、身につかないのですから。
また、「ゆとり教育」が行われた時期は、既に日本人が考えることを放棄する工作が、ほぼ完璧と言えるほど成功していた時期でもあります。
それは、テレビのニュースや解説者などに思考を委ね、それを神の如く信じ、自らは考えることを辞めてしまった日本人となったことを意味します。
アメリカにとって、日本人が真理や真実を探求し、彼らのプロパガンダの手先であるテレビを信じず、彼らに支配されていることに気づき、その価値観に疑いを持つことは、日本の占領政策上、不都合なのです。
私たちは、テレビを観て育ってきたことで、知らず知らずのうちに、彼らに飼い慣らされてきたのです。
「日テレとCIA」という書籍では、アメリカが意図的に日本人の思考をコントロールしようとしていたことが、米国公文書館の資料をもとに書かれています。
その書籍では、「反共宣伝」の目的のみがクローズアップされていますが、今になって考えてみると、あらゆる面で、日本人の思考や思想が制限されていたことが分かります。
欧米に褒められると嬉しいという感情を持っていませんか?
私達の心の奥底に、欧米人に対しては尊敬し、アジア人に対しては見下げ、ロシア(ソ連)人に対しては敵意が、テレビや新聞を通じて、いつの間にか刷り込まれ、そして新聞を読むと分かりますが、今でも随時その真理戦術は実施されていることが分かります。
平民が頭がよくなるとお上は困る?
でも、日本には資源がないので技術で
外国に対抗してきたわけで・・・
ゆとり教育で、その技術力がなくなったから
また「詰め込み教育」の復活・・・
振り回される子供はかわいそうです。
ハーバード大学の白熱教室は、サンデル教授のだけでは無く、他にもいろいろ放映されていました。
サンデル教授のものほど刺激的では無いかもしれませんが、他の白熱教室も結構新たな視点が得られて面白かったです(*^。^*)
学生の頃も、やはり「勉強」、つまり強いられていた感が強く、興味を感じられなかったのだと思います。
恐らく、学校の時は、強いられているから、面白くなかったのだと思います。
本来、それまで分からなかったことが分かる様になる訳ですので、面白いものなのです。
それと、どうも成長する時期というのが、人によって異なっていて、しかもそれは身体、頭、心など、それぞれ違っている様です。
「知りたい」と思った時、それがチャンスだと思います。
「死ぬまで勉強」とよく言いますが、「勉強」という言葉が嫌いなので、「死ぬまで学びと探求」と言い換えましょう。
それは、成績を良くすることでは無く、知りたいこと、分からないこと、不思議なことが分かった喜びとして蓄えられ、豊かになっていくものだと思います(*^。^*)
サンデル教授の講義、面白いですよね。
どんな分野であれ、その分野にひいでた人の話を聞いたり、
するのはとても好きです^^
教えるのが上手な人は押し付けませんよね。
学生の頃はどうしてあんなに勉強に興味がなかったのかな。。。^^;
大人になって自分からやってみると意外と勉強も面白い!となったりしてw
w
もっと早くそうなっていれば 学校で優等生だったのに( ̄ω ̄;
時 すでに遅しw(TωT)ノ<チーン!