「何故、勉強をすると眠くなるの?」
- カテゴリ:30代以上
- 2014/09/04 10:30:21
とあるQ&Aのページで、表題の様な小学4年生の質問を見かけた。
そこでベストアンサーに選ばれていたのは、いろいろ書いてあったが要約すると以下の点であった。
①私は眠くならない
②眠くなるのは、勉強からの逃避であり、気合いが足りない
③頑張って、勉強に取り組みましょう
以上
つまり、眠くなるのは逃避行動の一環だというのだ。
しかし、それは、生物の原理に反している。
確かに、生物同士が出会った際、弱い方の生物が逃避の為に「寝たふり」をするものがいる。
しかし、あくまで「寝たふり」であり、本当に寝てしまっては、その種はあっという間に絶滅し、自然淘汰されてしまうだろう。
つまり、現存している自然淘汰を生き抜いてきた生物において、逃避の為に眠くなる様な生物はいないと言っていい。
それでは、何故この様な勘違いな回答をしているのか?
それは、回答者の根拠である「①私は眠くならない」という経験則に誤りがある。
そこには、こう書いてある。
「私は、聖書や神学書、哲学書をよく読むが、眠くなるどころか、興奮する」
なるほど、その回答者がそういう回答をしたのも納得である。
つまり、彼は形而上学的な考え方しか出来ないのだ。
※形而上とは、形あるものの上、形として目に見えないもの、つまり神などの観念的なもの。 これに相反する言葉として、形而下というのがあり、形あるものの下、形として見えるもの。
そういう訳の分からない回答に感心して納得したのも、小学生ならば仕方の無いところだろう。
では、どうして眠くなるのか、それはまだ完全に解明されていないが、いくつかの現象と推論から考えてみようと思う。
通常戦おうと思った時、危険なものにであった時、脳からアドレナリンというホルモンが放出され、脳も身体も活発な状態になり、息が荒くなり、汗も出る場合がある。
何故か?
身体の筋肉が緊張状態となる為、エネルギーを大量に消費する為、内呼吸が活発になるからである。 その為、肺での外呼吸も活発にしなければならない為、息が荒くなるのである。
※内呼吸とは、細胞内で糖分と酸素を使って、エネルギーを獲得する反応。 簡単に言えば、「糖+酸素 → 二酸化炭素+水+エネルギー」という一連の反応のこと。
※外呼吸とは、肺において、空気を取り込み、血液中に流れる赤血球の中のヘモグロビンというタンパク質にくっついている二酸化炭素を引き離し、代わりに酸素をくっつけること。 この赤血球の中のヘモグロビンにくっついた酸素が、血管を中を移動することにより、体内の各地の細胞の内呼吸で使用する酸素の元となる。
脳においても、戦う為に、運動や思考の為の神経細胞が活発になり、筋肉と同様に内呼吸が活発になり、外呼吸も活発になるのである。
そして、心臓というポンプが活発になり、血管も緊張状態になる為、血流が速くなり、外呼吸で得られた酸素が、各細胞に補充される効率も良くなる。
そして、内呼吸によってエネルギーを作り、そのエネルギーが使われると、必ずエネルギーの無駄が発生し、有効に使われなかったエネルギーは熱として発散することになる。
その熱を冷やす為に、汗をかくのである。
そして、もう一つの内呼吸に必要なエネルギー源である糖も、脂肪やグリコーゲンを分解して糖が補充されている(糖新生)のである。
それでは、どういう時に戦って、どういう時に逃げるのだろうか。
逃げるのは、相手が明らかに強く、自分が負けて傷つく可能性が高い場合だろう。
では、戦うのは、相手を倒せる、つまり勝てる可能性があり、その勝利によって満足感という快感を得る可能性がある場合だろう。
難解なことを理解するというのは、この戦いの勝利と同じ満足感を得ることができる。
恐らく、同じ原理ではないかと思う。
そう考えると、この勘違いしている回答者が、形而上学的な本を読んで興奮するのも分かるだろう。
彼は、恐らく神学や哲学といった形而上学的なことに詳しく、同様な形而上学的な本を理解することができるので、その難解なことを理解するという戦いの勝利を感じているので、それらの本を読むと興奮するのであろう。
きっと、量子力学や相対性理論の本を読めば眠くなるだろう(^◇^;)
では、何故、その小学生が勉強をすると眠くなるのか?
それは、その勉強の内容が、その子の理解を超えた能力を必要とする為、脳がフル回転していた為だろう。
脳がフル回転していれば、神経細胞が活発になっているのだから、内呼吸、外呼吸によって、息が荒く、汗をかき、興奮状態となる筈ではないか?
ところが、そうはならない。
どうも人間は、自分に危害が及ぶ様な状態にならないと、アドレナリンが放出されず、興奮状態にならない様だ。
神経細胞が活発になり、内呼吸が活発になっても、外呼吸が活発化されず(息が荒くならず)、鼓動が速くならなければ酸素供給能力も上がらず、脂肪やグリコーゲンからの糖分の補充も無ければ、脳内の神経細胞は酸素や糖が欠乏状態となり、二酸化炭素が過剰な状態となる。
これは、長期間続けば、脳の神経細胞が死滅することさえある危険な状態なのである。
従って、脳の神経細胞は、エネルギーバランスが崩れ、活動を低下せざるを得なくなる。
その結果、眠くなるのであろう。
ある意味、「脳が休みたがっている」、つまり「脳が保護の為に逃避している」という説明は正しくもあるかもしれないが、「気合い」では対処できないのである。
考えてみれば、他の生物も思考をするものもいるが、人間ほど思考力を高めた生物は未だ地上に存在していない。
つまり、思考において、最先端の生物なのである。
それ故に、思考するという精神活動に対して、未だ不完全な身体システムを持つ生物なのだろう。
こういうことは、人間が神に作られた完全な生命体と考えている神学者には理解出来ないだろうし、したくも無いだろう。
しかし、そういう勘違いを小学生にアドバイスするというのは危険な行為ではないだろうか。
何故なら、その小学生が、勉強に気合いを入れて、それでも眠くなったら、次にはカフェイン剤(ドラッグストアで売っている)などで眠気を押さえる様になり、それでも駄目なら覚醒剤などの違法薬物に興味を持ちかねないからである。
また、気合いで眠気を押さえるというのは、脳が必要性があって休もうとしているのを邪魔することになり、脳の神経細胞を危険に晒すことになるからである。
もし、「勉強してて眠くなったらどうしたらいいの?」と聞かれたら、次の様に対処するのが良いだろう。
①涼しい場所に行って、深呼吸をする。 軽く運動をするのも良いだろう。
これにより、体内に酸素を補給し、二酸化炭素を放出することができる。
軽い運動によって、少しアドレナリンを放出させ、若干興奮状態に持っていくことが出来る。
②甘い物を適量食べる。
これによって、糖分を補給することができる。
しかし、あまり大量に食べると、その糖分が満腹中枢を刺激し、満腹中枢が刺激されると眠くなるという反応が起こるからである。
また、ケーキなどの糖分とともに多量の脂肪分も含まれているものは避けた方がいいだろう。
脳が使用できるエネルギーは糖分だけであり、アドレナリンが活発に放出されて無い状態では脂肪分は使いようが無く、単に貯まっていくだけ、つまり太るだけである。





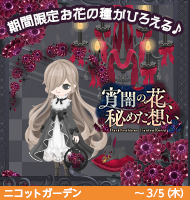







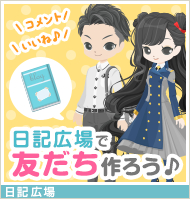












お褒め頂き、ありがとうございますm(__)m
ちなみに、私がいろいろ書いている様な妄想からの仮説をたて、一番重要なポイントを実験や調査によって確認し、同じ実験を何度かやって再現された時、その結果を他の人の別の実験結果との関連性をまとめると、一つの研究の形となります。 学会発表や論文にするなら、最初の自分の妄想、仮説の元になった論文の原著を調べておく必要があります。
理研も当然やってるとは思いますが、理研は東大閥なので、人間関係上いろいろあるのでしょう(^◇^;)
ここでブログを書いて、分かり易く書ける様になって、それを私の他のブログでも実践すれば、そのブログも少しは喜んで貰える様になると思っています(^^)
私ン家の悩みの一部でもあるので(^_^;)
ひなパパさんの言うように 私も
こんないい事を教えてくれてるのに 何か勿体ない気がする・・・(´;ω;`)
理論に基づいた もう立派な論文だしいw (←見習え 理研w!)
もっと多くの人に読んで欲しいなあと思います
私の文章の様に、伝える側の理解が浅いほど、分かり易く伝えることが出来なくなります。
その場合、教える教員の算数に対する理解が浅いほど、子供達に分かり易く教えることが出来ません。
簡単に言うと、先生が算数をよく分かって無いので、教えられる子供達も分からないということでしょうか。
最近の教員は、書類書類で忙しく、子供に向き合う時間も、教える教科の理解を深める時間も無く、その為教科の理解も浅く、教える技術も養えないので、その教科が得意な子供しか理解できない様になってしまったのでしょう。
そもそも小学校の教員は、全教科を教えられることが前提となっているので、一つ一つの教科に精通することは出来ないのではないでしょうか。
つまり、学校に就職してから、教科の理解や教える技術を習得しなければならないのです。
「初歩的なことだから、簡単に教えられる」のでは無く、「初歩的なことだからこそ、教えるのは難しい」のです。
一般に、伝える側(講演者や教員など)は、それに対する質問をする側(講演会の聴衆や生徒など)よりも10倍以上詳しくなければ答えられないと言われています。
ただ、個人的意見としては、子供達に先生の印象が悪くなる様なことは言わない方が良いと思います。
生徒が先生を尊敬できなければ、教えられる教科の内容も、学校内の生活指導も、受け付けなくなる危険性があるからです。
一方、先生も、尊敬に値する様に日頃から努力する必要があります。
そして、文部科学省や教育委員会も、教員達が十分に努力できる様な環境、つまり時間的余裕がある教育環境作りをする必要があります。
また、政治家やマスコミも、教員に対する不必要な罵倒をするべきではありません。 子供達もテレビを視ています。
これらは教育界、国家全体の問題では無いでしょうか。
更に言えば、子供達の成長具合というものは一律では無く、身体が伸びる時期も、学ぶ力が伸びる時期も違いますので、現在の様な教育体制は人間の多様性に対応できていません。
ただ、これを言い出すと、結局ルソーの示した様な家庭教師による教育しかなくなってしまうので、きりがないのかもしれまん。
しかし、先生が子供達に向き合う余裕があれば、多少は対処可能ではないかと思います。
「女王の教室」なつかしい・・・大好きなドラマでした。
主演の天海祐希の演技もかっこよくて^^
で、勉強について・・・私は先生にも問題があると
思っています。「なぜ(算数)、できないの」と先生に
叱られ、「学校に行きたくない」とうちの子は
なってしまいました。
でも、私が家で解き方のコツを教え、(リズムをつかいます)
簡単にできるようになると、学校に行くのが楽しくなったようです。
大人が作った教科書を、子供に理解しろという・・・
そんなの無理に決まってます。
生徒は先生を選べない。教え方の下手な先生ほど
子供に「どうしてできないの」というのかもしれませんね。
私の普通のブログも、実はあります。
ただ、ここで書く様には、分かり易く書こうとしていませんし、私の強い感情が上乗せされている為、他の人が読んでも、面白くないものとなっています。
・・・自分の思ったことをぶつけている・・・みたいな感じでしょうか。
だから、ここで書くことは、私の良い学びになっているのだと思います(*^。^*)
学ぶのに年齢は関係無いと思います。
確かに、記憶力は若い時の方が遙かに優秀です。
しかし、記憶力というのは、多くの能力の中の一つでしかありません。
学ぶとは、知り得た知識を記憶することでは無く、自分がどう理解するか、自分の考えにどう組み込んでいくかを考え、結果的に認識していくことだと思います。
確かに、大昔の人類にとって、記憶は重要な要素だったと思います。
しかし、文字ができ、紙が発明され多くを記述することが出来るようになり、本ができて共有される様になり、インターネットによっていつでも参照できる様になったので、学びにおいて記憶力の重要性は減りました。
それを「人間のサイボーグ化」と批判する人もいますが、言葉や文字、本、インターネットなどの文明を積み上げたからこそ、思考力を高めることができる様になったのではないでしょうか。
いしころさんのブログを読んでいると、とても良い学びをされてきたことがよく分かります。
私にとって、とても良い学びになっています。
それにしても、「勉強」という文字は、それだけで嫌な気分になってしまうのは、私だけでしょうか。
眠くなった時の対処法として、私の提案も一つのやり方ですが、寝るというのも、自然な生理的解決法であり、一つの解決法だと思います。
また、眠いのを我慢して、学ぶことが嫌いになってしまったら、本末転倒ですしね(^^)
それに、眠いのを我慢すると、本文中に書いた様なストレスが脳にかかり、ストレスを緩和させる為、異常な食欲を誘導し、糖分の補充や満腹感による満足感を得ようとするそうです。
それは、肥満や糖尿病などの原因ともなりますし、健康を損なう恐れもあります。
ただ、脳だけの疲労に対して、どの様な寝方をしたら良いか、それはそれで非常に難しいのかも知れません。
「睡眠の科学」という新たな学問領域があり、勉強や事務仕事、また食後の満腹感による睡眠誘導などにおいて、どの時間帯にどの程度寝れば良いかが研究されています。
放送大学でその最新の知見が言われてましたが、すみません、忘れてしまいましたm(__)m
ただ、午前、午後、夕方で、それぞれ違いがあり、寝ない方がいい時間帯、30分程度寝た方が良い時間帯などがあった様です。
寝てはいけない時間帯に寝てしまうと、本来寝る必要がある時間帯に眠ることが出来なくなる場合もある様です。
その結果として睡眠の生活リズムが狂い、夜の本格的睡眠の時に脳から出る身体の修復ホルモンが十分に働けず、脳や肌、内臓、筋肉、骨などのを含む身体全体の新陳代謝が低下し、老化が進む場合もあるかもしれません。
その為、日中の睡眠には難しい点もありますが、我慢するよりは遙かに良いでしょう。
内容が理解できる様になれば、その分野の勉強を好きになり、本分にある様な興奮を得られるのではないでしょうか(=●^0^●=)
昔、「女王の教室」というドラマで次の様に言ってました。
子供達の、「何故、勉強をしなければならないのですか?」という質問に対して
女王先生は、「勉強はしなければならないものでは無く、したいと思うものなのです。」
つまり、世の中のいろいろな不思議なこと、自然の花の美しさや香りなどを感じた時、「何故なんだろう」、「どう表現したら良いのだろう」と思うことが動機となり、「学びたい」と思うのではないでしょうか。
受験、大変ですね、ご苦労様ですm(__)m
私は受験勉強に不向きな性格で、偏差値の低い大学にしか行っていません。
私は当時数学が大好きで、特に証明問題が好きでした。
好きな証明問題ですから、一つの問題に何時間でも考えるし、考えて考えて、解けずに疲れて寝る時間になると、その問題を考えながら寝ていました。
もし、受験勉強が得意な人であったなら、10分考えて分からなければ、解答を見て、その解答を覚えていくでしょう。 その方が効率がいいですよね。
でも、解けなかった問題を考えながら寝て、夢の中で解いて、そして朝起きて、実際に解けた時の感激は、何ものにも代え難い喜びでした。
だから、受験に成功したとは言えませんが、受験勉強は楽しかった・・・(;^_^A アセアセ…
三流大学とあえて書かないのは、所詮大学というのは自分で学ぶ場であって、どの大学に行ったとしても、本人次第で一流の学びが出来るからです。
ただ、現在では、大学の位置づけが「良い就職をする為の予備校」と考えられている場合が多いので、私の考え方はあまり受け入れられません(^◇^;)
日本の受験勉強や大学が、知識と技術の習得が主たる目的で、人類の将来を担う知恵や思考力、学ぶ力が軽視されているのは残念なことです。
ハーバード大学のサンデル教授の哲学の講義がテレビで公開されていますが、サンデル教授の話が面白いことも興味深いですが、そこに集っている学生の皆さんが、講義以前の予習し、柔軟な思考力を持ち、自分のそれまでの信念と新たな考え方を組み合わせた自分の考えを持って講義に出席していることに感心してしまいます。
その予習があった上で、サンデル教授の講義で討論し、その討論を踏まえた上で更に考えを深める・・・これが学ぶということではないかと思います。
ちなみに、私は大学に入って数年は、麻雀などで遊んでしまい、やっぱり三流学生でした(__;)
それでも、卒業研究で学んだタンパク質の構造のことは、現在でも視点の基礎となっています。
その視点をベースとして、社会に出てから学んだことがほとんどの様な気がします。
ニコタのブログでは、勿体ない気がする。
もっと、一般公開のブログにした方が、いいかもしれませんねぇ^^
フォロワーがたくさん来ますよ^^
学生の頃 学ぶことは嫌いじゃなかったけれど
勉強してると眠くなることが多くて
親に たしなめられ つらい思いをいっぱいしました
怠けているのじゃなくて フル回転しすぎた結果だったのですね
自分を責めることが多かった人生の前半でした
能力もないのに親に期待されて つらかった青春時代でした
本当に気が楽になりました ありがとうです
年を重ねて 自然に肩の力を抜く方法を自分なりにしていますが
深呼吸とか、理に適っているんですね
字数の制限の中で 読みやすくまとめてくださってあって本当にありがとうです(^^)/
「勉強してて、眠くなったら寝ていいよ」って家では
小学生の娘にそう言ってる私。
寝て、起きたらまたやればいいことだと。
勉強で、肝心なのは嫌いにならないことだと
思います。
眠くなるのは苦痛だから、かもしれませんね。
好きな事は眠くてもできるのに、いやな事は
「眠さが倍」になるのかも。
「・・・・勉強、好きになったら眠くならないよ」
って、理想論ですね。^^
一番大事なことは、勉強して眠くなることを羞じてはいけないことだと思います。
「頭の中の細胞が頑張ってくれて、嬉しい」と褒めてあげて下さいね(*^。^*)
そして、深呼吸したり、少し甘い物を食べたりして、ご褒美を渡してあげてください(^^)
私も勉強をすると眠くなっちゃうので、参考にさせていただきま~す^^
文字数制限の為、若干論理が飛躍している部分があるかもしれませんm(__)m
小学生の疑問に対する対処法は、ニコタではお子様がいらっしゃる女性も多いので、少しでも参考になれば幸いと思っています(^◇^;)
ブログ広場から参りました。
とても興味深いお話です。
ふむふむ、と読んでいて終末近く(「何故なら」からの段落)での思考(または論理)の飛躍が劇的で、最終的に小学生の疑問に自分なりの対処法を明確に述べているのがステキだと思いました。