神経痛とは・・・
- カテゴリ:30代以上
- 2014/09/03 18:28:27
(科学的な知見-放送大学で解説された脳の海馬における実験結果-と、私の推測を織り交ぜて書いてあるので、あくまで仮説です)
神経痛は、神経細胞における原始的記憶だと思う。
何かを覚えると言った普通の記憶は、脳において、神経細胞が手を伸ばし(樹状突起)、他の神経細胞に連絡するという、神経細胞同士が仲良くなり、ネットワークが出来上がる高レベルなものだそうです。
しかし、その高レベルな記憶も、脳の海馬と呼ばれる領域での原始的記憶から始まるらしい。
それでは、神経痛の原因でもある、神経細胞の原始的記憶とはどんなものか?
私の断片的知識と治療法からの考察から推論してみると・・・
刺激を受けた神経細胞は、伝言ゲームの様に繋がった次の細胞に信号を次々と送っていく。
神経細胞は胴体が長いので、化学的な電位差を利用して、電気的にその端っこまで信号を送っている。
問題は、その長い胴体の端っこと、次の神経細胞の受け渡し部分にある。
長い胴体の端っこには、神経伝達物質と呼ばれるものが溜まっていて、電気的な信号があると、それらを放出する。
次の神経細胞には、それらの神経伝達物質を受け取る為の受容体と呼ばれるタンパク質がある。
そして、この受容体と呼ばれるタンパク質には二種類あり、仮にそれらをA受容体、B受容体とする。
A受容体は、神経伝達物質がくっつくと、口を開いて、ナトリウムイオンを中に入れ、すぐにその胴体に電気信号を走らせる。
※ナトリウムイオンとは、塩の成分のナトリウムが、水に溶け、電子が一つ減った状態の+(プラス)の電荷を持っている原子のこと。
しかし、B受容体は、神経伝達物質がくっついただけでは、口を開かない、なかなか強情なのだ。
その部分には、A受容体も、B受容体もたくさんあるのだが、それでも数に限りがあり、あまり多くの神経伝達物質があると、くっつく為の受容体が無く、溢れてしまう。
通常ならば、その溢れた神経伝達物質は、分解されたりして消えてしまうのだが、強い刺激が連続して起こると、分解が追いつかないものも出てくる。
ところで、神経細胞の周りには、グリア細胞と呼ばれる細胞があり、そのグリア細胞にも神経伝達物質を受け取る受容体がある。
強い刺激の為に、分解もされずに溢れてしまった神経伝達物質は、このグリア細胞の受容体にくっついてしまうのである。
このグリア細胞の受容体は、神経伝達物質がくっつくと、口を開け、カルシウムイオンを細胞の中に入れ、そのカルシウムイオンが細胞内の酵素を刺激し(活性化)、D-セリンというアミノ酸を放出する。
※カルシウムイオンとは、骨の成分のカルシウムから電子が二つ減り、水に溶けた原子のこと。 様々な酵素を活動できる様にする働きがある。
※D-セリンとは、セリンというアミノ酸の一種なのだが、アミノ酸にはDタイプとLタイプの二種類あり、普通のタンパク質に含まれるのは全部Lタイプなのに対し、それとはタイプの違うDタイプのもの。
このD-セリンが、先ほどの神経伝達物質がくっついても口を開かないB受容体にくっつくと、口を開けてしまうのだ。
しかも、この口から入ってくるのは、ナトリウムイオンだけで無く、カルシウムイオンも入れてしまう。
この神経細胞内に入ってきたカルシウムイオンは、細胞内の様々な反応を活発にして、その結果、A受容体となるタンパク質を大量に作りだす。
その為、その神経細胞の神経伝達物質を受け取る部分のA受容体の数が飛躍的に増えることとなる。
つまり、数多くの神経伝達物質をくっつけることが出来る様になり、更に多くのナトリウムイオンを中に入れることが出来る様になる。
簡単に言えば、すごく敏感になってしまうのである。
そして、同じ様なことが、伝言ゲームの様に繋がっている神経細胞に次々に起こり、その伝言ゲームの様な刺激を伝える系統自体がどんどん敏感になってしまうのである。
その為、少しの刺激がどんどん増幅して伝わってしまう為、本来無視できる様な刺激に対しても、強い信号が脳に届いてしまうのである。
そして、その敏感さは、タンパク質で作られた受容体が原因で、タンパク質はそう簡単には分解されない為、「受容体の数が多い」という敏感さが、しばらく維持されてしまう。
※余った神経伝達物質の分解は素早く起こるのに対して、受容体を減らすには、その受容体タンパク質が徐々に劣化していくのを待つか、神経細胞自体が新しくなるしかないのかもしれない。 何故なら、消化管と違い、神経細胞はデリケートなので、安易にタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)を働かせる訳にはいかないのでは無いかと推測できるからである。
これが、神経細胞における原始的記憶であり、その刺激が「痛み」であった場合は神経痛となる。
更に悪いことに、その刺激が伝言ゲームに伝わる度に、その敏感さは保存されてしまうので、神経痛の治療には長い時間がかかってしまうのである。





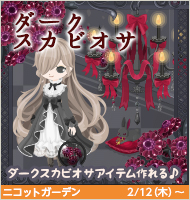

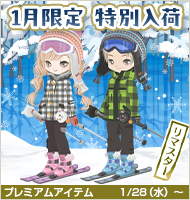


















恐らく、幻肢痛のことだと思います。
不幸にも身体の一部を切断されてしまった方が、その切断面におきている感覚が脳に伝わった痛みです。
その痛みを感じていた切断面の神経は、本来切断されてしまった部分のある場所(例えば人差し指など)に繋がっていたもので、脳はその神経による刺激を、その場所(人差し指など)の痛みと記憶している為、その痛みはその部分(人差し指など)の痛みだと感じてしまうことです。
幻の四肢の痛みなので、幻肢痛と呼ばれています。
昔、救命病棟24時というドラマで知りました(^^)
私の母親が数年前に大腿骨を骨折し、大手術でチタン合金でできた人工代替骨を入れましたが、今でも少し足先の方まで痛みがある様です。
恐らく、手術の時に大腿部の神経がかなり切断されたと考えられ、その神経の切断面での痛みが、足先の痛みとして脳に伝わってくるのでしょう。
足先は幻ではありませんが、足先の痛みでは無いのに足先の痛みと感じるので、これも幻肢痛の一つだと言って良いのだと思います。
ちなみに母親は高齢ですので、本来自然治癒に任せると車椅子生活になってしまうのですが、この手術のお陰で今でも歩くことが出来ています。
ただ、人工物なので、転ぶと簡単に脱臼し、そうなると車椅子生活を余儀なくされてしまうので、お医者さんからは「絶対に転ばないように」と注意されています。
また、地べたに座ると脱臼し易いので、家の中は全て椅子とベッドの生活となりました。
骨髄、特に大腿骨の骨髄は骨髄幹細胞と呼ばれる造血システムがあり、赤血球や白血球、リンパ球などが作られています。
その為、私としては、貧血と免疫力の低下を心配したので、ビタミンミネラルの健康食品とヤ○ルトを毎食飲む様に言っています。
でも、風邪が前よりひきにくくなって、免疫力が低下したということも無く、貧血もおきていないので、それほど心配する必要は無い様です。
意外と、大腿骨に突き刺しているチタン合金の代替骨が、骨髄幹細胞を刺激して、免疫力を上昇させているのかも・・・
私は、優しい気持ちの時は「ですます調」、強い思いがある時は「である調」、不安定だったり、書いている途中で気分が変わった時は混合されてしまうので、読みづらいと思いますm(__)m
グリア細胞の存在がA受容体を増やし 取り込むナトリウムイオンの量を増やして
電気信号を送るのですね・・それが痛みとなって届くから 敏感になる・・
ひとつひとつを噛み砕いて説明されているので何となくわかるような気がします
痛みの記憶ってあるようですね 原始痛って言われるらしいですけれど
痛みを感じるものがなくても 記憶した痛みを実際にはない場所に感じてしまうらしいですね
人体の神秘はごくごく一部しかわかっていないですね
図に表わすともっとわかりやすいでしょうけれど 言葉だけで分かりやすく表現されているのには
驚きです。いつも勉強になります あrがとうございます
恥ずかしいのですけれど 数回読ませていただかないと 頭に入ってきません。
昔から 頭の構造が緩やかにできているようで あはは (^^)/
図があれば、もう少し分かり易くなるのですが、ちょと文章だけでは説明が難しい(^◇^;)
あららら・・・そりゃ、失敗でした(__;)
力不足で申し訳ありませんm(__)m
けど、やっぱり博士だなぁ^^