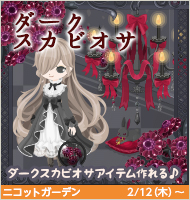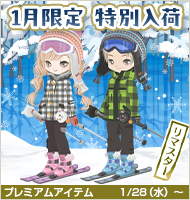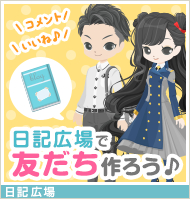■近代文藝之研究|講話|劇場問題(5)
- カテゴリ:その他
- 2013/12/15 23:49:07
■近代文藝之研究|講話|劇場問題 (5)
先年英吉利畫界の耆宿であるアルマ・タデマなどが發起人となつて、主なる書割畫家の爲に會を開いた事がある。其主意とする所は、從來書割畫家は一種特殊な畫家と認められて居た、腕一つで世人が非常な樂みを舞臺の上に與へられて居るに關らず、やゝともすれば美術家たる地位を認められない、故に書割畫家も嚴然たる美術家たるを表彰せんが爲め此會を開くといふ趣意であつた。其時ジョセフ・ハーカーといふ有名な書割畫家の話の一節が一寸おもしろいから引て見ると、書割の進歩は一世紀以來特に著しい、最近に到りてはかのアーヴヰングの此方面に於ける非常な熱心が目覺しい進歩を喚び起した、また近時此書割を進歩せしむる重なる理由は、第一が電燈の發明である、此光は極めて物を細いところまで明瞭と見せる光であつて、其色が眞白で瓦斯の光などの如く赤い柔い所が少もなく、それが爲め少しも眞實に背いた事を書く譯にいかない、これが書割を寫實の方に進歩せしむる理由の一つである。次には畫家自からの間の競爭といふ事が激しくなつて來た、旅興行に出かける一座は近年は皆其書割を携帶して行く便利が出來て來て、これが爲め從來各座に於て座附の書割畫家を抱へて居たのが無用になつて來て、上手な人に頼んで描て貰つて何所へでも持つて行ける是が拙い書割畫家を無くする一の理由となつた。(これは言ふまでもなく西洋の書割はドロップスといつて上から下すやうに出來てゐて捲て仕舞ふ事の出來る大きな布に描くから携帶が自由になつてゐるのである。また昔は此布が高價であつたために、一つの布で其座に畫家を抱へて置て興行毎に塗消して書き更へたものであるが、それが今日では一度描いたものは其儘置て持廻つて利用する便利が開けたのである。)次は
--------------------
*註1:先年英吉利
原本では文頭は前ページの文末より改行なしでつづいている。
*註2:畫界・畫家
「畫」の俗字体(一説に本字とも)。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/ga_kaku.jpg
*註3:アルマ・タデマ
ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema/1836年~1912年)のこと。オランダ生まれのイギリスの画家。古代ローマ、古代ギリシア、古代エジプトなどの歴史をテーマにした写実的な絵で有名。
[参照]⇒http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lawrence_Alma-Tadema
*註4:發起人・喚び起した
「起」の正字体。旁の「己」が「巳」。
*註5:書割
「割」
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/katsu_waru.jpg
*註6:主意とする所・柔い所・何所
「所」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/tokoro.jpg
*註7:認められて・認められない
「認」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/mitomeru.jpg
*註8:ジョセフ・ハーカー
Joseph Harker の綴りかと思われるが、生没年等の詳細は不明。19世紀末~20世紀初頭のイギリス演劇界において、テルヴィン、ハウズ・クラーヴェン(「ホーズ・クレイヴン」とも表記/Henry Hawes Craven Green)らとともに並び称された一流の舞台美術デザイナー。下記参照 URL はそのジョセフ・ハーカーの書割作画中の動画かと思われるので紹介する。
[参照]⇒http://www.britishpathe.com/video/forty-foot-art-a-camera-interview-with-mr-joseph
*註9:一節
「節」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/setsu_hushi.jpg
*註10:進歩
「進」の旧字体。「シンニョウ」は「二点シンニョウ」。
*註11:世紀
「紀」の俗字(か?)。「糸」+「已」。
*註12:著しい
「著」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/tyo_arawasu.jpg
*註13:最近・近時・近年
「近」の旧字体。「シンニョウ」は「二点シンニョウ」。
*註14:熱心
「熱」の俗字体(か?)。「執」+「レンガ(レッカ)」。下記 URL の文字は作字したもの。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/sakuji_netsu.jpg
*註15:瓦斯
「瓦」の俗字体(か?)。「一」+「九」+「ン」。Unicode にも文字種がないようなので作字してみた。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/ga_kawara.jpg
*註16:便利
「便」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/ben_tayori.jpg
*註17:抱へて
「抱」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/hou_daku.jpg
*註18:頼んで
「頼」の旧字体。旁の「頁」が「刀」+「貝」。
*註19:塗消して
「消」の旧字体。旁の「ナオガシラ」は「小」。
*註20:書き更へた
「更」の旧字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/sara.jpg
*註21:次は
「次」の正字体。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/moji/ji_tsugi.jpg
--------------------
■抱月『近代文藝之研究』を註記なしに通しで読みたいかたは、こちらをどうぞ。
http://www5e.biglobe.ne.jp/%7Ehanadada/tougetsu/kbk_tobira.html
■このテキストの原本は国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」収録の「近代文芸之研究 / 島村抱月(滝太郎)著 早稲田大学出版部, 明42.6」の画像データに依っています。
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/871630/1