弘法筆を選ばず。じゃあ、常人は、
- カテゴリ:アート/デザイン
- 2009/08/02 23:56:22
どういう意味なんだろうねぇ、
「弘法筆を選ばず」
一般的には、「弘法大師ほど書に通じた人は、どんな筆でも、良い書を記す」ということらしい。
だから、慣用句として、「優れた人は、ささいなことで、結果を左右されない」となるらしい。
ん〜、そうなんだよねぇ。
納得できる話だよね〜。
でも、なんだか、僕の中での感覚と、慣用句に、ズレがあるような気がする。
空海について書かれた本を読むと、どうも、空海の書って、決まった形式が無いということらしい。
いつも違った筆跡を記す。
時と場所によって変わる。
空海の言動で、こんな話があるそうだ。
ある時、天皇が素晴らしい書を手に入れたので、空海に見に来るように誘った。
日頃、天皇と空海は、書を通じて親交があったらしい。
天皇が唐から輸入した書の中で、とても優れた物があったので、日本で最も書に優れた空海に見せようということ。
これが、ただの親切で見せてあげようというのではなくて、どうやら本音は、空海よりも優れた人間がいることを見せつけて、暗に「お前は世界一じゃないんだぞ」と天皇は言いたかったらしい。
ちょっと余談だけど、この天皇の態度、政治家が持っている「権威」に対する感じ方のようなものが見えて、面白い。
さて空海、この書を見て言った「ああ、これは私が書きました」。
中国に住んでいる間に書いたものだという。
天皇にしてみると、明らかに、空海が日頃書いている書と違う。
輸入した書のほうが、優れているように感じる。
だから天皇は、「お前の書よりも、この書のほうが、明らかに上ではないか」と言った。
すると空海は答えた。
「書というのは、書いた場所が現れる」と言う。「雄大な土地に住み、雄大な心境になれば、書いたものもそのようになる。貧しいところでは、書も、貧しくなる」
さらに、天皇に言う。「今の自分は日本に居る。現在の自分の書は、そういうものである」
つまり、日本の長である天皇に向かって、「日本はそういう所だ」と言った。
さて、それでですね、空海の話はここまでとして、僕は考えるわけです。
空海の感性が、本当に、この話のようなものなら、「筆を選ばず」は、どんな筆でも上手な書を記すということではないだろう。
古い筆なら、古い筆のような書になるし、癖の在る筆なら、癖のある書になる。
そういうことだろう。
ここで大切なのは、単純に技術を論じているわけではないということ。
たとえば、僕には、「適材適所」という言葉に共通性を感じる。
「適材適所」の意味は、おおざっぱにいえば、専用の道具を使えということだろう。
「選ばず」とは正反対に感じる人もいるかもしれないが、僕は、相通じる言葉だと思う。
手にとった筆に、最も適した書が、空海の中から現れるのである。
空海は、手にした筆がどんなものか、感じ取って、自分の中へ受け入れる。
この、内と外、宇宙全体、という関係性が、空海の密教だ。
—————
え〜、なんとなく、
ニコンの高級、高性能レンズが欲しいなぁ〜
などと思いながら、
常人は、良い筆を与えなければ、良い結果を得るのは難しい
などと考えながら、
日食の時は、大日如来って何を感じているんだろう?
とか、妄想したのです。





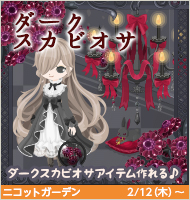




















太陽が動き続けるから、季節が移り変わる。
季節とともに、生き物は生き続ける。
この世の全ては、このリズムで生きている。
単純化すれば、これが密教の根本原理ですね。
それで、大日如来がこの世の全てであり、中心でもある。となるわけです。
渡り鳥は季節によって移動し、自分の住みやすい土地に住む。
土地の気象は、太陽に支配されているのであって、渡り鳥もまた、太陽とともに生きている。
じゃあ、人間は?
その問いが密教です。
だから、人間が、住む土地によって違った精神を持つし、行いも変わる。
書もまた変わる。
書が変わることもまた、大日如来の意思である。
天皇に向かって、日本なんてさほどの国でもないし、その長だからといってたいしたことでもない。
と言っちゃう空海もむちゃくちゃな人だけど、
思想の裏付けも持ってるわけですね。